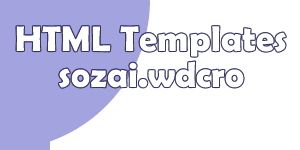Hi’z 5 Errand〜はいず 5 えらんど〜
トーキョーN◎VA-The-Detonation
小説
シーン8 “魔を断つ剣”〜ハースニール〜
マキシマム・揚も続いて出て行く。
すれ違いざまに来栖が呟く。表情には、憮然としていた。
「後悔しています。あなたの依頼を受けたことを」
「そうか。悪かったな」
マキシマム・揚が表情を変えず答える。
「何も思わないのですか?」
「俺のせいだと言いたいのか? この結果は、彼女の選択によってもたらされたものだ」
マキシマム・揚が突き放すように言うとそのまま部屋から出て行った。
マキシマム・揚が出て行った後、来栖は、拳を畳に叩きつけた。
「優。私達も行こう」
アリーシアが来栖に立ち上がるように促すと来栖と共に部屋から出て行く。
アリーシアと来栖が廊下を無言で進む。アリーシアが立ち止まる。
「ねえ。優」
「なんだ?」
来栖が不機嫌な声で答えアリーシアを見る。
「マキシマム・揚は、白耀姫を騙しているのよ」
アリーシアが来栖の瞳を覗き込みながら言った。
アリーシアの瞳は、澄んだ青色から血に濡れたような赤に変わっている。
「そうなのか?」
来栖が魅入られたような目でアリーシアを見つめながら問い返す。
「そうよ。だから優、マキシマム・揚を倒せば白耀姫が出て行く必要はなくなるわ」
妖艶な甘い声が来栖の心を支配していく。
「急ごう。まだ遠くに行ってないはずだ」
「そうね。急ぎましょう」
来栖とアリーシアが境内へと急ぐ。
そして来栖は、境内を歩くマキシマム・揚と白耀姫を呼び止める。
「ちょっと待て」
二人がその声に振り返る。
「何の用だ?」
マキシマム・揚が冷たい声で来栖に問い返す。
「白耀姫さん。あなたが出て行く必要はない。あなたは、彼に騙されているんだ」
来栖がマキシマム・揚をびしっと人差し指を突きつける。
「冗談に付き合っている暇はない。行こう」
マキシマム・揚が来栖に背を向け白耀姫を促す。
「待て。こやつ魔に魅入られているようじゃ」
白耀姫が重々しい声で言った。顔つきも厳しいものになる。
「だとしても今の俺達には関係ないことだ」
「こやつ敵の刺客に操られているかもしれん。後々厄介なことになるやも知れんぞ」
白耀姫が前に出て来栖と対峙しようとする。
マキシマム・揚が白耀姫を手で制して前に出ると来栖と対峙する。
「それで俺が彼女を騙しているとしてお前は、どうするつもりだ」
「あなたを倒して彼女を助けます」
マキシマム・揚が侮蔑の目で来栖を見る。そしてやる気なさそうに手招きする。
「操ってるのはどいつだ?」
マキシマム・揚が後ろにいる白耀姫に尋ねる。
「あの娘じゃ。あの娘から魔の気配を感じる」
白耀姫が顎で来栖の後ろに立つアリーシアを示す。
「わかった。俺がけりをつけるから手をだすな」
白耀姫が意外そうな顔でマキシマム・揚を見る。
「優しいのじゃな」
「お前に何かあると困る。中華街を救うために無事でいてもらわなければならん」
マキシマム・揚が素っ気無く答える。来栖が朗々と声を上げる。
「汝は、運命より全てを守る我が盾。汝は、運命を全て断ち切る我が剣」
来栖が右手を天に掲げる。
「我は、汝の全ての力を欲す。我が手へ疾く来たれ!」
しかし掲げた右手には、剣は現れなかった。来栖が思わず掲げた右手を見る。
「そんな馬鹿な」
来栖が愕然となり呟く。その隙を見逃さずマキシマム・揚が紫電のような速さで瞬く間に間合いを詰める。
そして来栖のがら空きの鳩尾に左足で前蹴りを叩き込む。
来栖が後方へ蹴り飛ばされ石畳を勢いよく転がり狛犬にぶつかりようやく止まる。
来栖の意識がぷっつりと途切れる。
マキシマム・揚は、そのまま踏み込みアリーシアを間合いに捉える。
「やめて。あなたは、女性を襲うような人じゃないでしょ」
アリーシアが妖艶な笑みと共に甘い声がマキシマム・揚の心に忍び寄る。
「悪いな。あんたは、俺の好みじゃない」
マキシマム・揚が構わず右上段回し蹴りを放つ。
蹴りは、アリーシアをすり抜けた。哄笑を上げアリーシアの姿が消えていく。
「逃がしたか」
マキシマム・揚が忌々しそうに舌打ちすると白耀姫の所に戻っていく。
「敵の手がここまで迫っているとなると一刻を争うな」
「そうじゃな。急がねばならぬ」
マキシマム・揚が手を差し出す。
「なんじゃ?」
白耀姫が不審そうにその手を見る。
「中華街に転移する」
「なるほど。わかった」
白耀姫がマキシマム・揚の手を握る。マキシマム・揚は、ゆっくりと息を吐き出し全身の力を抜く。
そしてふらふらと体を揺らした後、踵を石畳に打ちつけた。
音と同時にマキシマム・揚と白耀姫の姿は、霧のように消えた。
どこからか自分を呼ぶ声がする。ゆっくりと来栖が目を開く。
目に飛び込んできたのは、来栖の見覚えがある木の杖を持ち長い白い髭が印象的な老人の顔だった。
来栖に剣を手渡してくれた占い師だった。
「じいさん。久しぶりだな」
どうやら自分は、地面に寝ているらしい。背中に石畳の冷たい感触を感じる。
辺りを見回す。石畳があり神社も遠くに見えるが風景がおかしい。
遠くに見える風景が白い霧のようなものに覆われ何も見えない。
空から見ると恐らく神社一帯だけを切り取り宙に浮いているように見えるだろう。
「じいさん。ここどこだ」
来栖が立ち上がり占い師に尋ねる。
「アストラル界じゃ。お若いの。また忘れ物を届けに来たぞ」
占い師が来栖に飾りつきの鞘に収められた柄に大きなダイアモンドがはまった白銀の剣を差し出す。
来栖が剣を掴む。来栖の手に痺れが走り慌てて手を引っ込める。
剣が来栖を拒んでいるかのようだった。
「なあ。じいさん。この剣を握ろうとすると手に痺れが走るんだが」
占い師が長い髭をしごく。
「ふむ。それは、お主が剣を粗末に扱ったから怒っておるのじゃろう」
「剣が怒る? そんなことがあるのか?」
来栖が信じられないといった表情で首をかしげる。
「ある。この剣は、ただの剣ではない。明確な意思を持ち魔物を倒す剣じゃ。
どれ。お主にもわかりやすく剣の意志を見せようか」
占い師が呪文を唱える。剣が輝き閃光が辺りを照らす。閃光が収まり人影が現れる。
そこには、西洋鎧に身を包み砂金をまぶしたように輝く髪を青いリボンで後ろにまとめた凛々しい顔の小柄な女性が立っていた。
そしてその腰には、飾りつきの鞘に収められた柄に大きなダイアモンドがはまった白銀の剣を差していた。
「我が名は、ハースニール。ダイアモンドの騎士の剣なり」
鋼のように硬く冷ややかな声で来栖に告げた。
そして抜く手も見せず来栖の首に剣の切っ先を突きつける。
「問おう。貴方が私のマスターか」
「・・・そうだ」
来栖が動揺し上ずった声で答える。背中は、冷や汗で冷たい。
「ならばなぜ私を捨てたのか」
「悪かった。反省している」
来栖が素直に頭を下げあやまる。ハースニールがあきれた表情を見せる。
「貴方は、自分のしたことがまだわかってないようだな。確かに私は、貴方と契約した。
だが私を捨てたということは、契約を破棄したと考えざるをえない」
確かにそう思われても仕方ない。来栖が言い返せず沈黙する。
「あまつさえ恋人に化けたアヤカシを見抜けず騙される始末。
これでは、力量不足と言わざるをえない。それでも貴方は、騎士たる資格を持つ者なのか」
ハースニールは、淡々と来栖の非難を続ける。
「たぶん・・・。そうなんだよな。じいさん」
助けを求めるように来栖が占い師の方を見る。
占い師は、好々爺とした笑いを浮かべ何も答えなかった。
「騎士の自覚がないのは、更に問題だ」
ハースニールが冷たく言う。
「・・・俺には、お前の力が必要なんだ」
果たさねばならない誓いがあるし何より三流探偵が生き抜く為には剣の力が必要不可欠だ。
「ならば試させてもらおう。私を使う力量と資格が貴方にあるのどうか」
ハースニールが来栖の首から剣を引き軽やかに後方へ飛ぶと青眼に構える。
「私からこの剣を奪えば貴方の力量と資格を認めよう」
「ちょっと待て。俺は、素手だぞ。武器無しで戦えっていうのか?」
来栖が止めるように両手を広げ慌てて言った。
剣を持った相手に無手で挑むなど殺してくださいと言っているのと同じだ。
「武器がない? 異な事を言う。貴方には、両手に両足という立派な武器がある。
それに目に見える武器だけが力ではない」
ハースニールがさも当然という口調で言った。
言われてみれば確かにそうだ。来栖が思わず納得する。
頷くと来栖が占い師を巻き込まないように石畳の方へ歩く。
間合いを十分に取りハースニールと対峙する。
距離は、約十メートル。剣を振るうには遠すぎる間合いだ。
「異論はないようだな。では始める」
ハースニールがぶんと横薙ぎに剣を振う。だが剣の届く間合いではない。
来栖の探偵の勘が危険を告げる。
「やべっ!」
言うが早いか石畳に身を投げ出す。その上を不可視の刃が風切り音と共に通過する。
「やばかった・・・。あの剣がカマイタチを放てること忘れていた・・・・」
来栖がほっと一息つく。
カマイタチに気がつかなかったら恐らく胴体を真っ二つにされていただろう。
「甘いぞ」
ハースニールが剣を上段から振り下ろす。カマイタチが石畳を切り裂きながら来栖に迫る。
来栖が慌ててカマイタチの直線上から飛びのく。
「縦のカマイタチと横のカマイタチか。厄介な」
自分の武器は、両手と両足、それに当てにならない探偵の勘だけだ。
それを確認し来栖は、神と悪魔を心の中で罵る。
全然、勝てる気がしないぞ。俺の人生っていつも勝ち目のない勝負ばかりだ。
そんなことを考えつつも次々放たれるカマイタチを右に左に転がり或いは、飛びのきながら回避する。
「逃げてばかりでは勝てぬぞ」
小柄な体にどこにそんな体力があるのかと思うほどハースニールが剣を絶え間なく
縦横無尽に振り続ける。
「好きで逃げてるわけじゃねぇよ」
転がり或いは飛び無様な姿でカマイタチから逃げ回りつつ作戦を考える。
まずハースニールに接近しないと勝負にならないこと。
次にカマイタチをよけながらハースニールに接近できるほど運動神経はよくない。
となればおのずと作戦の方針が決まる。
来栖が辺りを見回し目当ての物を見つける
「ま、やってみるか」
来栖が駆け出す。ハースニールの方ではなくまったく見当違いの方へ駆け出す。
「逃がすか!」
ハースニールが剣を横薙ぎに振う。
カマイタチが不気味な音を立て来栖に向かって飛んでくる。
来栖は、身を屈めスライディングしカマイタチをかわしそのまま見つけた目当てのものの後ろに滑り込む。
「ふう。やれやれ。これで一息つける」
来栖が立ち上がり服の埃を手で払う。
「出て来い! 卑怯だぞ!」
ハースニールが声を荒げ叫ぶ。来栖がひょっこりと障害物の後ろから首を出す。
ハースニールは、烈火のごとく怒っている。それも来栖の行為を考えれば当然だろう。
「人の後ろにこそこそ隠れるなどそれでも騎士か!」
来栖が隠れているのは事態を傍観している占い師の背後だ。
来栖をカマイタチで攻撃するためには占い師を必ず巻き込んでしまう。
占い師の背後こそカマイタチから身を守る唯一の安全地帯だ。
「そっちこそカマイタチで遠距離からいやらしくねちねち攻撃してきやがって。
それでも騎士の剣かよ。騎士らしく正面から正々堂々と戦え」
来栖が負けずに言い返す。その言葉に占い師は、面白そうに笑っている。
占い師の背後にいる限りハースニールは、カマイタチで攻撃してこないだろう。
となれば自分から接近してくるに違いない。
「さて、次の手を考えるか」
首をひっこめ占い師の後ろで来栖が再び考え込む。
まずハースニールが接近してきた後、どうなるか。
「斬ってくるんだろうな。なんてたって騎士の剣のだし」
次に自分の武器を確認する。
「殴ると蹴るか。どうやって剣を奪えばいい?」
真っ先に思いついたのは時代劇でよく見る真剣白羽取り。
「できるわけねぇだろ。俺、しがない三流の探偵だぞ」
来栖が頭を抱える。とりあえず殴ってその隙に剣を奪うか。
そうしている間にもハースニールが占い師の背後に回り込み来栖の正面に立つ。
「さあ、これで文句はないな。行くぞ!」
言うが早いかハースニールは、豹を思わせる走りで一気に間合いを詰める。
そして剣を大上段に振り上げる。
気合の声と共に剣が瀑布を思わせる力強さと速さで来栖に向かって振り下ろされる。
慌てて来栖が腰砕けで剣の落下点から逃げる。
剣は、落下点の石畳を砕き巻き上げる。
更に土埃を巻き上げハースニールの体を包む。
来栖は、逃げたおかげで土埃の範囲外にいる。
来栖からは、ハースニールらしき人影が見えている。
だがハースニールは、土埃で視界を遮られている。来栖の姿は、見えないはずだ。
自分は、今始めてこの戦いで有利になったのだ。
「チャンス!」
言うが早いか来栖が土埃に見える人影に向かい右拳を繰り出す。
人影の目前で拳が鈍い音と共に見えない壁にぶつかったかのように止まる。
「しまった! 鞘の能力を忘れてた!」
「恩知らずだな」
ハースニールの持つ剣は、カマイタチを放つ力と魔を退ける力と鉄すら軽々と切断する鋭い切れ味を持ち
更に契約者の願いをかなえるまで戦いを続けさせる呪いをかける。
そして飾りつきの鞘には、持ち主を守り死から遠ざける力を持つ。
来栖も鞘の能力に何度も命を助けられた。
うっかりとそのことを忘れていたのは、確かに恩知らずと言われても何も言い返せない。
土埃が晴れハースニールの姿が現れる。
土埃の中にいたにも関わらず身を包む鎧と青眼に構えている剣は、白銀に輝いている。
「覚悟はいいか?」
「よくない」
言うが早いか来栖は、ハースニールにくるりと背を向け走り出す。
「往生際が悪いぞ」
ハースニールが来栖を追いかける。来栖は、逃げつつ次の作戦を考える。
あの障壁がある限り殴ったり蹴ったりしても無駄。
真剣白羽取りも無理。でも剣を奪わなければならない。さて、どうする?
来栖は、無い知恵を総動員し考える。そして一つの考えが浮かぶ。
「これしか手がなさそうだな・・・」
思いついた策にため息をつき心の中で神と悪魔を思いっきり罵る。
この作戦が失敗すると恐らく死ぬだろう。
来栖が覚悟を決める。
「よし。やるぞ!」
来栖が意気込んだ瞬間、足がもつれ石畳に顔から倒れこむ。
「いててて・・・」
来栖が鼻を抑えつつ立ち上がろうとする。
目の前には、突きつけられた剣の切っ先があった。
「終わりだ」
表情を変えることなくハースニールが冷たく来栖に告げる。
来栖もあきらめたような表情を浮かべる。
切っ先がいったん引かれ次の瞬間、放たれた矢のように来栖の心臓に迫る。
来栖が身をよじり心臓から切っ先を外す。
剣は、心臓を外れ右肩を刺し貫く。剣の先端が貫通し来栖の背中に姿を現していた。
切っ先から鮮血がしたたり石畳を赤く染める。
「・・・やっと捕まえた」
来栖が苦痛に顔を歪ませながら呟く。そして左手で剣の柄を掴む。
「まさか・・・」
ハースニールが何かに気がついたように驚きの表情を見せる。
「ああ、わざと刺された。これしか捕まえる手段が思い浮かばなかったからな」
来栖には、わざと刺されて剣を捕まえるという作戦しか思い浮かばなかった。
振られた剣を止めることは来栖には不可能。
かといって殴ったり蹴ったりしてもハースニールは、隙を見せない。
ならば突かれたなら剣の長さの分で止まるだろうという安直な考えだった。
もし斬られたなら鋭い切れ味により問答無用で両断されてしまうため斬られるわけにはいかなかった。
そのためにわざと転び突きがくる確率を上げた。
なぜなら最初にハースニールが剣を突きつけてきたのが印象に残っていたからだ。
再び剣を突きつけるような状況に身を置けば今度は突いてくるだろうという読みだった。
もし斬られたならば来栖は、成す術も無く死んでいただろう。
「賭けだったんだが何とか上手くいったな」
来栖が苦笑しながら柄を離さないようにしっかりと握る。
「残念ながら勝利条件は、私から剣を奪うことです。
捕まえただけでは勝利条件を満たしていません」
「そうか・・・。参ったな」
来栖が消えそうな声で言った。出血からか青ざめてきている。
「参ったとは?」
ハースニールが不思議そうに首をかしげる。
「予想以上に痛い。それに力が入らなくなってきた。やばい・・・かも」
そう言うと来栖が瞳を閉じる。柄を握っていた左手が柄からずり落ちる。
遠くか誰かがら自分を必死に呼ぶ声が聞こえる。
そう思いながら来栖の意識は、眠るように薄らいでいった。
すれ違いざまに来栖が呟く。表情には、憮然としていた。
「後悔しています。あなたの依頼を受けたことを」
「そうか。悪かったな」
マキシマム・揚が表情を変えず答える。
「何も思わないのですか?」
「俺のせいだと言いたいのか? この結果は、彼女の選択によってもたらされたものだ」
マキシマム・揚が突き放すように言うとそのまま部屋から出て行った。
マキシマム・揚が出て行った後、来栖は、拳を畳に叩きつけた。
「優。私達も行こう」
アリーシアが来栖に立ち上がるように促すと来栖と共に部屋から出て行く。
アリーシアと来栖が廊下を無言で進む。アリーシアが立ち止まる。
「ねえ。優」
「なんだ?」
来栖が不機嫌な声で答えアリーシアを見る。
「マキシマム・揚は、白耀姫を騙しているのよ」
アリーシアが来栖の瞳を覗き込みながら言った。
アリーシアの瞳は、澄んだ青色から血に濡れたような赤に変わっている。
「そうなのか?」
来栖が魅入られたような目でアリーシアを見つめながら問い返す。
「そうよ。だから優、マキシマム・揚を倒せば白耀姫が出て行く必要はなくなるわ」
妖艶な甘い声が来栖の心を支配していく。
「急ごう。まだ遠くに行ってないはずだ」
「そうね。急ぎましょう」
来栖とアリーシアが境内へと急ぐ。
そして来栖は、境内を歩くマキシマム・揚と白耀姫を呼び止める。
「ちょっと待て」
二人がその声に振り返る。
「何の用だ?」
マキシマム・揚が冷たい声で来栖に問い返す。
「白耀姫さん。あなたが出て行く必要はない。あなたは、彼に騙されているんだ」
来栖がマキシマム・揚をびしっと人差し指を突きつける。
「冗談に付き合っている暇はない。行こう」
マキシマム・揚が来栖に背を向け白耀姫を促す。
「待て。こやつ魔に魅入られているようじゃ」
白耀姫が重々しい声で言った。顔つきも厳しいものになる。
「だとしても今の俺達には関係ないことだ」
「こやつ敵の刺客に操られているかもしれん。後々厄介なことになるやも知れんぞ」
白耀姫が前に出て来栖と対峙しようとする。
マキシマム・揚が白耀姫を手で制して前に出ると来栖と対峙する。
「それで俺が彼女を騙しているとしてお前は、どうするつもりだ」
「あなたを倒して彼女を助けます」
マキシマム・揚が侮蔑の目で来栖を見る。そしてやる気なさそうに手招きする。
「操ってるのはどいつだ?」
マキシマム・揚が後ろにいる白耀姫に尋ねる。
「あの娘じゃ。あの娘から魔の気配を感じる」
白耀姫が顎で来栖の後ろに立つアリーシアを示す。
「わかった。俺がけりをつけるから手をだすな」
白耀姫が意外そうな顔でマキシマム・揚を見る。
「優しいのじゃな」
「お前に何かあると困る。中華街を救うために無事でいてもらわなければならん」
マキシマム・揚が素っ気無く答える。来栖が朗々と声を上げる。
「汝は、運命より全てを守る我が盾。汝は、運命を全て断ち切る我が剣」
来栖が右手を天に掲げる。
「我は、汝の全ての力を欲す。我が手へ疾く来たれ!」
しかし掲げた右手には、剣は現れなかった。来栖が思わず掲げた右手を見る。
「そんな馬鹿な」
来栖が愕然となり呟く。その隙を見逃さずマキシマム・揚が紫電のような速さで瞬く間に間合いを詰める。
そして来栖のがら空きの鳩尾に左足で前蹴りを叩き込む。
来栖が後方へ蹴り飛ばされ石畳を勢いよく転がり狛犬にぶつかりようやく止まる。
来栖の意識がぷっつりと途切れる。
マキシマム・揚は、そのまま踏み込みアリーシアを間合いに捉える。
「やめて。あなたは、女性を襲うような人じゃないでしょ」
アリーシアが妖艶な笑みと共に甘い声がマキシマム・揚の心に忍び寄る。
「悪いな。あんたは、俺の好みじゃない」
マキシマム・揚が構わず右上段回し蹴りを放つ。
蹴りは、アリーシアをすり抜けた。哄笑を上げアリーシアの姿が消えていく。
「逃がしたか」
マキシマム・揚が忌々しそうに舌打ちすると白耀姫の所に戻っていく。
「敵の手がここまで迫っているとなると一刻を争うな」
「そうじゃな。急がねばならぬ」
マキシマム・揚が手を差し出す。
「なんじゃ?」
白耀姫が不審そうにその手を見る。
「中華街に転移する」
「なるほど。わかった」
白耀姫がマキシマム・揚の手を握る。マキシマム・揚は、ゆっくりと息を吐き出し全身の力を抜く。
そしてふらふらと体を揺らした後、踵を石畳に打ちつけた。
音と同時にマキシマム・揚と白耀姫の姿は、霧のように消えた。
どこからか自分を呼ぶ声がする。ゆっくりと来栖が目を開く。
目に飛び込んできたのは、来栖の見覚えがある木の杖を持ち長い白い髭が印象的な老人の顔だった。
来栖に剣を手渡してくれた占い師だった。
「じいさん。久しぶりだな」
どうやら自分は、地面に寝ているらしい。背中に石畳の冷たい感触を感じる。
辺りを見回す。石畳があり神社も遠くに見えるが風景がおかしい。
遠くに見える風景が白い霧のようなものに覆われ何も見えない。
空から見ると恐らく神社一帯だけを切り取り宙に浮いているように見えるだろう。
「じいさん。ここどこだ」
来栖が立ち上がり占い師に尋ねる。
「アストラル界じゃ。お若いの。また忘れ物を届けに来たぞ」
占い師が来栖に飾りつきの鞘に収められた柄に大きなダイアモンドがはまった白銀の剣を差し出す。
来栖が剣を掴む。来栖の手に痺れが走り慌てて手を引っ込める。
剣が来栖を拒んでいるかのようだった。
「なあ。じいさん。この剣を握ろうとすると手に痺れが走るんだが」
占い師が長い髭をしごく。
「ふむ。それは、お主が剣を粗末に扱ったから怒っておるのじゃろう」
「剣が怒る? そんなことがあるのか?」
来栖が信じられないといった表情で首をかしげる。
「ある。この剣は、ただの剣ではない。明確な意思を持ち魔物を倒す剣じゃ。
どれ。お主にもわかりやすく剣の意志を見せようか」
占い師が呪文を唱える。剣が輝き閃光が辺りを照らす。閃光が収まり人影が現れる。
そこには、西洋鎧に身を包み砂金をまぶしたように輝く髪を青いリボンで後ろにまとめた凛々しい顔の小柄な女性が立っていた。
そしてその腰には、飾りつきの鞘に収められた柄に大きなダイアモンドがはまった白銀の剣を差していた。
「我が名は、ハースニール。ダイアモンドの騎士の剣なり」
鋼のように硬く冷ややかな声で来栖に告げた。
そして抜く手も見せず来栖の首に剣の切っ先を突きつける。
「問おう。貴方が私のマスターか」
「・・・そうだ」
来栖が動揺し上ずった声で答える。背中は、冷や汗で冷たい。
「ならばなぜ私を捨てたのか」
「悪かった。反省している」
来栖が素直に頭を下げあやまる。ハースニールがあきれた表情を見せる。
「貴方は、自分のしたことがまだわかってないようだな。確かに私は、貴方と契約した。
だが私を捨てたということは、契約を破棄したと考えざるをえない」
確かにそう思われても仕方ない。来栖が言い返せず沈黙する。
「あまつさえ恋人に化けたアヤカシを見抜けず騙される始末。
これでは、力量不足と言わざるをえない。それでも貴方は、騎士たる資格を持つ者なのか」
ハースニールは、淡々と来栖の非難を続ける。
「たぶん・・・。そうなんだよな。じいさん」
助けを求めるように来栖が占い師の方を見る。
占い師は、好々爺とした笑いを浮かべ何も答えなかった。
「騎士の自覚がないのは、更に問題だ」
ハースニールが冷たく言う。
「・・・俺には、お前の力が必要なんだ」
果たさねばならない誓いがあるし何より三流探偵が生き抜く為には剣の力が必要不可欠だ。
「ならば試させてもらおう。私を使う力量と資格が貴方にあるのどうか」
ハースニールが来栖の首から剣を引き軽やかに後方へ飛ぶと青眼に構える。
「私からこの剣を奪えば貴方の力量と資格を認めよう」
「ちょっと待て。俺は、素手だぞ。武器無しで戦えっていうのか?」
来栖が止めるように両手を広げ慌てて言った。
剣を持った相手に無手で挑むなど殺してくださいと言っているのと同じだ。
「武器がない? 異な事を言う。貴方には、両手に両足という立派な武器がある。
それに目に見える武器だけが力ではない」
ハースニールがさも当然という口調で言った。
言われてみれば確かにそうだ。来栖が思わず納得する。
頷くと来栖が占い師を巻き込まないように石畳の方へ歩く。
間合いを十分に取りハースニールと対峙する。
距離は、約十メートル。剣を振るうには遠すぎる間合いだ。
「異論はないようだな。では始める」
ハースニールがぶんと横薙ぎに剣を振う。だが剣の届く間合いではない。
来栖の探偵の勘が危険を告げる。
「やべっ!」
言うが早いか石畳に身を投げ出す。その上を不可視の刃が風切り音と共に通過する。
「やばかった・・・。あの剣がカマイタチを放てること忘れていた・・・・」
来栖がほっと一息つく。
カマイタチに気がつかなかったら恐らく胴体を真っ二つにされていただろう。
「甘いぞ」
ハースニールが剣を上段から振り下ろす。カマイタチが石畳を切り裂きながら来栖に迫る。
来栖が慌ててカマイタチの直線上から飛びのく。
「縦のカマイタチと横のカマイタチか。厄介な」
自分の武器は、両手と両足、それに当てにならない探偵の勘だけだ。
それを確認し来栖は、神と悪魔を心の中で罵る。
全然、勝てる気がしないぞ。俺の人生っていつも勝ち目のない勝負ばかりだ。
そんなことを考えつつも次々放たれるカマイタチを右に左に転がり或いは、飛びのきながら回避する。
「逃げてばかりでは勝てぬぞ」
小柄な体にどこにそんな体力があるのかと思うほどハースニールが剣を絶え間なく
縦横無尽に振り続ける。
「好きで逃げてるわけじゃねぇよ」
転がり或いは飛び無様な姿でカマイタチから逃げ回りつつ作戦を考える。
まずハースニールに接近しないと勝負にならないこと。
次にカマイタチをよけながらハースニールに接近できるほど運動神経はよくない。
となればおのずと作戦の方針が決まる。
来栖が辺りを見回し目当ての物を見つける
「ま、やってみるか」
来栖が駆け出す。ハースニールの方ではなくまったく見当違いの方へ駆け出す。
「逃がすか!」
ハースニールが剣を横薙ぎに振う。
カマイタチが不気味な音を立て来栖に向かって飛んでくる。
来栖は、身を屈めスライディングしカマイタチをかわしそのまま見つけた目当てのものの後ろに滑り込む。
「ふう。やれやれ。これで一息つける」
来栖が立ち上がり服の埃を手で払う。
「出て来い! 卑怯だぞ!」
ハースニールが声を荒げ叫ぶ。来栖がひょっこりと障害物の後ろから首を出す。
ハースニールは、烈火のごとく怒っている。それも来栖の行為を考えれば当然だろう。
「人の後ろにこそこそ隠れるなどそれでも騎士か!」
来栖が隠れているのは事態を傍観している占い師の背後だ。
来栖をカマイタチで攻撃するためには占い師を必ず巻き込んでしまう。
占い師の背後こそカマイタチから身を守る唯一の安全地帯だ。
「そっちこそカマイタチで遠距離からいやらしくねちねち攻撃してきやがって。
それでも騎士の剣かよ。騎士らしく正面から正々堂々と戦え」
来栖が負けずに言い返す。その言葉に占い師は、面白そうに笑っている。
占い師の背後にいる限りハースニールは、カマイタチで攻撃してこないだろう。
となれば自分から接近してくるに違いない。
「さて、次の手を考えるか」
首をひっこめ占い師の後ろで来栖が再び考え込む。
まずハースニールが接近してきた後、どうなるか。
「斬ってくるんだろうな。なんてたって騎士の剣のだし」
次に自分の武器を確認する。
「殴ると蹴るか。どうやって剣を奪えばいい?」
真っ先に思いついたのは時代劇でよく見る真剣白羽取り。
「できるわけねぇだろ。俺、しがない三流の探偵だぞ」
来栖が頭を抱える。とりあえず殴ってその隙に剣を奪うか。
そうしている間にもハースニールが占い師の背後に回り込み来栖の正面に立つ。
「さあ、これで文句はないな。行くぞ!」
言うが早いかハースニールは、豹を思わせる走りで一気に間合いを詰める。
そして剣を大上段に振り上げる。
気合の声と共に剣が瀑布を思わせる力強さと速さで来栖に向かって振り下ろされる。
慌てて来栖が腰砕けで剣の落下点から逃げる。
剣は、落下点の石畳を砕き巻き上げる。
更に土埃を巻き上げハースニールの体を包む。
来栖は、逃げたおかげで土埃の範囲外にいる。
来栖からは、ハースニールらしき人影が見えている。
だがハースニールは、土埃で視界を遮られている。来栖の姿は、見えないはずだ。
自分は、今始めてこの戦いで有利になったのだ。
「チャンス!」
言うが早いか来栖が土埃に見える人影に向かい右拳を繰り出す。
人影の目前で拳が鈍い音と共に見えない壁にぶつかったかのように止まる。
「しまった! 鞘の能力を忘れてた!」
「恩知らずだな」
ハースニールの持つ剣は、カマイタチを放つ力と魔を退ける力と鉄すら軽々と切断する鋭い切れ味を持ち
更に契約者の願いをかなえるまで戦いを続けさせる呪いをかける。
そして飾りつきの鞘には、持ち主を守り死から遠ざける力を持つ。
来栖も鞘の能力に何度も命を助けられた。
うっかりとそのことを忘れていたのは、確かに恩知らずと言われても何も言い返せない。
土埃が晴れハースニールの姿が現れる。
土埃の中にいたにも関わらず身を包む鎧と青眼に構えている剣は、白銀に輝いている。
「覚悟はいいか?」
「よくない」
言うが早いか来栖は、ハースニールにくるりと背を向け走り出す。
「往生際が悪いぞ」
ハースニールが来栖を追いかける。来栖は、逃げつつ次の作戦を考える。
あの障壁がある限り殴ったり蹴ったりしても無駄。
真剣白羽取りも無理。でも剣を奪わなければならない。さて、どうする?
来栖は、無い知恵を総動員し考える。そして一つの考えが浮かぶ。
「これしか手がなさそうだな・・・」
思いついた策にため息をつき心の中で神と悪魔を思いっきり罵る。
この作戦が失敗すると恐らく死ぬだろう。
来栖が覚悟を決める。
「よし。やるぞ!」
来栖が意気込んだ瞬間、足がもつれ石畳に顔から倒れこむ。
「いててて・・・」
来栖が鼻を抑えつつ立ち上がろうとする。
目の前には、突きつけられた剣の切っ先があった。
「終わりだ」
表情を変えることなくハースニールが冷たく来栖に告げる。
来栖もあきらめたような表情を浮かべる。
切っ先がいったん引かれ次の瞬間、放たれた矢のように来栖の心臓に迫る。
来栖が身をよじり心臓から切っ先を外す。
剣は、心臓を外れ右肩を刺し貫く。剣の先端が貫通し来栖の背中に姿を現していた。
切っ先から鮮血がしたたり石畳を赤く染める。
「・・・やっと捕まえた」
来栖が苦痛に顔を歪ませながら呟く。そして左手で剣の柄を掴む。
「まさか・・・」
ハースニールが何かに気がついたように驚きの表情を見せる。
「ああ、わざと刺された。これしか捕まえる手段が思い浮かばなかったからな」
来栖には、わざと刺されて剣を捕まえるという作戦しか思い浮かばなかった。
振られた剣を止めることは来栖には不可能。
かといって殴ったり蹴ったりしてもハースニールは、隙を見せない。
ならば突かれたなら剣の長さの分で止まるだろうという安直な考えだった。
もし斬られたなら鋭い切れ味により問答無用で両断されてしまうため斬られるわけにはいかなかった。
そのためにわざと転び突きがくる確率を上げた。
なぜなら最初にハースニールが剣を突きつけてきたのが印象に残っていたからだ。
再び剣を突きつけるような状況に身を置けば今度は突いてくるだろうという読みだった。
もし斬られたならば来栖は、成す術も無く死んでいただろう。
「賭けだったんだが何とか上手くいったな」
来栖が苦笑しながら柄を離さないようにしっかりと握る。
「残念ながら勝利条件は、私から剣を奪うことです。
捕まえただけでは勝利条件を満たしていません」
「そうか・・・。参ったな」
来栖が消えそうな声で言った。出血からか青ざめてきている。
「参ったとは?」
ハースニールが不思議そうに首をかしげる。
「予想以上に痛い。それに力が入らなくなってきた。やばい・・・かも」
そう言うと来栖が瞳を閉じる。柄を握っていた左手が柄からずり落ちる。
遠くか誰かがら自分を必死に呼ぶ声が聞こえる。
そう思いながら来栖の意識は、眠るように薄らいでいった。