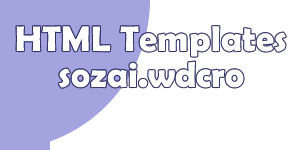Hi’z 5 Errand〜はいず 5 えらんど〜
トーキョーN◎VA-The-Detonation
小説
シーン1 ラインブレイカー
ハルマゲドン、最後の審判、ラグナロク、様々な言葉で呼ばれる災厄の後、
奇跡的な繁栄を遂げ旧東京湾に浮かぶ鎖国した日本の唯一の出島。それが災厄の街トーキョーN◎VAだ。
そしてこの街の治安を守るのが特務警察ブラックハウンドだ。
テロリストや犯罪者を追い詰める誇り高き黄金の猟犬。それがブラックハウンドだ。
鳳翔刻は、このブラックハウンドの警官の一人である。
顔は、精悍だが目は、優しく精悍さを和らげている。
動物で例えるならば狼よりも猟犬のようだ。
長身で無駄な脂肪がついてない一目で鍛え上げられたとわかる体。
捜査であっても制服を着用することは稀でライダースーツが制服の代わりになっている。
二十代後半でありながら未だに階級は、巡査。
原因は、度重なる上司への反抗や命令違反、独断専行のせいである。
ある事件によってブラックハウンドを一度辞め北米に渡りニューヨーク市警で警官をしていたが
ブラックハウンド機動捜査課の千早冴子課長に引き抜かれ五年ぶりにブラックハウンドに
戻ってきたという異例の経歴の持ち主である。
昔から鳳翔を知る人物に言わせると昔から一人で突っ走る奴だったが帰ってきてからは益々磨きがかかって
更に悪知恵までついて上司に噛み付くようになりやがったとのことである。
鳳翔がそうなった理由は、ニューヨーク市警での日々だった。
ニューヨーク市警では、マフィアであるカーライルシンジケートによる警官の買収が横行し
更にFBIやCIAが捜査に横槍を入れてくるというのが日常茶飯事だった。
それにキレた鳳翔は、独断専行や命令違反に命令不服従を繰り返し事件を一人で解決してきた。
キャリアに嫌悪感を抱くようになったのもこの頃からである。
出世とデスクワークとは無縁の日々だが鳳翔は、満足だった。
鳳翔は、出勤して機動捜査課のオフィスに顔を出し同僚達に挨拶しパトロールに行くと告げと即座に駐車場に戻ってきた。
駐車場には猟犬達が使うバイクや車がずらりと並んでいる。
その中でも異彩を放っているのが鳳翔の目の前にあるバイクである。
他のバイクを押しのけるような力強い存在感。
速さだけを追求した刀のように無駄が無い鋭角的なデザイン。
鳳翔の愛車であるムラマサである。
このムラマサを駆り鳳翔は、幾多の犯罪者とチェイスを繰り広げ勝利してきた。
鳳翔の一番の相棒であり体の一部といっても過言ではない。
鳳翔が鍵を回しムラマサのエンジンに火を入れる。
鳳翔が眉を潜める。何度かアクセルを回し耳を澄ましエンジンの排気音を聞く。
そして鍵を回しエンジンの火を落とす。
「おい。誰かいるか」
鳳翔が駐車場に響きわたる声で呼びかける。
その声を聞き工具箱を片手にツナギを着た整備員がやって来る。
「何すか? 鳳翔巡査」
「ちょっと俺のバイクを見てくれないか?」
「分かりました」
整備員がしゃがみ込みムラマサを見ていく。
時折、工具箱から様々な道具を取り出しムラマサを検査していく。
「で、どうだ?」
作業を見守っていた鳳翔が焦れたように整備員に尋ねた。
「鳳翔巡査。オーバーホールしないとまずいっすよ」
「そんなにまずいのか?」
「部品のほとんどが磨耗して限界ですよ。このまま走り続けるとその内、スクラップですね」
整備員がオイルで汚れた手をタオルでぬぐいながら答える。
「エンジンの音がいつもと違ったのもそれが原因か?」
「そうっす。よくわかりましたね。そんなに違いがでるほどの音じゃないはずなんですが」
「毎日乗ってりゃそれくらいすぐわかるさ」
鳳翔が面白くなさそうに言った。ムラマサの状態がそれほど酷いと思ってなかったせいだろう。
「それで部品を取り替えるのにどれぐらいかかる?」
「ウチじゃ無理ですね」
整備員が患者の死を告げる医者のように情け容赦なくきっぱりと告げる。
「てめぇメカニックだろう。何とかしやがれ!」
鳳翔がツナギの胸元を掴み整備員を締め上げる。
爪先立ちになりながら整備員が苦しそうに答える。
「このバイク乗っているのブラックハウンドじゃ鳳翔巡査だけじゃありませんか。
当然、スペアパーツなんてありませんよ」
「既製品で何とかしろ。共通のパーツとかあるだろうが」
「無理っすよ。このマシン、ほとんどがハンドメイドですよ。
既製品なんてタイヤとミラーとライトくらいですよ」
鳳翔が手を離す。整備員が足を地につけると苦しそうに咳き込む。
鳳翔が面白くなさそうに後頭部を掻く。
「参ったな。じゃあ、しばらくムラマサは、使用不能ってことか」
「そうですね。ニ、三日で壊れるってこともないですが無理すると取り返しがつかなくなりますよ。交換部品の当てもありませんし」
「わかった。しばらくここにムラマサは、ここに置いていくから面倒見てくれ」
鳳翔が整備員に頭を下げる。
「わかりました。俺も何とか部品を調達してみます」
「頼む。ところで今からパトロールに行くんだが空きのバイクないか?」
「ちょっと待ってください」
整備員がポケットロンを取り出しデータを呼び出す。
「八番に止まっているグリューヴルムが空いています。コイツを使ってください」
「わかった。データを見せてくれ」
整備員がポケットロンを鳳翔に投げる。そしてグリューヴルムの鍵を取りに奥へ戻っていった。
鳳翔がキーを操作しグリューヴルムのデータを見ていく。
グリューヴルムのデータ上の性能は、全てムラマサより数段下だ。
世界のバイクメーカー和光技研の作ったレース用バイクだけに
直線の速度も旋回時の安定性もバランスよくまとまっていて本当ならば文句無しの合格点の性能だ。
しかし鳳翔の乗っていたムラマサは、速く駆けることだけに特化した暴れ馬のようなマシンだ。
暴れ馬のようなマシンに乗っていた鳳翔から見ればグリューヴルムは、飼い慣らされた馬のようにしか感じられない。
「まあ、こいつも悪いマシンじゃねえし久しぶりに違うマシンに乗るのも悪くない」
鳳翔は、気分を切り替えるように軽く言うとデータを閉じる。
ちょうど整備員が戻ってきた。鳳翔に向かって鍵を投げる。
鳳翔が左手で鍵を受けとり代わりに右手でポケットロンを整備員に投げる。
そうして鳳翔は、八番スポットに止まっているグリューヴルムの所へ向かっていった。
鳳翔がグリューヴルムのアクセルを全開に開き直線を飛ばす。風が渦巻く音が耳に届く。
目前に迫った右コーナー手前でブレーキを握り速度を落とす。
体を右に倒し右コーナーをクリア。
体勢を立て直し再び見えた直線をアクセルを開ける。
静かな住宅街の喧騒を打ち破るように排気音を轟かせグリューヴルムが駆ける。
乗ってみるとやはり物足りなさを痛感させられる。
目に飛び込んでくる風景も耳に入ってくる音もその全てがムラマサのものとは違う。
鳳翔がつまらなそうな表情で機械的にグリューヴルムを操る。
「ん?」
鳳翔が何かに気がついたように前方に目をやる。
その視線の先にあるのは流線型の滑らかなボディ。
真紅を纏った堂々たる姿は、否応も無く人の視線を惹きつける。
それは、Model・512と呼ばれる今では見なくなった形式のスポーツカーだ。
Model・512の流れを組むスポーツカーは、最悪の燃費と最高の速度を誇ると
走り屋の中では有名であり人気も高い。
今は、その最新型であるModel・XXが市場に出回っておりModel・512の
生産は、完全に終了している。交換部品のみが受注で生産されているはずだ。
性能も完全にModel・XXの方が上回っている。
それでも旧型であるModel・512を乗り続けているということはよほど強い思い入れがあるのだろう。
Model・512が後部のハザードを二回点灯させた後、左折の方向ランプを光らせる。
左に止まれという合図だ。Model・512がまず左の路肩により止まる。
鳳翔もModel・512の後ろにグリューヴルムを止める。
Model・512の扉が開き中から長身の男が出てくる。
男の髪は、黒く短く刈ってありその目は、獲物を狙う狼のように鋭く冷たい。
そしてボクサーのように無駄な肉を殺ぎ落としたことによって痩せて見える体に合成皮の
ジャケットを纏っている。
男がゆっくりと鳳翔に近づいてくる。鳳翔がヘルメットを外し男が近づいてくるのを待つ。
「あんた、リンギオの鳳翔だろう」
男が鳳翔のあだ名を口にする。リンギオ、イタリア語で犬の唸り声を表す言葉だ。
ニューヨーク市警時代、鳳翔は、カーライルシンジケートの買収に応じず徹底的にカーライルシンジケートと戦った。
そこからカーライルシンジケートは、鳳翔のことをリンギオと呼ぶようになった。
唸り声を上げ命令を聞かない犬と言う意味を込めての事だろう。
もう一つの由来は、鳳翔の駆るムラマサの排気音が犬の唸り声のように聞えこの音を恐れた
マフィアの下っ端たちがつけたのだと言う。
別に鳳翔自身がそう名乗っているわけではないがせっかくつけてもらったあだ名なので
そのままにしていると言うのが本当のところだ。
「そうだが。あんたは何者だ?」
「俺の名は、ジャンルカ・インザーギ。あだ名は、ラインブレイカー」
「ニューヨーク市警にいたこと噂を聞いた事がある。警察がどんなに厳重な道路封鎖を
張り巡らせても突破し目的地に辿り着き荷物を届ける運び屋がいるってな。
そしてその運び屋についたあだ名がラインブレイカーだってことを」
「知っていてくれて光栄だ。リンギオ。あんたのことは、北米にいた頃に噂で聞いていた。
残念ながら北米では縁が無かったが」
「そいつが何の用だ。お互い会った記念にお茶を飲みましょうって柄じゃないよな」
お互いの視線が絡み合い火花を散らし挑戦的な笑みがお互いの口に浮かぶ。
ジャンルカが言わずとも何がしたいかは、鳳翔には分かる。
だがどうこの男がどういう風に口火を切るのかが楽しみで仕方ない。
ジャンルカが真っ直ぐ鳳翔を見つめる。
「俺と勝負しろ。リンギオ」
そしてそのまま視線と同じように真っ直ぐ用件を切り出した。
「構わないが俺は、仕事中だがいいか?」
鳳翔が自分の状況を説明する。仕事中と言ったのはジャンルカを気遣ってのことだ。
つまり横からいらぬ邪魔が入るかもしれないがいいかという意味だ。
久しぶりに戦いがいがありそうな相手なのだ。
できれば邪魔が入らない条件でとことんまで戦いたいというのが鳳翔の正直な気持ちだ。
「問題ない。今すぐにやろう」
ジャンルカが静かな声で言った。
「ほう?」
面白そうに片方の眉をあげ鳳翔がジャンルカを見る。
「俺も今、仕事中だ。俺の車には、ヘロインが積んである。港の倉庫まで運ぶ途中だ」
それを聞き鳳翔が面白そうに大声で笑う。
「あんた気に入ったぜ。俺が勝ったらそのヘロインは、没収させてもらう。
お前が勝ったら見逃してやる。お互い仕事中ということならこれでいいな」
鳳翔がジャンルカへの好意と勝負への期待が入り混じった熱い声で告げる。
「構わん。賭けるものがあるからこそ熱くなれる」
言葉とはまったく逆の冷めた声でジャンルカが告げる。
「じゃあ、やるか。ゴールは港の一番ゲートだ。いいな」
ジャンルカが無言で頷きModel・512に戻っていく。
鳳翔がグリューヴルムをModel・512の隣に並べる。
Model・512の運転席側の窓が開きジャンルカが顔を出す。
「こいつを投げて地面に落ちたらスタートだ。いいな?」
ジャンルカが手に持った缶コーヒーの空き缶を見せる。
「いいぜ」
鳳翔が頷く。
「リンギオ。一つだけ聞きたいことがある」
「何だ?」
「お前は、マシンの声が聞えるか?」
ジャンルカが真っ直ぐ鳳翔を見据え真摯な口調で言った。
「いいや。マシンの声なんて聞いたことないぜ」
鳳翔が首を振り答える。
「そうか」
ジャンルカは、少し沈んだような声で答えた。
聞き様によっては残念がっているような声だった。
「始めるか」
ジャンルカが天高く空き缶を投げる。
鳳翔が真っ直ぐ空き缶を見つめ地面に落ちる瞬間を待つ。
ジャンルカも両手でハンドルを握り狼のような鋭い目で空き缶を見つめる。
運転手達のはやる気持ちを代弁するかのようにお互いの愛車が低い排気音を唸らせる。
空き缶が地面に落ち軽い音を響かせる。
その瞬間、ジャンルカと鳳翔の二人だけのレースが始まった。
レースの世界は、冷酷だ。
その世界にいるのは、勝者と敗者だけだ。
レースの世界は、残酷だ。
一秒にも満たない刹那の瞬間によって勝者と敗者が分けられる。
レースの世界は、非情だ。
勝者は、全てを肯定され敗者は、全て否定される。
レースの世界は、無常だ。
勝者は、永遠に名を刻まれ敗者は、誰にも覚えられることも無く消えていく。
鳳翔は、ジャンルカに負けた。
それが一秒しか違わなかったのかそれとも大差で負けたのかそんなことに意味はない。
鳳翔は、敗者なのだ。敗者に語る言葉は与えられない。
語るべき言葉を持つのは勝者であるジャンルカだけだ。
勝者のジャンルカは、全てを肯定され敗者の鳳翔は、全てを否定された。
これだけが容赦ない事実にして残酷な現実。
これがレースのそしてカゼと呼ばれるスタイルを持つ者達が住む世界のルールなのだ。
ジャンルカとのレースが終わり鳳翔は、ブラックハウンド基地に戻ってきた。
八番スポットにグリューヴルムを止めて鍵を抜く。
グリューヴルムから降りてヘルメットを脇に抱え歩き出す。
鳳翔の足は、無意識にムラマサの方に向いた。
ムラマサは、相変わらずそこに止まっていた。
他のバイクを押しのけるような力強い存在感。
速さだけを追求した刀のように無駄が無い鋭角的なデザイン
ブラックハウンドであることを示す金と黒の塗られたそのボディが今は、輝きを失っているように見える。
自分は、負けた。ムラマサに乗っていれば勝てたなどと言うつもりは無い。
その言葉は、グリューヴルムに乗って全力で戦った自分を自分で否定する言葉だ。
だから今口に出して言うべき言葉はただ一つ。
「あいつにもう一度、挑戦する。」
レースの世界は、冷酷だ。
その世界にいるのは、勝者と敗者だけだ。
レースの世界は、残酷だ。
一秒にも満たない刹那の瞬間によって勝者と敗者が分けられる。
レースの世界は、非情だ。
勝者は、全てを肯定され敗者は、全て否定される。
レースの世界は、無常だ。
勝者は、永遠に名を刻まれ敗者は、誰にも覚えられることも無く消えていく。
そしてレースの世界は、過酷だ
勝者は、いつまでも勝者ではなく敗者もいつまでも敗者ではない。
敗者は、再び勝者に挑み勝者は、別の勝者に挑む。そして永遠に戦い続ける。
「もう一度だ」
鳳翔が自分に言い聞かせるように力強く言った。ムラマサだけがその言葉を共に聞いていた。
シーン2 Over The Topに進む
奇跡的な繁栄を遂げ旧東京湾に浮かぶ鎖国した日本の唯一の出島。それが災厄の街トーキョーN◎VAだ。
そしてこの街の治安を守るのが特務警察ブラックハウンドだ。
テロリストや犯罪者を追い詰める誇り高き黄金の猟犬。それがブラックハウンドだ。
鳳翔刻は、このブラックハウンドの警官の一人である。
顔は、精悍だが目は、優しく精悍さを和らげている。
動物で例えるならば狼よりも猟犬のようだ。
長身で無駄な脂肪がついてない一目で鍛え上げられたとわかる体。
捜査であっても制服を着用することは稀でライダースーツが制服の代わりになっている。
二十代後半でありながら未だに階級は、巡査。
原因は、度重なる上司への反抗や命令違反、独断専行のせいである。
ある事件によってブラックハウンドを一度辞め北米に渡りニューヨーク市警で警官をしていたが
ブラックハウンド機動捜査課の千早冴子課長に引き抜かれ五年ぶりにブラックハウンドに
戻ってきたという異例の経歴の持ち主である。
昔から鳳翔を知る人物に言わせると昔から一人で突っ走る奴だったが帰ってきてからは益々磨きがかかって
更に悪知恵までついて上司に噛み付くようになりやがったとのことである。
鳳翔がそうなった理由は、ニューヨーク市警での日々だった。
ニューヨーク市警では、マフィアであるカーライルシンジケートによる警官の買収が横行し
更にFBIやCIAが捜査に横槍を入れてくるというのが日常茶飯事だった。
それにキレた鳳翔は、独断専行や命令違反に命令不服従を繰り返し事件を一人で解決してきた。
キャリアに嫌悪感を抱くようになったのもこの頃からである。
出世とデスクワークとは無縁の日々だが鳳翔は、満足だった。
鳳翔は、出勤して機動捜査課のオフィスに顔を出し同僚達に挨拶しパトロールに行くと告げと即座に駐車場に戻ってきた。
駐車場には猟犬達が使うバイクや車がずらりと並んでいる。
その中でも異彩を放っているのが鳳翔の目の前にあるバイクである。
他のバイクを押しのけるような力強い存在感。
速さだけを追求した刀のように無駄が無い鋭角的なデザイン。
鳳翔の愛車であるムラマサである。
このムラマサを駆り鳳翔は、幾多の犯罪者とチェイスを繰り広げ勝利してきた。
鳳翔の一番の相棒であり体の一部といっても過言ではない。
鳳翔が鍵を回しムラマサのエンジンに火を入れる。
鳳翔が眉を潜める。何度かアクセルを回し耳を澄ましエンジンの排気音を聞く。
そして鍵を回しエンジンの火を落とす。
「おい。誰かいるか」
鳳翔が駐車場に響きわたる声で呼びかける。
その声を聞き工具箱を片手にツナギを着た整備員がやって来る。
「何すか? 鳳翔巡査」
「ちょっと俺のバイクを見てくれないか?」
「分かりました」
整備員がしゃがみ込みムラマサを見ていく。
時折、工具箱から様々な道具を取り出しムラマサを検査していく。
「で、どうだ?」
作業を見守っていた鳳翔が焦れたように整備員に尋ねた。
「鳳翔巡査。オーバーホールしないとまずいっすよ」
「そんなにまずいのか?」
「部品のほとんどが磨耗して限界ですよ。このまま走り続けるとその内、スクラップですね」
整備員がオイルで汚れた手をタオルでぬぐいながら答える。
「エンジンの音がいつもと違ったのもそれが原因か?」
「そうっす。よくわかりましたね。そんなに違いがでるほどの音じゃないはずなんですが」
「毎日乗ってりゃそれくらいすぐわかるさ」
鳳翔が面白くなさそうに言った。ムラマサの状態がそれほど酷いと思ってなかったせいだろう。
「それで部品を取り替えるのにどれぐらいかかる?」
「ウチじゃ無理ですね」
整備員が患者の死を告げる医者のように情け容赦なくきっぱりと告げる。
「てめぇメカニックだろう。何とかしやがれ!」
鳳翔がツナギの胸元を掴み整備員を締め上げる。
爪先立ちになりながら整備員が苦しそうに答える。
「このバイク乗っているのブラックハウンドじゃ鳳翔巡査だけじゃありませんか。
当然、スペアパーツなんてありませんよ」
「既製品で何とかしろ。共通のパーツとかあるだろうが」
「無理っすよ。このマシン、ほとんどがハンドメイドですよ。
既製品なんてタイヤとミラーとライトくらいですよ」
鳳翔が手を離す。整備員が足を地につけると苦しそうに咳き込む。
鳳翔が面白くなさそうに後頭部を掻く。
「参ったな。じゃあ、しばらくムラマサは、使用不能ってことか」
「そうですね。ニ、三日で壊れるってこともないですが無理すると取り返しがつかなくなりますよ。交換部品の当てもありませんし」
「わかった。しばらくここにムラマサは、ここに置いていくから面倒見てくれ」
鳳翔が整備員に頭を下げる。
「わかりました。俺も何とか部品を調達してみます」
「頼む。ところで今からパトロールに行くんだが空きのバイクないか?」
「ちょっと待ってください」
整備員がポケットロンを取り出しデータを呼び出す。
「八番に止まっているグリューヴルムが空いています。コイツを使ってください」
「わかった。データを見せてくれ」
整備員がポケットロンを鳳翔に投げる。そしてグリューヴルムの鍵を取りに奥へ戻っていった。
鳳翔がキーを操作しグリューヴルムのデータを見ていく。
グリューヴルムのデータ上の性能は、全てムラマサより数段下だ。
世界のバイクメーカー和光技研の作ったレース用バイクだけに
直線の速度も旋回時の安定性もバランスよくまとまっていて本当ならば文句無しの合格点の性能だ。
しかし鳳翔の乗っていたムラマサは、速く駆けることだけに特化した暴れ馬のようなマシンだ。
暴れ馬のようなマシンに乗っていた鳳翔から見ればグリューヴルムは、飼い慣らされた馬のようにしか感じられない。
「まあ、こいつも悪いマシンじゃねえし久しぶりに違うマシンに乗るのも悪くない」
鳳翔は、気分を切り替えるように軽く言うとデータを閉じる。
ちょうど整備員が戻ってきた。鳳翔に向かって鍵を投げる。
鳳翔が左手で鍵を受けとり代わりに右手でポケットロンを整備員に投げる。
そうして鳳翔は、八番スポットに止まっているグリューヴルムの所へ向かっていった。
鳳翔がグリューヴルムのアクセルを全開に開き直線を飛ばす。風が渦巻く音が耳に届く。
目前に迫った右コーナー手前でブレーキを握り速度を落とす。
体を右に倒し右コーナーをクリア。
体勢を立て直し再び見えた直線をアクセルを開ける。
静かな住宅街の喧騒を打ち破るように排気音を轟かせグリューヴルムが駆ける。
乗ってみるとやはり物足りなさを痛感させられる。
目に飛び込んでくる風景も耳に入ってくる音もその全てがムラマサのものとは違う。
鳳翔がつまらなそうな表情で機械的にグリューヴルムを操る。
「ん?」
鳳翔が何かに気がついたように前方に目をやる。
その視線の先にあるのは流線型の滑らかなボディ。
真紅を纏った堂々たる姿は、否応も無く人の視線を惹きつける。
それは、Model・512と呼ばれる今では見なくなった形式のスポーツカーだ。
Model・512の流れを組むスポーツカーは、最悪の燃費と最高の速度を誇ると
走り屋の中では有名であり人気も高い。
今は、その最新型であるModel・XXが市場に出回っておりModel・512の
生産は、完全に終了している。交換部品のみが受注で生産されているはずだ。
性能も完全にModel・XXの方が上回っている。
それでも旧型であるModel・512を乗り続けているということはよほど強い思い入れがあるのだろう。
Model・512が後部のハザードを二回点灯させた後、左折の方向ランプを光らせる。
左に止まれという合図だ。Model・512がまず左の路肩により止まる。
鳳翔もModel・512の後ろにグリューヴルムを止める。
Model・512の扉が開き中から長身の男が出てくる。
男の髪は、黒く短く刈ってありその目は、獲物を狙う狼のように鋭く冷たい。
そしてボクサーのように無駄な肉を殺ぎ落としたことによって痩せて見える体に合成皮の
ジャケットを纏っている。
男がゆっくりと鳳翔に近づいてくる。鳳翔がヘルメットを外し男が近づいてくるのを待つ。
「あんた、リンギオの鳳翔だろう」
男が鳳翔のあだ名を口にする。リンギオ、イタリア語で犬の唸り声を表す言葉だ。
ニューヨーク市警時代、鳳翔は、カーライルシンジケートの買収に応じず徹底的にカーライルシンジケートと戦った。
そこからカーライルシンジケートは、鳳翔のことをリンギオと呼ぶようになった。
唸り声を上げ命令を聞かない犬と言う意味を込めての事だろう。
もう一つの由来は、鳳翔の駆るムラマサの排気音が犬の唸り声のように聞えこの音を恐れた
マフィアの下っ端たちがつけたのだと言う。
別に鳳翔自身がそう名乗っているわけではないがせっかくつけてもらったあだ名なので
そのままにしていると言うのが本当のところだ。
「そうだが。あんたは何者だ?」
「俺の名は、ジャンルカ・インザーギ。あだ名は、ラインブレイカー」
「ニューヨーク市警にいたこと噂を聞いた事がある。警察がどんなに厳重な道路封鎖を
張り巡らせても突破し目的地に辿り着き荷物を届ける運び屋がいるってな。
そしてその運び屋についたあだ名がラインブレイカーだってことを」
「知っていてくれて光栄だ。リンギオ。あんたのことは、北米にいた頃に噂で聞いていた。
残念ながら北米では縁が無かったが」
「そいつが何の用だ。お互い会った記念にお茶を飲みましょうって柄じゃないよな」
お互いの視線が絡み合い火花を散らし挑戦的な笑みがお互いの口に浮かぶ。
ジャンルカが言わずとも何がしたいかは、鳳翔には分かる。
だがどうこの男がどういう風に口火を切るのかが楽しみで仕方ない。
ジャンルカが真っ直ぐ鳳翔を見つめる。
「俺と勝負しろ。リンギオ」
そしてそのまま視線と同じように真っ直ぐ用件を切り出した。
「構わないが俺は、仕事中だがいいか?」
鳳翔が自分の状況を説明する。仕事中と言ったのはジャンルカを気遣ってのことだ。
つまり横からいらぬ邪魔が入るかもしれないがいいかという意味だ。
久しぶりに戦いがいがありそうな相手なのだ。
できれば邪魔が入らない条件でとことんまで戦いたいというのが鳳翔の正直な気持ちだ。
「問題ない。今すぐにやろう」
ジャンルカが静かな声で言った。
「ほう?」
面白そうに片方の眉をあげ鳳翔がジャンルカを見る。
「俺も今、仕事中だ。俺の車には、ヘロインが積んである。港の倉庫まで運ぶ途中だ」
それを聞き鳳翔が面白そうに大声で笑う。
「あんた気に入ったぜ。俺が勝ったらそのヘロインは、没収させてもらう。
お前が勝ったら見逃してやる。お互い仕事中ということならこれでいいな」
鳳翔がジャンルカへの好意と勝負への期待が入り混じった熱い声で告げる。
「構わん。賭けるものがあるからこそ熱くなれる」
言葉とはまったく逆の冷めた声でジャンルカが告げる。
「じゃあ、やるか。ゴールは港の一番ゲートだ。いいな」
ジャンルカが無言で頷きModel・512に戻っていく。
鳳翔がグリューヴルムをModel・512の隣に並べる。
Model・512の運転席側の窓が開きジャンルカが顔を出す。
「こいつを投げて地面に落ちたらスタートだ。いいな?」
ジャンルカが手に持った缶コーヒーの空き缶を見せる。
「いいぜ」
鳳翔が頷く。
「リンギオ。一つだけ聞きたいことがある」
「何だ?」
「お前は、マシンの声が聞えるか?」
ジャンルカが真っ直ぐ鳳翔を見据え真摯な口調で言った。
「いいや。マシンの声なんて聞いたことないぜ」
鳳翔が首を振り答える。
「そうか」
ジャンルカは、少し沈んだような声で答えた。
聞き様によっては残念がっているような声だった。
「始めるか」
ジャンルカが天高く空き缶を投げる。
鳳翔が真っ直ぐ空き缶を見つめ地面に落ちる瞬間を待つ。
ジャンルカも両手でハンドルを握り狼のような鋭い目で空き缶を見つめる。
運転手達のはやる気持ちを代弁するかのようにお互いの愛車が低い排気音を唸らせる。
空き缶が地面に落ち軽い音を響かせる。
その瞬間、ジャンルカと鳳翔の二人だけのレースが始まった。
レースの世界は、冷酷だ。
その世界にいるのは、勝者と敗者だけだ。
レースの世界は、残酷だ。
一秒にも満たない刹那の瞬間によって勝者と敗者が分けられる。
レースの世界は、非情だ。
勝者は、全てを肯定され敗者は、全て否定される。
レースの世界は、無常だ。
勝者は、永遠に名を刻まれ敗者は、誰にも覚えられることも無く消えていく。
鳳翔は、ジャンルカに負けた。
それが一秒しか違わなかったのかそれとも大差で負けたのかそんなことに意味はない。
鳳翔は、敗者なのだ。敗者に語る言葉は与えられない。
語るべき言葉を持つのは勝者であるジャンルカだけだ。
勝者のジャンルカは、全てを肯定され敗者の鳳翔は、全てを否定された。
これだけが容赦ない事実にして残酷な現実。
これがレースのそしてカゼと呼ばれるスタイルを持つ者達が住む世界のルールなのだ。
ジャンルカとのレースが終わり鳳翔は、ブラックハウンド基地に戻ってきた。
八番スポットにグリューヴルムを止めて鍵を抜く。
グリューヴルムから降りてヘルメットを脇に抱え歩き出す。
鳳翔の足は、無意識にムラマサの方に向いた。
ムラマサは、相変わらずそこに止まっていた。
他のバイクを押しのけるような力強い存在感。
速さだけを追求した刀のように無駄が無い鋭角的なデザイン
ブラックハウンドであることを示す金と黒の塗られたそのボディが今は、輝きを失っているように見える。
自分は、負けた。ムラマサに乗っていれば勝てたなどと言うつもりは無い。
その言葉は、グリューヴルムに乗って全力で戦った自分を自分で否定する言葉だ。
だから今口に出して言うべき言葉はただ一つ。
「あいつにもう一度、挑戦する。」
レースの世界は、冷酷だ。
その世界にいるのは、勝者と敗者だけだ。
レースの世界は、残酷だ。
一秒にも満たない刹那の瞬間によって勝者と敗者が分けられる。
レースの世界は、非情だ。
勝者は、全てを肯定され敗者は、全て否定される。
レースの世界は、無常だ。
勝者は、永遠に名を刻まれ敗者は、誰にも覚えられることも無く消えていく。
そしてレースの世界は、過酷だ
勝者は、いつまでも勝者ではなく敗者もいつまでも敗者ではない。
敗者は、再び勝者に挑み勝者は、別の勝者に挑む。そして永遠に戦い続ける。
「もう一度だ」
鳳翔が自分に言い聞かせるように力強く言った。ムラマサだけがその言葉を共に聞いていた。
シーン2 Over The Topに進む