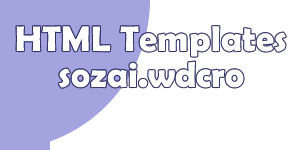Hi’z 5 Errand〜はいず 5 えらんど〜
トーキョーN◎VA-The-Detonation
小説
シーン2 Over The Top
コンテナをその背に載せたトラックがブラックハウンド基地の駐車場に入ってくる。
トランスポーターと呼ばれるレーシングカーやレーシングバイクを収納する専用のトラックだ。
整備部品や工具などのレースに必要な部品を一気に大量輸送する。
車の出し入れには、専用のリフトを使い車には一切負担をかけない。
レースで各地を転戦するレースチームの移動基地として使われる車だ。
コンテナには、和光技研の社名とマークと共に狼のマークが書いてある。
和光のバイクレースチーム、チームWA―K◎のマークだ。
鳳翔が手を上げトランスポーターを誘導する。
トランスポーターが止まり助手席から年配の小柄な女性が降りてくる。
眼鏡をかけた瞳の奥に理性的な光を宿している。くたびれたツナギが良く似合っている。
「お袋。久しぶり」
鳳翔が駆け寄り手を上げ挨拶する。年配の女性は、鳳翔の母、鳳翔静だ。
和光のレースチームのメカニックから二輪開発チームの主任になった叩き上げの技術者だ。
「それで噂のバイクは何処?」
鳳翔のことなど眼中にないようだ。そっけなく静が言った。
「こっちだ」
鳳翔が静をムラマサのところへ案内する。静がしゃがみ込みムラマサに手を触れる。
そして各所を探るように手を触れ見ていく。静がため息をつき感嘆の声を上げる。
「正に走る芸術品ね。全てのパーツが速く走るためだけに作られ極限まで磨き上げられ
機能を追及している。そしてどれも紙一重のバランスで精密にすり合わされ構成されている」
静が立ち上がり鳳翔に向き合う。
「それで?」
「こいつを直して欲しい。ただ直すんじゃなくて整備しやすいように部品を作り直してくれるとありがたい。
性能は落とさずそのままで頼む」
静が難しい顔で腕を組む。
「やっぱり無理か?」
鳳翔が煙草を取り出し火をつけ吸い始める。
「わがままな注文ね。何も無い所からマシンを設計するより難しい。
再設計するのではなく既に完璧に完成された設計を性能を落とすことなく変更する」
鳳翔が無言で静の言葉を聞く。自分がいかに無茶な注文をしているのかが思い知らされる。
「でもねレーサーの無茶に答えるのが超一流のメカニックの仕事よ。
任せなさい。一週間で新品同様にしてあげる」
静が微笑み挑戦的な光を瞳の奥に宿す。
レーサーとメカニックという違いはあるがマシンを通してゴールを目指す挑戦者であることに違いはない。
「で、見返りは何?」
静がメカニックの顔から二輪開発チームの主任の顔になり尋ねる。
「見返りって。息子に見返りを要求するのかよ」
鳳翔があきれたように咥えた煙草を上に向ける。
「私は、ただのメカニックじゃない。今は、二輪開発チームの主任なの。
企業の一部門を担うということはそれなりの結果を出さないといけない。
確かにこのバイクを直すというのは技術者としてとても興味を引かれるけどそのためには、
開発チームを動かさないといけない。私一人じゃ性能を落とさずに整備性を良くする
なんて不可能よ。となると開発チームを動かしただけの結果を上に出さないといけない。
やる以上は、結果を求められる。この点は、レーサーと一緒よ」
「金ならないぞ。ムラマサは、やらん」
鳳翔が吸殻を投げ捨て足で踏みながら答える。
「しょうがない子ね」
母親の顔になりながら静があきれたように呟く。
「このムラマサを研究対象としてこちらの要請があったら貸してくれればいいわ。
ムラマサを研究して使われている技術を次に開発するバイクに応用すれば上も文句も言わないし誰も損しない。これでどう?」
「その話、乗った!」
「じゃあ、契約成立ね。契約中は、メンテナンスはこちらで一切受け持つわ。
交換部品もこちらが製作する。あとは走った後、ちょっとした性能の違いや違和感に
気がついたら言って頂戴。その意見を取り込んで後の開発に生かすから」
静が大まかな契約内容を指折りで数えながら鳳翔に告げる。
「それでいい」
鳳翔が大きく頷く。
「それならムラマサをトランスポーターに乗せなさい。会社に運ぶから」
鳳翔がムラマサを引きリフトを使用しコンテナに積み込む。
静が助手席に乗り込む。そして窓を開け鳳翔に話しかける。
「それじゃ預かっていくわ。一週間後、またここに持ってくるから」
「お袋。親父は今、何処にいるんだ?」
鳳翔がトランスポーターの排気音に負けない声で言った。
「あの人ならB◎―S◎サーキットで遊んでいるわ。会いに行くなら早く行きなさい」
静が運転手に発進するように促す。静が鳳翔にじゃあと手を振る。
鳳翔も手を振る。トランスポーターが見えなくなると八番スポットに向かった。
B◎―S◎サーキット。木更タタラ街にあるチームWA―K◎のホームサーキットだ。
サーキットを走っているのは、一台のバイク。
見る者を魅了するような見事な走りで疾風の如くサーキットを駆け抜ける。
鳳翔は、その走りを見るだけで乗っているのが誰だか分かった。
鳳翔巌。鳳翔の父だ。超一流バイクレーサーとして一時代を築いた男だ。
優勝回数こそ少ないものの速さを追求だけでなく人を魅了することをも追求した
その走りは、今もファンの中で語り継がれている。
記録よりも人々の記憶に残っている稀有なバイクレーサーだ。
それは、速さだけを追求しなければならないレーサーでありながら
人々を魅了する走りをも追及した異端児だからなのかもしれない。
現在は、現役を引退し開発チームのテストドライバーとしてサーキットを走っている。
ピットに巌のバイクが入っていく。鳳翔もピットに向かう。
「親父!」
鳳翔が巌を大声で呼ぶ。
ピットのなかは、指示を出す声やバイクを整備する音で喧騒を響かせている。
「おう。刻か」
巌は、視線を下にしデータが表示されているディスプレイを見ていたが声に気がつくと
鳳翔の顔へ視線を上げた。
ヘルメットは傍らに置いてあり上半身だけライダースーツを脱いで扇風機の前で涼んでいる。
その顔と体は、彫刻された岩のように逞しい。
「珍しいな。何の用だ?」
「一緒に走りにきた」
手短に鳳翔が用件を告げる。巌が面白そうに鳳翔を見つめる。
「いいだろう。今、ちょうど八耐用エンジンの耐久テストの途中だったんだ。
お前、一緒に走れ。手間が省けるし比較データも取れる」
八耐とは、B◎―S◎サーキットで毎年行われるバイクの八時間耐久レースの事だ。
巌は、脱いでいた上半身のライダースーツを着るとヘルメットを脇に抱え自分のマシンに
向かう。
「こいつをスペアマシンに乗っけるから準備してくれ」
巌が鳳翔を指差しメカニックに指示を出していく。
鳳翔もスペアマシンに乗りB◎―S◎サーキットのスタートラインに向かう。
巌は、既にスタートラインで待っている。
「じゃ、行くか。最初は軽く一時間くらいから始めるか」
「おう」
スタートシグナルが赤から青に変わる。鳳翔と巌が同時にスタートを切った。
甲高い排気音がサーキットを支配した。
鳳翔の熱くなった体に水風呂の冷たさが染みていく。
バイクという乗り物の性質上、レーサーには様々な負担がかかる。
特に熱さは、レーサーを襲い続ける最大の敵だ。
コースのアスファルトは、太陽光を反射しその照り返しが容赦ない熱さとなってレーサーを襲う。
更にマシンのエンジンは、周回を重ねるごとに熱を持ち直にレーサーの体を焼く。
そのためレーサーの体温が四十度近くになることも珍しくない
ピットには、レーサーの体を冷やすため扇風機や水風呂が完備されている。
巌も隣で水風呂に漬かっている。上機嫌に下手な演歌まで口ずさんでいる
レースは、圧倒的に巌の方が速かった。
現役を退いたとはいえその腕は、まだまだ錆びついていなかった。
巌は、鳳翔が超えられない一線を易々と超えていく。
それが速さの差だ。鳳翔は、そう思う。
「なあ、親父。俺のテクまだまだ甘いか?」
「いや。今のお前は、俺と同じくらいのテクがある。
連絡先も告げすにN◎VAから出て行って五年間、何処で何やってるか心配したがいい走りをするようになった」
鳳翔が勢いよく立ち上がる。
「じゃあ、何であんな差がつくんだよっ」
「そりゃ、目指す所が違うからな。勝てなくて当然だ」
巌が謎かけのように鳳翔に告げる。
「何だそりゃ? 目指すところってゴールじゃないのかよ?」
鳳翔が再び水風呂に身を浸す。
「お前は、ストリートばかりで走ってたからな。わからんだろうな」
巌が残念そうに呟く。
鳳翔は、あまりサーキットでのレース経験が無い。
十代の頃、偉大な父に反発し主戦場はサーキットではなくストリートだった。
「悪いかよっ! 俺は、自由に走りたかったんだ!」
鳳翔が声を荒げる。
「そもそもそれが違うんだ、刻。お前、どうしてサーキットが自由じゃないって考えるんだ?」
「だって親父。コースが決まっているじゃないか」
鳳翔が指で空中にB◎―S◎サーキットのコース図を描く。
焦れたったそうに巌が後頭部を掻く。
「だからそれが違うんだってーの。
お前、一番速くゴールに向かう方法を考えたことがあるか?」
「コースを一番スピードが乗るライン取りで走ればいいだけだろ」
「違う」
巌があっさりと否定する。
「じゃ、答えは何だよ」
鳳翔が口を尖らせ言った。
「コースに関係なくゴールに誰よりも速く着けばいいんだ」
それが真実という風に巌がきっぱりと言い切る。
鳳翔があきれたように口を開ける。
「例えばずっとコースの内側を走りつづけて一番速くゴールに着くならそうすべきだ。
タイヤバリアに沿って走るのが一番速いならそうすべきだ。
分かるか? 刻。コースなんて決められているようで決められてねぇんだ。
ゴールも同じく決められているようで決められてねぇんだ。
決められているのは、スタートラインだけだ。走り出すのだっていつだっていいんだ。
決めるのは、自分だ。分かったか?」
巌が真面目な顔で熱っぽく語る。
鳳翔が首を捻る。分かるような気もするし分からないような気もする。
巌が熱くなった頭を冷やすように頭から水風呂に潜る。そしてしばらくして頭を上げた。
「分からんようならしばらく一緒に走るか。言葉で分からないなら走りで教えてやる」
鳳翔は、巌の言葉に静かに頷いた。
ジャンルカに敗れてから一週間経った。
鳳翔は、ブラックハウンドの駐車場でトランスポーターが来るのを今か今かと待ち構えている。
足元には、吸殻が何本も落ちている。
新たに煙草を咥え火をつける。すると遠くより排気音が聞えてきた。
トランスポーターの排気音だ。ゆっくりとトランスポーターが駐車場に入ってくる。
コンテナが開きリフトで静と一緒にムラマサが降りてくる。
「お待たせ。刻。完璧に仕上げたわ」
鳳翔が吸い始めた煙草を捨てムラマサに駆け寄る。
静の手から鍵を受け取りムラマサのエンジンに火を入れる。
犬の唸り声のような独特の排気音。何の違和感も感じない澄み切った音だ。
「お袋。ありがとう」
そのままひらりと鳳翔がムラマサに飛び乗る。
「さっさと行きなさい。戦いたい奴がいるんでしょう?
慣らしも終わってちゃんと当たりは出してあるからすぐ戦えるわよ」
静がムラマサの排気音に負けない声で鳳翔に告げる。鳳翔が驚いた表情で静を見る。
静や巌にはジャンルカに負けたことを告げてないのだ。
「これでも一応、あんたの母親よ。それにマシンを見れば何があったかわかる。
父さんもあんたの走りを見て何があったかわかったらしいわ。
勝ったら家に来いって。シャンパン用意しておくから必ず勝てって言ってたわ」
静が微笑み励ますように手を振る。鳳翔が困ったように笑い肩をすくめる。
「これじゃ負けられねぇな。レース前に重い荷物背負わせるなよ」
「そういう重さを背負って走るのが本当のレースよ。今まで縁が無かったのが残念ね」
そうかもしれない。鳳翔が頭の中でそう思う。だが走り出せばそんな事もすぐ忘れるだろう。
アクセルを吹かしムラマサを発進させた。
鳳翔が住宅街の路肩にムラマサを止める。
最初にジャンルカと会った場所だ。今日、ここで再び会えるとは限らない。
だが鳳翔には確信がある。ここにいればジャンルカに再び会えると。
ムラマサに寄りかかり逸る気持ちを抑えるため煙草を取り出し吸い始める。
煙草の長さが半分になった頃、待ち合わせの相手が現れた。
流線型の滑らかなボディに否応無く人の視線を惹きつける真紅を纏った堂々たる姿。
あちらも鳳翔に気がついたようだ。ムラマサの後ろにModel・512が止まる。
運転席の扉が開きジャンルカが降りてくる。
「久しぶりだな」
鳳翔がジャンルカに向かって片手を上げる。
「ああ」
ジャンルカが頷く。その目は、吸いつけられるようにムラマサを見ている。
「いいマシンだ」
ジャンルカが視線を鳳翔に向け言った。
「ああ。俺の相棒だ」
鳳翔がムラマサのボディを撫でる。
しばらくの沈黙の後、鳳翔が真っ直ぐジャンルカを見据える。
「仕事中か?」
「いいや」
ジャンルカが首を振る。
「勝負しないか? 俺も今、休みだ」
「いいだろう。コースは、この前と一緒でいいか?」
鳳翔が頷きそれを見たジャンルカがModel・512に戻っていく。
ジャンルカがふと足を止め鳳翔の方を振り返る。
「そのマシンの声を聞いたことは?」
「いや、無い」
「そうか」
ジャンルカが再び歩を進める。
その背に鳳翔が言葉を投げかける。
「ラインブレイカー。あんた、風の声を聞いたことはあるか?」
ジャンルカが振り返らず歩を止める。
「いや、無い」
「そうだろうな」
鳳翔がその言葉に頷く。
ジャンルカがModel・512に乗り込みムラマサの隣にやって来る。
「スタート方法も前回と一緒でいいな」
ジャンルカが缶コーヒーの空き缶を見せる。
鳳翔が頷く。空き缶が天高く放り投げられた。
Model・512が力強い走りで駆ける。
ムラマサは、切れ味鋭い走りで駆ける。
二台は、絡み合い熾烈に争う。
鳳翔の顔にもジャンルカの顔にも満足そうな笑みが浮かんでいる。
それも走っている間だけだ、ゴールに辿り着けばどちらかの笑みが消える。
レースの世界は、冷酷だ。
その世界にいるのは、勝者と敗者だけだ。
レースの世界は、残酷だ。
一秒にも満たない刹那の瞬間によって勝者と敗者が分けられる。
レースの世界は、非情だ。
勝者は、全てを肯定され敗者は、全て否定される。
レースの世界は、無常だ。
勝者は、永遠に名を刻まれ敗者は、誰にも覚えられることも無く消えていく。
レースの世界は、過酷だ
勝者は、いつまでも勝者ではなく敗者もいつまでも敗者ではない。
敗者は、再び勝者に挑み勝者は、別の勝者に挑む。そして永遠に戦い続ける。
確かにそうかも知れない。
だが誰がそうだと決めたのだろう。
ある男は、言った。
コースなんて決められているようで決められていない。
ゴールも決められているようで決められていない。
決められているのは、スタートラインだけだ。
走り出すのだっていつだっていいんだ。
決めるのは、自分だ。
そう、決めるのは自分なのだ。
コースもゴールもルールもスピードも全て自分が決める。
ゴールは、目前。
Model・512がムラマサの前にいる。
追い抜くスペースは左右どちらにもない。
Model・512のボディがスペースを塞いでいる。
前に出られ追い抜くスペースがないと言う事はもう負けだ。
自分がそう決めるなら負けだ。
「諦めるか!」
鳳翔が叫びゴールを見据える。そう、ゴールこそ目指す場所だ。
天啓のように鳳翔の頭に声が響く。
目指すところは、違う。ゴールではない。その先だ。
鳳翔が見据えていたゴールから目を離す。
そして風景を楽しむように辺りを見回す。
「そうか。そういうことか」
鳳翔がようやく何かに気がついたように呟く。
コースなんて決められているようで決められていない。
ゴールも決められているようで決められていない。
そう、全て自由に自分で決める。
そしてゴールの先を目指し永遠に走らなければならないのだ。
鳳翔がアクセルを全開に開けModel・512に接近する。
そしてテールトゥノーズの体勢に持ち込む。
そのままアクセルは、緩めない。
「風ぇ!」
鳳翔の声に答えるように鳳翔の体の周囲を風が渦巻く。
風がムラマサを空へと導く。
鳳翔の目の前に広がるのは、誰もいない無人の道。
耳に入ってくるのは、ムラマサが風を切る鋭い音。
これが鳳翔の選んだ道。選んだ光景。選んだ音。
見たかった光景。そして聞きたかった音。そして駆け抜けたかった自分だけの道。
この一瞬だけその全てを手に入れる。
夢のような一瞬が過ぎムラマサがModel・512の前に出る。
そのままムラマサがゴールを駆け抜ける。
鳳翔がムラマサを止めヘルメットを外し天を仰ぐ。
ジャンルカもムラマサの横にModel・512を止め運転席から降りてくる。
「やられたな。」
相変わらず表情を変えずにジャンルカが淡々と告げる。
「これで一勝一敗だ。次、会う時が楽しみだな」
鳳翔がそう言うと手を差し出す。ジャンルカがその手を力強く握る。
そしてModel・512の運転席に戻っていく。
振り返らずにジャンルカが静かな声で言った。
「See you again、Over The Top」
そしてそのままModel・512を発進させジャンルカが立ち去る。
「また会おう。頂上を超えたその先で、か」
ジャンルカも鳳翔が見たあの一瞬を見たことがあるのかも知れない。
そう、レースはまだ終わらない。次がある。
そして頂点を超えたその先で新たな挑戦者達が待っている
トランスポーターと呼ばれるレーシングカーやレーシングバイクを収納する専用のトラックだ。
整備部品や工具などのレースに必要な部品を一気に大量輸送する。
車の出し入れには、専用のリフトを使い車には一切負担をかけない。
レースで各地を転戦するレースチームの移動基地として使われる車だ。
コンテナには、和光技研の社名とマークと共に狼のマークが書いてある。
和光のバイクレースチーム、チームWA―K◎のマークだ。
鳳翔が手を上げトランスポーターを誘導する。
トランスポーターが止まり助手席から年配の小柄な女性が降りてくる。
眼鏡をかけた瞳の奥に理性的な光を宿している。くたびれたツナギが良く似合っている。
「お袋。久しぶり」
鳳翔が駆け寄り手を上げ挨拶する。年配の女性は、鳳翔の母、鳳翔静だ。
和光のレースチームのメカニックから二輪開発チームの主任になった叩き上げの技術者だ。
「それで噂のバイクは何処?」
鳳翔のことなど眼中にないようだ。そっけなく静が言った。
「こっちだ」
鳳翔が静をムラマサのところへ案内する。静がしゃがみ込みムラマサに手を触れる。
そして各所を探るように手を触れ見ていく。静がため息をつき感嘆の声を上げる。
「正に走る芸術品ね。全てのパーツが速く走るためだけに作られ極限まで磨き上げられ
機能を追及している。そしてどれも紙一重のバランスで精密にすり合わされ構成されている」
静が立ち上がり鳳翔に向き合う。
「それで?」
「こいつを直して欲しい。ただ直すんじゃなくて整備しやすいように部品を作り直してくれるとありがたい。
性能は落とさずそのままで頼む」
静が難しい顔で腕を組む。
「やっぱり無理か?」
鳳翔が煙草を取り出し火をつけ吸い始める。
「わがままな注文ね。何も無い所からマシンを設計するより難しい。
再設計するのではなく既に完璧に完成された設計を性能を落とすことなく変更する」
鳳翔が無言で静の言葉を聞く。自分がいかに無茶な注文をしているのかが思い知らされる。
「でもねレーサーの無茶に答えるのが超一流のメカニックの仕事よ。
任せなさい。一週間で新品同様にしてあげる」
静が微笑み挑戦的な光を瞳の奥に宿す。
レーサーとメカニックという違いはあるがマシンを通してゴールを目指す挑戦者であることに違いはない。
「で、見返りは何?」
静がメカニックの顔から二輪開発チームの主任の顔になり尋ねる。
「見返りって。息子に見返りを要求するのかよ」
鳳翔があきれたように咥えた煙草を上に向ける。
「私は、ただのメカニックじゃない。今は、二輪開発チームの主任なの。
企業の一部門を担うということはそれなりの結果を出さないといけない。
確かにこのバイクを直すというのは技術者としてとても興味を引かれるけどそのためには、
開発チームを動かさないといけない。私一人じゃ性能を落とさずに整備性を良くする
なんて不可能よ。となると開発チームを動かしただけの結果を上に出さないといけない。
やる以上は、結果を求められる。この点は、レーサーと一緒よ」
「金ならないぞ。ムラマサは、やらん」
鳳翔が吸殻を投げ捨て足で踏みながら答える。
「しょうがない子ね」
母親の顔になりながら静があきれたように呟く。
「このムラマサを研究対象としてこちらの要請があったら貸してくれればいいわ。
ムラマサを研究して使われている技術を次に開発するバイクに応用すれば上も文句も言わないし誰も損しない。これでどう?」
「その話、乗った!」
「じゃあ、契約成立ね。契約中は、メンテナンスはこちらで一切受け持つわ。
交換部品もこちらが製作する。あとは走った後、ちょっとした性能の違いや違和感に
気がついたら言って頂戴。その意見を取り込んで後の開発に生かすから」
静が大まかな契約内容を指折りで数えながら鳳翔に告げる。
「それでいい」
鳳翔が大きく頷く。
「それならムラマサをトランスポーターに乗せなさい。会社に運ぶから」
鳳翔がムラマサを引きリフトを使用しコンテナに積み込む。
静が助手席に乗り込む。そして窓を開け鳳翔に話しかける。
「それじゃ預かっていくわ。一週間後、またここに持ってくるから」
「お袋。親父は今、何処にいるんだ?」
鳳翔がトランスポーターの排気音に負けない声で言った。
「あの人ならB◎―S◎サーキットで遊んでいるわ。会いに行くなら早く行きなさい」
静が運転手に発進するように促す。静が鳳翔にじゃあと手を振る。
鳳翔も手を振る。トランスポーターが見えなくなると八番スポットに向かった。
B◎―S◎サーキット。木更タタラ街にあるチームWA―K◎のホームサーキットだ。
サーキットを走っているのは、一台のバイク。
見る者を魅了するような見事な走りで疾風の如くサーキットを駆け抜ける。
鳳翔は、その走りを見るだけで乗っているのが誰だか分かった。
鳳翔巌。鳳翔の父だ。超一流バイクレーサーとして一時代を築いた男だ。
優勝回数こそ少ないものの速さを追求だけでなく人を魅了することをも追求した
その走りは、今もファンの中で語り継がれている。
記録よりも人々の記憶に残っている稀有なバイクレーサーだ。
それは、速さだけを追求しなければならないレーサーでありながら
人々を魅了する走りをも追及した異端児だからなのかもしれない。
現在は、現役を引退し開発チームのテストドライバーとしてサーキットを走っている。
ピットに巌のバイクが入っていく。鳳翔もピットに向かう。
「親父!」
鳳翔が巌を大声で呼ぶ。
ピットのなかは、指示を出す声やバイクを整備する音で喧騒を響かせている。
「おう。刻か」
巌は、視線を下にしデータが表示されているディスプレイを見ていたが声に気がつくと
鳳翔の顔へ視線を上げた。
ヘルメットは傍らに置いてあり上半身だけライダースーツを脱いで扇風機の前で涼んでいる。
その顔と体は、彫刻された岩のように逞しい。
「珍しいな。何の用だ?」
「一緒に走りにきた」
手短に鳳翔が用件を告げる。巌が面白そうに鳳翔を見つめる。
「いいだろう。今、ちょうど八耐用エンジンの耐久テストの途中だったんだ。
お前、一緒に走れ。手間が省けるし比較データも取れる」
八耐とは、B◎―S◎サーキットで毎年行われるバイクの八時間耐久レースの事だ。
巌は、脱いでいた上半身のライダースーツを着るとヘルメットを脇に抱え自分のマシンに
向かう。
「こいつをスペアマシンに乗っけるから準備してくれ」
巌が鳳翔を指差しメカニックに指示を出していく。
鳳翔もスペアマシンに乗りB◎―S◎サーキットのスタートラインに向かう。
巌は、既にスタートラインで待っている。
「じゃ、行くか。最初は軽く一時間くらいから始めるか」
「おう」
スタートシグナルが赤から青に変わる。鳳翔と巌が同時にスタートを切った。
甲高い排気音がサーキットを支配した。
鳳翔の熱くなった体に水風呂の冷たさが染みていく。
バイクという乗り物の性質上、レーサーには様々な負担がかかる。
特に熱さは、レーサーを襲い続ける最大の敵だ。
コースのアスファルトは、太陽光を反射しその照り返しが容赦ない熱さとなってレーサーを襲う。
更にマシンのエンジンは、周回を重ねるごとに熱を持ち直にレーサーの体を焼く。
そのためレーサーの体温が四十度近くになることも珍しくない
ピットには、レーサーの体を冷やすため扇風機や水風呂が完備されている。
巌も隣で水風呂に漬かっている。上機嫌に下手な演歌まで口ずさんでいる
レースは、圧倒的に巌の方が速かった。
現役を退いたとはいえその腕は、まだまだ錆びついていなかった。
巌は、鳳翔が超えられない一線を易々と超えていく。
それが速さの差だ。鳳翔は、そう思う。
「なあ、親父。俺のテクまだまだ甘いか?」
「いや。今のお前は、俺と同じくらいのテクがある。
連絡先も告げすにN◎VAから出て行って五年間、何処で何やってるか心配したがいい走りをするようになった」
鳳翔が勢いよく立ち上がる。
「じゃあ、何であんな差がつくんだよっ」
「そりゃ、目指す所が違うからな。勝てなくて当然だ」
巌が謎かけのように鳳翔に告げる。
「何だそりゃ? 目指すところってゴールじゃないのかよ?」
鳳翔が再び水風呂に身を浸す。
「お前は、ストリートばかりで走ってたからな。わからんだろうな」
巌が残念そうに呟く。
鳳翔は、あまりサーキットでのレース経験が無い。
十代の頃、偉大な父に反発し主戦場はサーキットではなくストリートだった。
「悪いかよっ! 俺は、自由に走りたかったんだ!」
鳳翔が声を荒げる。
「そもそもそれが違うんだ、刻。お前、どうしてサーキットが自由じゃないって考えるんだ?」
「だって親父。コースが決まっているじゃないか」
鳳翔が指で空中にB◎―S◎サーキットのコース図を描く。
焦れたったそうに巌が後頭部を掻く。
「だからそれが違うんだってーの。
お前、一番速くゴールに向かう方法を考えたことがあるか?」
「コースを一番スピードが乗るライン取りで走ればいいだけだろ」
「違う」
巌があっさりと否定する。
「じゃ、答えは何だよ」
鳳翔が口を尖らせ言った。
「コースに関係なくゴールに誰よりも速く着けばいいんだ」
それが真実という風に巌がきっぱりと言い切る。
鳳翔があきれたように口を開ける。
「例えばずっとコースの内側を走りつづけて一番速くゴールに着くならそうすべきだ。
タイヤバリアに沿って走るのが一番速いならそうすべきだ。
分かるか? 刻。コースなんて決められているようで決められてねぇんだ。
ゴールも同じく決められているようで決められてねぇんだ。
決められているのは、スタートラインだけだ。走り出すのだっていつだっていいんだ。
決めるのは、自分だ。分かったか?」
巌が真面目な顔で熱っぽく語る。
鳳翔が首を捻る。分かるような気もするし分からないような気もする。
巌が熱くなった頭を冷やすように頭から水風呂に潜る。そしてしばらくして頭を上げた。
「分からんようならしばらく一緒に走るか。言葉で分からないなら走りで教えてやる」
鳳翔は、巌の言葉に静かに頷いた。
ジャンルカに敗れてから一週間経った。
鳳翔は、ブラックハウンドの駐車場でトランスポーターが来るのを今か今かと待ち構えている。
足元には、吸殻が何本も落ちている。
新たに煙草を咥え火をつける。すると遠くより排気音が聞えてきた。
トランスポーターの排気音だ。ゆっくりとトランスポーターが駐車場に入ってくる。
コンテナが開きリフトで静と一緒にムラマサが降りてくる。
「お待たせ。刻。完璧に仕上げたわ」
鳳翔が吸い始めた煙草を捨てムラマサに駆け寄る。
静の手から鍵を受け取りムラマサのエンジンに火を入れる。
犬の唸り声のような独特の排気音。何の違和感も感じない澄み切った音だ。
「お袋。ありがとう」
そのままひらりと鳳翔がムラマサに飛び乗る。
「さっさと行きなさい。戦いたい奴がいるんでしょう?
慣らしも終わってちゃんと当たりは出してあるからすぐ戦えるわよ」
静がムラマサの排気音に負けない声で鳳翔に告げる。鳳翔が驚いた表情で静を見る。
静や巌にはジャンルカに負けたことを告げてないのだ。
「これでも一応、あんたの母親よ。それにマシンを見れば何があったかわかる。
父さんもあんたの走りを見て何があったかわかったらしいわ。
勝ったら家に来いって。シャンパン用意しておくから必ず勝てって言ってたわ」
静が微笑み励ますように手を振る。鳳翔が困ったように笑い肩をすくめる。
「これじゃ負けられねぇな。レース前に重い荷物背負わせるなよ」
「そういう重さを背負って走るのが本当のレースよ。今まで縁が無かったのが残念ね」
そうかもしれない。鳳翔が頭の中でそう思う。だが走り出せばそんな事もすぐ忘れるだろう。
アクセルを吹かしムラマサを発進させた。
鳳翔が住宅街の路肩にムラマサを止める。
最初にジャンルカと会った場所だ。今日、ここで再び会えるとは限らない。
だが鳳翔には確信がある。ここにいればジャンルカに再び会えると。
ムラマサに寄りかかり逸る気持ちを抑えるため煙草を取り出し吸い始める。
煙草の長さが半分になった頃、待ち合わせの相手が現れた。
流線型の滑らかなボディに否応無く人の視線を惹きつける真紅を纏った堂々たる姿。
あちらも鳳翔に気がついたようだ。ムラマサの後ろにModel・512が止まる。
運転席の扉が開きジャンルカが降りてくる。
「久しぶりだな」
鳳翔がジャンルカに向かって片手を上げる。
「ああ」
ジャンルカが頷く。その目は、吸いつけられるようにムラマサを見ている。
「いいマシンだ」
ジャンルカが視線を鳳翔に向け言った。
「ああ。俺の相棒だ」
鳳翔がムラマサのボディを撫でる。
しばらくの沈黙の後、鳳翔が真っ直ぐジャンルカを見据える。
「仕事中か?」
「いいや」
ジャンルカが首を振る。
「勝負しないか? 俺も今、休みだ」
「いいだろう。コースは、この前と一緒でいいか?」
鳳翔が頷きそれを見たジャンルカがModel・512に戻っていく。
ジャンルカがふと足を止め鳳翔の方を振り返る。
「そのマシンの声を聞いたことは?」
「いや、無い」
「そうか」
ジャンルカが再び歩を進める。
その背に鳳翔が言葉を投げかける。
「ラインブレイカー。あんた、風の声を聞いたことはあるか?」
ジャンルカが振り返らず歩を止める。
「いや、無い」
「そうだろうな」
鳳翔がその言葉に頷く。
ジャンルカがModel・512に乗り込みムラマサの隣にやって来る。
「スタート方法も前回と一緒でいいな」
ジャンルカが缶コーヒーの空き缶を見せる。
鳳翔が頷く。空き缶が天高く放り投げられた。
Model・512が力強い走りで駆ける。
ムラマサは、切れ味鋭い走りで駆ける。
二台は、絡み合い熾烈に争う。
鳳翔の顔にもジャンルカの顔にも満足そうな笑みが浮かんでいる。
それも走っている間だけだ、ゴールに辿り着けばどちらかの笑みが消える。
レースの世界は、冷酷だ。
その世界にいるのは、勝者と敗者だけだ。
レースの世界は、残酷だ。
一秒にも満たない刹那の瞬間によって勝者と敗者が分けられる。
レースの世界は、非情だ。
勝者は、全てを肯定され敗者は、全て否定される。
レースの世界は、無常だ。
勝者は、永遠に名を刻まれ敗者は、誰にも覚えられることも無く消えていく。
レースの世界は、過酷だ
勝者は、いつまでも勝者ではなく敗者もいつまでも敗者ではない。
敗者は、再び勝者に挑み勝者は、別の勝者に挑む。そして永遠に戦い続ける。
確かにそうかも知れない。
だが誰がそうだと決めたのだろう。
ある男は、言った。
コースなんて決められているようで決められていない。
ゴールも決められているようで決められていない。
決められているのは、スタートラインだけだ。
走り出すのだっていつだっていいんだ。
決めるのは、自分だ。
そう、決めるのは自分なのだ。
コースもゴールもルールもスピードも全て自分が決める。
ゴールは、目前。
Model・512がムラマサの前にいる。
追い抜くスペースは左右どちらにもない。
Model・512のボディがスペースを塞いでいる。
前に出られ追い抜くスペースがないと言う事はもう負けだ。
自分がそう決めるなら負けだ。
「諦めるか!」
鳳翔が叫びゴールを見据える。そう、ゴールこそ目指す場所だ。
天啓のように鳳翔の頭に声が響く。
目指すところは、違う。ゴールではない。その先だ。
鳳翔が見据えていたゴールから目を離す。
そして風景を楽しむように辺りを見回す。
「そうか。そういうことか」
鳳翔がようやく何かに気がついたように呟く。
コースなんて決められているようで決められていない。
ゴールも決められているようで決められていない。
そう、全て自由に自分で決める。
そしてゴールの先を目指し永遠に走らなければならないのだ。
鳳翔がアクセルを全開に開けModel・512に接近する。
そしてテールトゥノーズの体勢に持ち込む。
そのままアクセルは、緩めない。
「風ぇ!」
鳳翔の声に答えるように鳳翔の体の周囲を風が渦巻く。
風がムラマサを空へと導く。
鳳翔の目の前に広がるのは、誰もいない無人の道。
耳に入ってくるのは、ムラマサが風を切る鋭い音。
これが鳳翔の選んだ道。選んだ光景。選んだ音。
見たかった光景。そして聞きたかった音。そして駆け抜けたかった自分だけの道。
この一瞬だけその全てを手に入れる。
夢のような一瞬が過ぎムラマサがModel・512の前に出る。
そのままムラマサがゴールを駆け抜ける。
鳳翔がムラマサを止めヘルメットを外し天を仰ぐ。
ジャンルカもムラマサの横にModel・512を止め運転席から降りてくる。
「やられたな。」
相変わらず表情を変えずにジャンルカが淡々と告げる。
「これで一勝一敗だ。次、会う時が楽しみだな」
鳳翔がそう言うと手を差し出す。ジャンルカがその手を力強く握る。
そしてModel・512の運転席に戻っていく。
振り返らずにジャンルカが静かな声で言った。
「See you again、Over The Top」
そしてそのままModel・512を発進させジャンルカが立ち去る。
「また会おう。頂上を超えたその先で、か」
ジャンルカも鳳翔が見たあの一瞬を見たことがあるのかも知れない。
そう、レースはまだ終わらない。次がある。
そして頂点を超えたその先で新たな挑戦者達が待っている
TOPに戻る