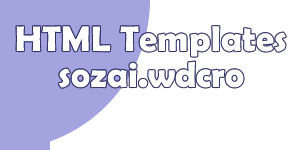Hi’z 5 Errand〜はいず 5 えらんど〜
トーキョーN◎VA-The-Detonation
小説
シーン1 Miss fortung
扉を叩く音で私は、目覚めた。朝は、あまり強い方ではない。
私を急かすようにノックは、続いているがすぐにベッドから降りる気にはならなかった。
ノックは、その間にも続いている。何をそんなに慌てているんだろう?
低血圧のせいでぼうっとする頭で考える。
ここは、トーキョーN◎VAで最大の高級歓楽街、ウェットシティのホテル。
ウェットシティは、その名の通り生身の人間でのサービスが売りの歓楽街だ。
生演奏のコンサートにネットを利用しない本物のディーラー相手のカジノ。
さらに高級娼婦に高級男娼。生身の人間が行うサービスでウェットシティで手に入らないものはない。
街には、ネットのケーブルが蜘蛛の巣のように張り巡らされ人ですら首の後ろに埋め込まれたIANUSというインターフェイスを通じてネットに接続できるこ のトーキョーN◎VAでここまで徹底的に生身にこだわった歓楽街は、ここだけだ。
それが一種のステータスになりここを高級歓楽街にのしあげた。
ここで遊べるのは、一握りの金持ちだけ。残念ながら私は、その一握りではない。
とは、いっても今いるこの部屋は、このホテルに二部屋しかないロイヤルスイート。
一晩泊まるだけで普通のサラリーマンの月給一ヶ月分が飛んでいく。
ノックは、相変わらず続いている。いい加減耳についてうるさい。
「あー、もう。今行くから」
苛立ちの混じった声で扉に向かって怒鳴りつける。
観念したようにベッドから降りる。こういうときDAKがあれば便利なのに。
そう思いながらベッドを降りスリッパに足を通す。
DAKというのは、録音、録画、通信、電話機能にデータ処理機能を持った端末のことだ。
DAKには、バディという擬似人格をもったAIが付属しておりユーザーが指示を出しておけば
その通りのことをやっておいてくれる。
この場合、私が「起きるまで来客は、全部断って。」とバディに指示を出しておけばバディがノックしている人間を
適当にあしらい私は、まだベッドの中で安眠できたわけだ。
扉まで歩きながらふとノックしている人間が誰か考える。
思い当たるのは、ルームサービスか昨日、来なかった待ち人だ。
久しぶりに抱いてもらえると思って待っていたのにそいつは、結局来なかった。
待ちくたびれた私は、バスローブ姿で一人ではもてあます広さのダブルベッドでふて寝した。
そういえば今もバスローブ姿だがまあ、いいだろう。
扉ごしでは、私がどんな姿をしていようとも相手には、関係ないだろう。
あいつだった場合は、気が済むまでありったけの文句をぶつけてやろう。
その後は、気分次第だ。だが生憎と私は、そんな軽い女じゃない。
扉の前に立ち扉の外に声をかける。
「で、何の用?」
相手の返答は、過激だった。確かに今は、朝だ。
熱いシャワーでも浴びてこのぼうっとした頭をはっきりさせたい。
だけど鉛玉のシャワーを浴びせられるとは、思わなかった。
分厚い樫の扉に次々と穴が開いていく。私は、くるりと扉に背を向けベッドの方へと戻る。
生憎、こんな鉛玉一個で命が買われてしまうほど私は、安い女じゃない。
鉛玉は、私の体を掠めることもなくその直線状にある植木鉢やシャンデリアといった調度品を蜂の巣にした。
誰がこの修理費を払うのだろう?絶対、私ではないはずだ。
ベッドに戻るとベッド横の引き出しを開ける。
聖書の隣には、愛用の44オートマグが置いてある。
44オートマグを手に取ると扉の方に引き返す。
あまりにもジャムが多かったためかつてオートジャムと皮肉を込めてその名を呼ばれたこの拳銃は、薬莢をなくし
火薬を固め直接、弾頭の後ろにとりつけたケースレス弾の登場により再び脚光をあびた。
ジャムの原因となる薬莢がなくなり強力な44マグナム弾を連射できるという利点がガンマン達をひきつけた。
私がこの銃を愛用しているのは、他の銃にはないこの個性的なフォルムが気に入ったからだが。
ちょうど扉が開き私の好みではない顔の男達が部屋に踏み込んできた。
手には、クリーナーと呼ばれるサブマシンガン。
私の姿を見て男達が幽霊を見たような驚きの表情を見せる。
なんて失礼な。
「レディの部屋に勝手に踏み込むのは失礼よ」
そう言うと私は、44オートマグの銃口を男達に向け無造作に銃爪を引いていく。
銃爪を引いた数は、全部で六回。倒れた男の数もちょうど六人全員。
全員が死んだことを確認してようやく銃を下ろす。全員死んだ?
低血圧でぼうっとした頭がようやく働き始めあることに気がつく。
「あっ!」
思わす声がでた。自分の失敗に気がつき思わず手で顔を覆う。一人、生かしておくんだった。
全員殺したのでは私を殺しにきた理由やどこの組織の者かわからない。
こんな簡単な事に気がつかなかったなんて。これも低血圧でぼうっとしていたせいだ。
そう思うことにした。気持ちを切り替えバスローブを脱ぎ捨て身支度を整える。
昨夜、着ていた胸元が大きく開いた白のドレスにハイヒールを履く。
ここからは、もうぼうっとしている暇はない。
恐らく近隣の部屋の住人が今の銃声を聞きつけ警察に電話していることだろう。
私のしたことは恐らく正当防衛だろう。だが私も叩かれれば埃がでる身分だ。
警察とはあまり関わりになりたくない。
身支度を整えると二機あるエレベーターの内ちょうど止まっていた方に乗り込む。
もう一台は、下から上がってきている。恐らくホテルに詰めている警備員だろう。
エレベーターの扉が閉まり私は、迷うことなく一階のボタンを押す。
エレベーターは、止まることなく一階に向かう。
扉が開き一階に着く。一階のロビーは、ちょうど朝の出勤ラッシュで込み合っている。
人ごみに紛れ私は、ホテルの外に出る。
しばらく歩き何度か角を曲がりそのたびに後ろを確認する。
尾行は、いないようだ。確認が終わると私は、手を上げタクシーを止める。
ウェットシティらしくロボタクと呼ばれているロボット制御のタクシーではなく人間が運転しているタクシーだ。
タクシーに乗り込むと私は、中年の運転手に行き先を告げる。
中年の運転手の視線は、バックミラーの私の顔と胸元に釘付けになっている。
「アサクサのBAR フォールン・エンジェルまで」
その声に我を取り戻したように中年の運転手は、返事をして車を発進させた。
「ねえ? か私の顔についている? とれてたようだけど」
後ろから猫なで声で話しかける。
「い、いえ。お客さんがあんまりにも美人なもので」
運転手が再びバックミラーの私の顔に視線を送る。
「あら? 本当かしら?」
「本当ですよ。お客さん」
「ふふ、ありがとう」
愛想笑いを浮かべて運転手に礼を言う。運転手が年甲斐もなく真っ赤になっている。
私の顔を見て動揺したかとも思ったが本当にただ単に見とれていただけらしい。
ということは、私は、まだ指名手配されていないということなのだろう。
ま、それも時間の問題だろう。早く身を隠しておくに越したことはない。
それにしてもいったい何に私は、巻き込まれたのだろう?
まったく何がWhat's何だかWhat?まったくわからない。
BARの近くまで来ると私は、運転手に多めに金を渡してタクシーから降りた。
タクシーが走り去るのを見届けて私は、路地にあるBARに向かう。
路地に向かってどんと構えている重い扉を開ける。
扉には、薄っぺらい金属板が打ち付けてありアルファベットでフォールン・エンジェルと刻んである。
扉をあけ店の中を見渡す。珍しくニ脚あるテーブル席が埋まっている。
テーブルに座っているのは、三人と四人の合わせて七人。
たまにはこんな日もあるものだと自分に言い聞かせ気にすることなくカウンターに向かう。
私の履いているハイヒールが床を叩く音がやけにうるさく店内に響く。
カウンターに座り指で顔なじみの若いバーテンダーを呼ぶ。
「シンデレラを」
私は、やってきたバーテンダーに注文を告げる。
シンデレラは、オレンジジュース、レモンジュース、パイナップルジュースをシェークし作るカクテルだ。
これだけならミックスジュースとなんら変わりないがそこはバーテンダーの腕の見せ所。
シェークすることにより違った味わいが楽しめるのだ。
ノンアルコールのためいくら飲んでも酔うことはない。
手早くシェイカーにジュースを注ぎ込みバーテンダーがシェイカーを振る。
出されたシンデレラに私は、口をつける。
果汁のさわやかな甘い味が口の中に広がる。
ようやく一息つけた。グラスを下ろし再び指を上げバーテンダーを呼ぶ。
やってきたバーテンダーに私の口元まで耳を寄せるように指で合図する。
「ねえ? 私のこと狙っている奴のこと知らないかしら?」
BARというのは、たくさんの人間が出入りする。
そして何かしら話をしていく。それは、貴重な情報となる。
それを聞いているバーテンダーは、貴重な情報源だ。
無論、職業柄、お客のプライバシーは、しゃべらないというバーテンダーも少なからず存在する。
そういうご立派な人間は、残念ながらと言うべきかここにはいない。
ここにいるのは、職業意識より自分の利益を優先するバーテンダーだ。
袖の下を渡せばすぐに口を滑らしてくれる。これまでに何度もお世話になってきた。
「さあな」
素っ気無くバーテンダーが答える。そして用が済んだと言うように私から離れていった。
「そ、ありがとう」
私は、そう言うとカクテルが半分くらい残っているグラスに手を伸ばす。
グラスを掴む直前、グラスが砕ける。砕けたグラスの破片が私の指に降りかかる。
幸いにも破片で指が傷つくことはなかった。何が起こったのかは、見なくともわかる。
「なるほど。そういうこと」
私は、離れた場所にいるバーテンダーに冷たい視線を送る。
恐らくテーブル席にいた七人は、私を狙っている連中だろう。
ここに私が来るのを待ち構えていたのだろう。
バーテンダーは、それを知っていながら黙殺したかそれとも私がここにくるという情報を売ったかのどちらかだろう。
耳が早い男だったから恐らく後者だ。
私は、ふうとため息をつき呟く。
「ついてないわね」
後ろの七人は、私に向けて銃口を向けて銃爪を引く。
私は、発砲音に合わせて身を翻す。
強化された反射神経は、発砲音に即座に反応し銃弾が体を貫く前に私は、銃弾の軌道上から移動した。
銃弾の雨は、あきらめることなく執拗に私を追いかけてくる。
私は、軽やかにステップを踏み銃弾をダンスパートナーに迎え踊るように銃弾の雨を避ける。
銃弾の雨が止む。ダンスパートナーは、どうやらお疲れのようだ。
グリップ横のボタンを押し空になったマガジンを床に落としマガジンを交換する。
私は、44オートマグを引き抜き狙いもつけずそのまま銃爪を引く。
相手から大きく外れた軌道を取った銃弾は、壁にあたりピンボールのように跳ね返る。
ボーリングのピンのように四人床に倒れる。続けて銃爪を引く。残り三人も床に倒れる。
「不幸な連中」
倒れた連中を見渡しながら同情するように私は呟く。
なぜ狙いもつけなかった弾丸が命中したのかというと銃弾は、壁に当たり跳弾によって角度を変え襲いかかったのだ。
最初の一人を貫いた弾丸の運動エネルギーは、それだけで収まらす貪欲に次の獲物を求めた。
魔法の弾丸と呼ばれる現象だ。
かつて米国大統領が暗殺された時にも同様の現象が起こったらしい。
あまりにも過去のことなので本当かどうか確かめようもない。
私がやったように発砲のタイミングさえつかめば銃弾をかわすことも不可能ではないこの時代にあって
跳弾を自在に操ることは極めて有効だ。
発砲のタイミングを読まれても弾丸は意外な角度で相手に襲いかかる。
私には、それが可能だ。跳弾は、極めて高い確率で相手の急所に向かう。
これは、技術でもなんでもない。ただ私の運がいいだけだ。
運がいいだけというと大抵の人間は、笑うか胡散臭そうな顔をするが運だけは持って生まれたもの以外に頼りに出来ない。
私は、生まれつき強運の星の下に生まれてきたのだ。
そういう風に生まれるように仕向けられてこの世に生を受けたのだ、私は。
七人をあっという間に倒した私をバーテンダーは、呆然と見つめている。
ぽんと1ゴールドのキャッシュをカウンターに投げると私は、扉に向かう。
扉を開ける直前に私は、肩越しに銃を背後に向け撃つ。
銃弾が跳ね返る音の後にどさっと何かが床に倒れる音。
扉をあけ外に出る際にカウンターにちらりと目をやる。
倒れているのはバーテンダー。手には、シェイカーではなく銃を握っている。
「馬鹿な男」
運の悪い奴に限って間違った選択を選び破滅に向かう。
もっとも私に同情する気は、まったくない。
運の悪い奴が一人死んだ。ただそれだけのことだ。
こんなことは、トーキョーN◎VAでは、日常茶飯事だ。
そういう街なのだ、このトーキョーN◎VAは。
シーン2 Misfortuneに戻る
TOPに戻る
私を急かすようにノックは、続いているがすぐにベッドから降りる気にはならなかった。
ノックは、その間にも続いている。何をそんなに慌てているんだろう?
低血圧のせいでぼうっとする頭で考える。
ここは、トーキョーN◎VAで最大の高級歓楽街、ウェットシティのホテル。
ウェットシティは、その名の通り生身の人間でのサービスが売りの歓楽街だ。
生演奏のコンサートにネットを利用しない本物のディーラー相手のカジノ。
さらに高級娼婦に高級男娼。生身の人間が行うサービスでウェットシティで手に入らないものはない。
街には、ネットのケーブルが蜘蛛の巣のように張り巡らされ人ですら首の後ろに埋め込まれたIANUSというインターフェイスを通じてネットに接続できるこ のトーキョーN◎VAでここまで徹底的に生身にこだわった歓楽街は、ここだけだ。
それが一種のステータスになりここを高級歓楽街にのしあげた。
ここで遊べるのは、一握りの金持ちだけ。残念ながら私は、その一握りではない。
とは、いっても今いるこの部屋は、このホテルに二部屋しかないロイヤルスイート。
一晩泊まるだけで普通のサラリーマンの月給一ヶ月分が飛んでいく。
ノックは、相変わらず続いている。いい加減耳についてうるさい。
「あー、もう。今行くから」
苛立ちの混じった声で扉に向かって怒鳴りつける。
観念したようにベッドから降りる。こういうときDAKがあれば便利なのに。
そう思いながらベッドを降りスリッパに足を通す。
DAKというのは、録音、録画、通信、電話機能にデータ処理機能を持った端末のことだ。
DAKには、バディという擬似人格をもったAIが付属しておりユーザーが指示を出しておけば
その通りのことをやっておいてくれる。
この場合、私が「起きるまで来客は、全部断って。」とバディに指示を出しておけばバディがノックしている人間を
適当にあしらい私は、まだベッドの中で安眠できたわけだ。
扉まで歩きながらふとノックしている人間が誰か考える。
思い当たるのは、ルームサービスか昨日、来なかった待ち人だ。
久しぶりに抱いてもらえると思って待っていたのにそいつは、結局来なかった。
待ちくたびれた私は、バスローブ姿で一人ではもてあます広さのダブルベッドでふて寝した。
そういえば今もバスローブ姿だがまあ、いいだろう。
扉ごしでは、私がどんな姿をしていようとも相手には、関係ないだろう。
あいつだった場合は、気が済むまでありったけの文句をぶつけてやろう。
その後は、気分次第だ。だが生憎と私は、そんな軽い女じゃない。
扉の前に立ち扉の外に声をかける。
「で、何の用?」
相手の返答は、過激だった。確かに今は、朝だ。
熱いシャワーでも浴びてこのぼうっとした頭をはっきりさせたい。
だけど鉛玉のシャワーを浴びせられるとは、思わなかった。
分厚い樫の扉に次々と穴が開いていく。私は、くるりと扉に背を向けベッドの方へと戻る。
生憎、こんな鉛玉一個で命が買われてしまうほど私は、安い女じゃない。
鉛玉は、私の体を掠めることもなくその直線状にある植木鉢やシャンデリアといった調度品を蜂の巣にした。
誰がこの修理費を払うのだろう?絶対、私ではないはずだ。
ベッドに戻るとベッド横の引き出しを開ける。
聖書の隣には、愛用の44オートマグが置いてある。
44オートマグを手に取ると扉の方に引き返す。
あまりにもジャムが多かったためかつてオートジャムと皮肉を込めてその名を呼ばれたこの拳銃は、薬莢をなくし
火薬を固め直接、弾頭の後ろにとりつけたケースレス弾の登場により再び脚光をあびた。
ジャムの原因となる薬莢がなくなり強力な44マグナム弾を連射できるという利点がガンマン達をひきつけた。
私がこの銃を愛用しているのは、他の銃にはないこの個性的なフォルムが気に入ったからだが。
ちょうど扉が開き私の好みではない顔の男達が部屋に踏み込んできた。
手には、クリーナーと呼ばれるサブマシンガン。
私の姿を見て男達が幽霊を見たような驚きの表情を見せる。
なんて失礼な。
「レディの部屋に勝手に踏み込むのは失礼よ」
そう言うと私は、44オートマグの銃口を男達に向け無造作に銃爪を引いていく。
銃爪を引いた数は、全部で六回。倒れた男の数もちょうど六人全員。
全員が死んだことを確認してようやく銃を下ろす。全員死んだ?
低血圧でぼうっとした頭がようやく働き始めあることに気がつく。
「あっ!」
思わす声がでた。自分の失敗に気がつき思わず手で顔を覆う。一人、生かしておくんだった。
全員殺したのでは私を殺しにきた理由やどこの組織の者かわからない。
こんな簡単な事に気がつかなかったなんて。これも低血圧でぼうっとしていたせいだ。
そう思うことにした。気持ちを切り替えバスローブを脱ぎ捨て身支度を整える。
昨夜、着ていた胸元が大きく開いた白のドレスにハイヒールを履く。
ここからは、もうぼうっとしている暇はない。
恐らく近隣の部屋の住人が今の銃声を聞きつけ警察に電話していることだろう。
私のしたことは恐らく正当防衛だろう。だが私も叩かれれば埃がでる身分だ。
警察とはあまり関わりになりたくない。
身支度を整えると二機あるエレベーターの内ちょうど止まっていた方に乗り込む。
もう一台は、下から上がってきている。恐らくホテルに詰めている警備員だろう。
エレベーターの扉が閉まり私は、迷うことなく一階のボタンを押す。
エレベーターは、止まることなく一階に向かう。
扉が開き一階に着く。一階のロビーは、ちょうど朝の出勤ラッシュで込み合っている。
人ごみに紛れ私は、ホテルの外に出る。
しばらく歩き何度か角を曲がりそのたびに後ろを確認する。
尾行は、いないようだ。確認が終わると私は、手を上げタクシーを止める。
ウェットシティらしくロボタクと呼ばれているロボット制御のタクシーではなく人間が運転しているタクシーだ。
タクシーに乗り込むと私は、中年の運転手に行き先を告げる。
中年の運転手の視線は、バックミラーの私の顔と胸元に釘付けになっている。
「アサクサのBAR フォールン・エンジェルまで」
その声に我を取り戻したように中年の運転手は、返事をして車を発進させた。
「ねえ? か私の顔についている? とれてたようだけど」
後ろから猫なで声で話しかける。
「い、いえ。お客さんがあんまりにも美人なもので」
運転手が再びバックミラーの私の顔に視線を送る。
「あら? 本当かしら?」
「本当ですよ。お客さん」
「ふふ、ありがとう」
愛想笑いを浮かべて運転手に礼を言う。運転手が年甲斐もなく真っ赤になっている。
私の顔を見て動揺したかとも思ったが本当にただ単に見とれていただけらしい。
ということは、私は、まだ指名手配されていないということなのだろう。
ま、それも時間の問題だろう。早く身を隠しておくに越したことはない。
それにしてもいったい何に私は、巻き込まれたのだろう?
まったく何がWhat's何だかWhat?まったくわからない。
BARの近くまで来ると私は、運転手に多めに金を渡してタクシーから降りた。
タクシーが走り去るのを見届けて私は、路地にあるBARに向かう。
路地に向かってどんと構えている重い扉を開ける。
扉には、薄っぺらい金属板が打ち付けてありアルファベットでフォールン・エンジェルと刻んである。
扉をあけ店の中を見渡す。珍しくニ脚あるテーブル席が埋まっている。
テーブルに座っているのは、三人と四人の合わせて七人。
たまにはこんな日もあるものだと自分に言い聞かせ気にすることなくカウンターに向かう。
私の履いているハイヒールが床を叩く音がやけにうるさく店内に響く。
カウンターに座り指で顔なじみの若いバーテンダーを呼ぶ。
「シンデレラを」
私は、やってきたバーテンダーに注文を告げる。
シンデレラは、オレンジジュース、レモンジュース、パイナップルジュースをシェークし作るカクテルだ。
これだけならミックスジュースとなんら変わりないがそこはバーテンダーの腕の見せ所。
シェークすることにより違った味わいが楽しめるのだ。
ノンアルコールのためいくら飲んでも酔うことはない。
手早くシェイカーにジュースを注ぎ込みバーテンダーがシェイカーを振る。
出されたシンデレラに私は、口をつける。
果汁のさわやかな甘い味が口の中に広がる。
ようやく一息つけた。グラスを下ろし再び指を上げバーテンダーを呼ぶ。
やってきたバーテンダーに私の口元まで耳を寄せるように指で合図する。
「ねえ? 私のこと狙っている奴のこと知らないかしら?」
BARというのは、たくさんの人間が出入りする。
そして何かしら話をしていく。それは、貴重な情報となる。
それを聞いているバーテンダーは、貴重な情報源だ。
無論、職業柄、お客のプライバシーは、しゃべらないというバーテンダーも少なからず存在する。
そういうご立派な人間は、残念ながらと言うべきかここにはいない。
ここにいるのは、職業意識より自分の利益を優先するバーテンダーだ。
袖の下を渡せばすぐに口を滑らしてくれる。これまでに何度もお世話になってきた。
「さあな」
素っ気無くバーテンダーが答える。そして用が済んだと言うように私から離れていった。
「そ、ありがとう」
私は、そう言うとカクテルが半分くらい残っているグラスに手を伸ばす。
グラスを掴む直前、グラスが砕ける。砕けたグラスの破片が私の指に降りかかる。
幸いにも破片で指が傷つくことはなかった。何が起こったのかは、見なくともわかる。
「なるほど。そういうこと」
私は、離れた場所にいるバーテンダーに冷たい視線を送る。
恐らくテーブル席にいた七人は、私を狙っている連中だろう。
ここに私が来るのを待ち構えていたのだろう。
バーテンダーは、それを知っていながら黙殺したかそれとも私がここにくるという情報を売ったかのどちらかだろう。
耳が早い男だったから恐らく後者だ。
私は、ふうとため息をつき呟く。
「ついてないわね」
後ろの七人は、私に向けて銃口を向けて銃爪を引く。
私は、発砲音に合わせて身を翻す。
強化された反射神経は、発砲音に即座に反応し銃弾が体を貫く前に私は、銃弾の軌道上から移動した。
銃弾の雨は、あきらめることなく執拗に私を追いかけてくる。
私は、軽やかにステップを踏み銃弾をダンスパートナーに迎え踊るように銃弾の雨を避ける。
銃弾の雨が止む。ダンスパートナーは、どうやらお疲れのようだ。
グリップ横のボタンを押し空になったマガジンを床に落としマガジンを交換する。
私は、44オートマグを引き抜き狙いもつけずそのまま銃爪を引く。
相手から大きく外れた軌道を取った銃弾は、壁にあたりピンボールのように跳ね返る。
ボーリングのピンのように四人床に倒れる。続けて銃爪を引く。残り三人も床に倒れる。
「不幸な連中」
倒れた連中を見渡しながら同情するように私は呟く。
なぜ狙いもつけなかった弾丸が命中したのかというと銃弾は、壁に当たり跳弾によって角度を変え襲いかかったのだ。
最初の一人を貫いた弾丸の運動エネルギーは、それだけで収まらす貪欲に次の獲物を求めた。
魔法の弾丸と呼ばれる現象だ。
かつて米国大統領が暗殺された時にも同様の現象が起こったらしい。
あまりにも過去のことなので本当かどうか確かめようもない。
私がやったように発砲のタイミングさえつかめば銃弾をかわすことも不可能ではないこの時代にあって
跳弾を自在に操ることは極めて有効だ。
発砲のタイミングを読まれても弾丸は意外な角度で相手に襲いかかる。
私には、それが可能だ。跳弾は、極めて高い確率で相手の急所に向かう。
これは、技術でもなんでもない。ただ私の運がいいだけだ。
運がいいだけというと大抵の人間は、笑うか胡散臭そうな顔をするが運だけは持って生まれたもの以外に頼りに出来ない。
私は、生まれつき強運の星の下に生まれてきたのだ。
そういう風に生まれるように仕向けられてこの世に生を受けたのだ、私は。
七人をあっという間に倒した私をバーテンダーは、呆然と見つめている。
ぽんと1ゴールドのキャッシュをカウンターに投げると私は、扉に向かう。
扉を開ける直前に私は、肩越しに銃を背後に向け撃つ。
銃弾が跳ね返る音の後にどさっと何かが床に倒れる音。
扉をあけ外に出る際にカウンターにちらりと目をやる。
倒れているのはバーテンダー。手には、シェイカーではなく銃を握っている。
「馬鹿な男」
運の悪い奴に限って間違った選択を選び破滅に向かう。
もっとも私に同情する気は、まったくない。
運の悪い奴が一人死んだ。ただそれだけのことだ。
こんなことは、トーキョーN◎VAでは、日常茶飯事だ。
そういう街なのだ、このトーキョーN◎VAは。
シーン2 Misfortuneに戻る
TOPに戻る