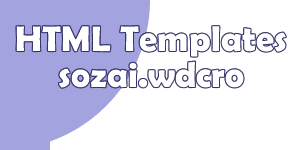Hi’z 5 Errand〜はいず 5 えらんど〜
トーキョーN◎VA-The-Detonation
小説
シーン2〜Kinght born in Night〜
来栖 優は、ベッドも兼ねているソファの上に力なく寝そべりながら呟いた。
「腹へった・・・」
部屋の中は、探偵事務所を兼ねているため整頓されている。
正確に言うならば部屋を整頓するしか仕事がないからだ。
最後に来た仕事は、二週間前の迷い猫探しだ。
これで依頼人が企業の重役なら大もうけなのだが依頼人は、来栖の期待を裏切り小学生だった。
普段なら断るところを小学生は、目に涙を浮かべて来栖に強引に貯金箱を渡し服のすそをつかみながら頼んできたのだ。
来栖は、断りきれず仕方なく引き受けた。
猫は、見つけ出したが収支は、見事に赤字。最後の貯金も使い果たした。
それ以来、冷蔵庫の食料を食い延ばし次の依頼を待っていたが依頼が来る前に一昨日、
ついに食料が底をついた。一昨日からは、水を飲み飢えをしのいでいる。
「だめだ・・・腹・・・へりすぎて・・・眠くなってきた」
来栖は、再び呟いた。来栖の脳裏に寝たら死ぬかもという考えがよぎったが睡魔に勝てずに現実から逃避。
そのまま夢の世界に逃げ込むこととなった。
夢に出てくるのは、決まってトーキョーN◎VAに来る前の日々。
積層要塞都市ニューフォートで暮らしていた頃だ。
運命を変えたあの日、来栖は、大学の帰り道を歩いているとおとぎ話にでてくる魔法使いそのままの格好をした占い師に呼び止められた。
占い師は、この時代では、珍しい木の杖を持ち長い白い髭が印象的な老人だった。
「お主、なかなか面白い相がでておるぞ」
「じいさん。宗教の勧誘なら他でやってくれ」
そう言うと来栖は、占い師の前を通りすぎようとしたが占い師の杖が行く手を阻んだ。
「お主は、今、運命の境目にいる。ここでわしの言葉を聞かんと後悔するぞ」
占い師の言葉は、逆らいがたい雰囲気を持っていた。
来栖は、しぶしぶ卓に座る。占い師は、慣れた手つきでタロットを切り卓に並べていく。
来栖には、置いてあるカードに何の意味があるのかさっぱりわからない。
占い師は、タロットを並べ終わると得心したように頷いた。
「両手を出すがいい」
来栖は、言うとおり両手を卓の上に出した。
占い師は、集中し呪文のようなものを唱えている。呪文が終わると同時に閃光が走った。
光が静まると来栖の手の上には、白銀の剣が載っていた。
柄には、大きなダイアモンドがはまっている。
「その剣は、お主の力になる。お主が望む力を与えてくれるだろう」
来栖が剣を握り持ち上げてみる。重さは、感じない。
しばらく剣を見つめた後、来栖は、口を開いた。
「じいさん。この剣の鞘は、ないのか? このままじゃ危なくて持ち歩けないんだけど」
その言葉を聞き占い師は、面白そうに笑った。
「待っておれ」
占い師は、また呪文のような物を唱えるとその手に鞘が現れた。飾りがついた鞘だ。
占い師の手から鞘を受け取ると来栖は、剣を鞘に収めた。
すると剣は、その存在を何処かへと消した。
「消えた・・・」
「案ずるな。あの剣と鞘は、お主の物じゃ。お主が望む時に現れお主を守るじゃろう」
来栖は、納得いかない顔で自分の手を見つめている。
「ところでお主、剣と鞘どちらが大切かの?」
占い師の問いに来栖は、手から占い師に視線を戻し答える。
「鞘なんじゃねえか」
「その理由は?」
「剣は、なくなっても困らない。だけど鞘がなくなると剣がしまえなくなって困る」
来栖の答えに占い師は、また面白そうに笑った。
「それでよい。鞘を大切にするがよい。さすれば鞘がお主を守ってくれる。
ゆめゆめ忘れることなかれ」
占い師は、そう言うとタロットを片付け卓をしまい始めた。
どうやら占いは、終わりのようだ。
狐につままれたような気分で来栖は、家路についた。
闇の中、二つの声が響く。
一つは、氷の冷たさを持った声。
一つは、暗く重く威厳に満ちた声。
「我が主。剣が騎士の手に渡りましたぞ」
「剣を渡したのは、あやつか?」
「姿は、違えど間違いございません。我が主」
「この時代にあっても我が行く手を阻もうというのか。忌々しい魔道師め」
「我が主。今ならば騎士を殺すことは、たやすいかと思います」
「ほう」
「騎士の方には、我が娘がついております。命令とあれば今すぐにでも騎士は、殺せます」
「ならばすぐに行動に移すが良い。騎士を殺し剣を我らの元へともたらすのだ」
「御心のままに」
翌日、来栖は、大学に来ていた。学部は、経済学部である。
昨日のことが気にかかり今日は、講義に集中できない。
家に帰り剣を呼び出そうとしたが剣は、現れなかった。
(夢だったのか?)
そんな気さえしてくる。教授が講義の終わりを告げる。学生達が次々と席を立ち教室から出て行く。
来栖は、それにも気づかず席に座っている。
「どうしたの? 優。講義、終わったよ」
後ろから声をかけられる。その声にようやく来栖は、我を取り戻し後ろに振り向く。
そこには、雪のように白い肌を持った女性が立っていた。
来栖のガールフレンドのアリーシア・ムトゥだ。
澄んだ青い瞳で心配そうにこちらをみつめている。
「ああ。ごめん。少し考え事をしてた」
「悩み事?」
「大したことじゃない」
来栖は、タップからディスクを抜きズボンのポケットに突っ込むと立ち上がった。
「あとでデータくれないか。講義聞いてなかった」
「仕方ないなぁ。その代わり昼ご飯おごってね」
「いいよ」
「こういう時、IAUNUSつけとけば便利なのにね」
アリーシアが言い終わってから自分の失敗に気づいた。
「ああ」
来栖は、不機嫌そうに返事する。
来栖は、ほとんどの人がつけている脳内コンピューターIANUSをつけていない。
なぜなら来栖は、体がサイバーパーツに適合できないという極めて稀な体質なのだ。
今のところ治療方法は、見つかっていない。
「ごめん。気にしてたよね」
アリーシアが不機嫌な来栖の表情に気づきあやまる。
アリーシアもIANUSをつけていない。来栖は、その理由を聞いていない。
そのことを聞くとアリーシアが傷つきそうな気がしたからだ。
「別にいいさ」
そう言うと表情を元に戻す。教室から出て食堂に向かう。アリーシアが並んで横を歩く。
食堂は、学生達で込み合っている。
「好きな物選べよ」
「うん。ありがと」
列に並んで来栖とアリーシアもトレイを手に取る。
来栖は、ハンバーガーとフライドポテトとコーラをトレイに載せる。
アリーシアは、ミートソーススパゲッティに野菜サラダとエスプレッソをトレイに載せる。
来栖はアリーシアの分の料金も支払い席を探す。
幸い窓際の席が一つ空いている。
来栖は、その席に座る。向かいには、アリーシアが座る。
アリーシアが来栖のトレイを覗き込み眉をひそめる。
「またジャンクフードばかり。体に悪いよ」
「好きなんだから仕方ないだろ。お前こそ食いすぎは、太るぞ」
「残念でした。きちんとカロリー計算してますからこのくらい食べても平気だよ」
お互いに笑いながら食事は、進んでいく。
「ねぇ。今日、何の日か知ってる?」
食後のエスプレッソを飲みながらアリーシアが来栖に尋ねてきた。
「何の日だったかなぁ」
来栖がコーラを飲みながらとぼけた口調で答える。
「本当にわからない?」
来栖の答えにアリーシアは、すねたように口を尖らす。
「わかってるよ。今日は、君と付き合い始めた日だろ」
その答えにアリーシアが満面の笑顔を浮かべた。
「そう! 覚えててくれたんだ!」
「忘れるものか」
来栖がコーラを飲み干し空になったトレイの上に置く。
アリーシアは、うつむきエスプレッソをスプーンでかき回している。
やがて決心したように顔を上げて口を開いた。
「優。今晩空いてる?」
「暇だよ」
「今晩、デートしない?」
アリーシアの頬が真っ赤に染まっている。
雪のような白い肌に赤に染まった頬が美しい。その美しさに来栖は、しばし呆然とした。
「・・・答え聞きたいんだけど」
来栖の答えを待ちきれなくなりアリーシアが口を開く。
いつもよりぶっきらぼうな口調がアリーシアの心境を表していた。
「いいよ」
いつもと違うアリーシアの様子に来栖は、慌てて答える。
「じゃあ、今晩七時に公園の噴水の前で待ち合わせ。遅れないでね」
「わかった」
アリーシアが腕時計を見る。
「もうこんな時間。私、行くね。昼ご飯おごってくれてありがと」
「別にいいさ。データ写し終わったら返すよ」
アリーシアは、トレイを持って立ち上がり食堂の出口の方へ歩いていった。
来栖は、その後ろ姿を見送るともう一杯コーラを飲むべくグラスを持って立ち上がった。
来栖は、腕時計を見た。すでに今日は、終わり明日になっていた。
七時に約束通り公園でアリーシアと待ち合わせレストランで一緒に食事し色々と楽しんでいるうちにこんな時間になってしまった。
いつもならすでに別れてお互い家路についている筈なのだが今日は、アリーシアがあともうちょっとと言うのでこんな時間になってしまった。
アリーシアは、公園のブランコに座り月を眺めている。
月は、きれいな円を描いている。
アリーシアが疲れた様子の来栖を見て公園についたらデートは、終わりという約束でここまで戻ってきたのだ。
来栖は、ブランコの前の柵に腰掛けた。
「ねぇ。優。最初に出合った時のこと覚えてる?」
「なんだよ。唐突に。覚えているよ」
最初は、来栖がアリーシアに声をかけたのがきっかけだった。
名前の響きから同じ日系人だと思って声をかけたのだ。
アリーシアは、日系人では、なくルーマニア系ヴィル・ヌーブ人だった。
アリーシアは、声をかけてきた来栖がIANUSをつけてないことに気がつき自分もIANUSをつけてないことを来栖に告げた。
お互い話してみると気が合いそれ以来なんとなく一緒にいることが多くなっていった。
正式につきあおうと言ったのは、来栖からだった。
アリーシアは、微笑みながらいいよと言ってくれた。
一年前の事だが来栖には、昨日の事のように正確に思い出せた。
「もう一年か。早いもんだ」
「色々あって楽しかったね」
「ああ」
「ねぇ、優」
今までに聞いたことがないようなアリーシアの甘い声が来栖の耳に届いた。
「昨日、剣を貰ったでしょ」
「ああ。変な占い師のじいさんに貰った」
甘い声に来栖の脳は、しびれたようになっている。まるで熱病にかかったみたいだ。
「私、その剣が欲しいの」
「ああ。いいけどどうやったら出てくるかわからないんだ」
「大丈夫。優が望めばでてくるわ」
来栖は、アリーシアに促され剣が出てくるように願った。
剣は、何もない空間よりゆっくりと現れる。
来栖は、現れた剣の真ん中を掴んだ。やはり何も重さを感じない。
「それをこっちに渡して」
来栖は、立ち上がりふらふらと頼りない足取りでアリーシアの元へ向かう。
そのまま剣をアリーシアに差し出す。アリーシアが剣に触れる。
その時、柄にはまっているダイアモンドが輝いた。光が辺りを昼間のように照らす。
それと同時に来栖の脳内に圧倒的な記憶が流れ込んでくる。
(何だ・・・。これは・・・)
今ではない場所。
ここではない時代。
迷宮。
戦う魔物と人間。
繰り広げられる別れと出会い。
生と死。
役目を終え眠る剣。その剣が今、来栖の手にある。
光が消え去る。熱病にかかかっていたような脳の感覚も消え去っている。
アリーシアは、光を避けるように手で顔を覆っている。
「アリーシア」
来栖がアリーシアを気遣うように呼びかける。
アリーシアが顔を覆っていた手をどけ顔を上げる。
そこには、見慣れたアリーシアの顔は、なかった。
澄んだ青い瞳は、血に濡れたような赤い瞳に、雪のように白い肌は、月の光に濡れたように青白い肌に変わり妖艶な雰囲気を放っていた。
「アリーシア・・・いったい何が起こった」
アリーシアの変化に来栖は、戸惑う。再び剣より記憶が流れ込んでくる。
「魔物だと・・・。アリーシアが・・・」
「そう。私、人間じゃないの」
来栖の言葉にアリーシアが悲しげに答えた。
「本当の私は、太陽の光を浴びる世界の住人ではなく月の光を浴びる世界の住人。
この姿が本当の姿」
アリーシアが悲しげに微笑み言葉を続ける。
「私、父に言われてあなたを見張っていたの」
「俺を見張っていた? なぜ?」
「あなたが騎士だから」
「俺が騎士?俺は、ただの人間だ」
「私もそうならいいと思っていた。でもあなたは、剣を手に入れてしまった。
その剣が騎士の証なのよ」
「この剣が・・・?」
「私、あなたを殺してその剣を手に入れなければならないの」
(アリーシアになら殺されてもいいかな)
アリーシアの今にも泣き出しそうな表情を見つめながら来栖は、思った。
それに彼女が魔物だというなら抵抗しても勝てないだろう。
来栖は、自分が狂ってしまったかと思ったがあいにくとそうではないらしい。
心に恐怖はなくむしろ冷静そのものだった。
「いいよ」
来栖がアリーシアに優しく微笑んだ。手に持っていた剣を地面に投げ捨てる。
「え・・・?」
「俺を殺して剣を持っていったらいいさ。それしか方法がないんだろ?」
「あなた、自分の言っていることがわかってるの?」
アリーシアの赤い瞳から大粒の涙がこぼれる。
「わかってるよ」
「わかってない。あなた死ぬのよ」
「君に殺されるのなら別にいいさ。さっきそう思った。
それに抵抗しても君に勝てそうにもない。他にいい方法もなさそうだしな。その代わり」
アリーシアは、来栖の言葉を待った。
来栖の顔は、相変わらず優しくアリーシアに微笑んでいる。
「痛くしないで一思いにやってくれ」
「バカッ」
アリーシアが来栖の胸に飛び込んでくる。子供のように来栖の胸を叩く。
「痛いよ」
「あなた大バカよ。どうして逃げたり恐がったりしてくれないの? どうしてそんなに冷静なの?
そしたら私だって単なる魔物としてあなたを殺せるのに」
「ごめんな」
来栖は、泣きじゃくるアリーシアを抱きしめ頭を撫でる。
アリーシアは、大きな声をあげて泣いた。二人は長い間そうしていた。
アリーシアが来栖を見上げた。赤い瞳が赤く腫れている。
「泣き止んだか?」
「うん」
来栖がアリーシアの瞳を見つめる。この血のように赤い瞳も月の光を浴びて濡れたようになっている青白い肌もきれいだと思う。
最後にきれいな本当のアリーシアを抱けて満足だった。
アリーシアが来栖に微笑む。
「優のこと忘れないよ。永遠に」
「ああ、ありがと」
アリーシアの顔がゆっくりと来栖の首筋に近づいていく。来栖が目を閉じる。
アリーシアの顔が首筋に覆
いさった。痛みは、襲ってこない。
背後に落ちていた剣のダイアモンドが輝いた。
アリーシアの顔が首筋から力なく肩にもたれかかる。
「アリーシア?」
来栖は、目を開きアリーシアの様子を窺う。アリーシアを抱く手に濡れたような感触がある。ゆっくりと手を目の前に持ってくる。
手は、赤く染まっている。慌ててアリーシアの背中を見る。背中に真一文字の赤い線ができている。
赤い線は、鋭利な刃物で切りつけたようだった。
赤い血がとめどなく流れ出してくる。
「アリーシア」
来栖の呼びかけにアリーシアが顔を上げる。アリーシアが弱々しく微笑む。
「優」
「しっかりしろ」
「もう・・・だめ・・・みたい。ねぇ・・・優。最後の・・・お願い・・・聞いてくれる?」
「ああ」
「キス・・・してくれる?」
来栖は、無言でアリーシアと唇を重ねた。 最後のキスは、血の味がした。唇が離れる。
「私・・・優のこと・・・本当に・・・好きだったよ・・・」
耳にようやく届くくらいの小さな声で途切れ途切れにアリーシアが呟いた。言い終えると眠るように瞳を閉じた。
アリーシアの体がゆっくりと消えていく。
体が全て消えるまでそれほど時間は、かからなかった。
来栖が嗚咽をもらす。次第にそれは、大きくなっていった。
翌日、来栖は、大学に中退届を提出し姿を消した。
闇の中、二つの声が響く。
一つは、氷の冷たさを持った声。
一つは、暗く重く威厳に満ちた声。
「我が主」
「騎士は、仕留めたか?」
「残念ながら生きております。しかし奴は、もう騎士としては、戦えないでしょう」
「ほう?」
「体は、殺せませんでしたが心を殺しました」
「そうか。ならばよい」
積層都市ニューフォートの外は、年々増加する人口のため臨時の居住区が建設されている。
無計画に建築される居住区は、次第にスラム街となっていった。
そのスラム街の一角。不法投棄されたゴミに埋もれた場所に来栖はいた。
瞳は、にごり生気が感じられない。力なく四肢を投げ出しゴミの山に埋もれている。
「探したぞ。お若いの」
杖を携えた白髪の占い師は、ゴミに埋もれる来栖に声をかけた。
来栖は、ゴミに埋もれたまま動こうとしない。
「忘れ物じゃ」
占い師は、来栖の足元に剣を置く。
アリーシアが死んだあの日来栖は、剣を公園に置いたままだった。
アリーシアが死んだ原因になった剣を再び触ることに嫌悪したからだ。
「「じいさん・・・。騎士って・・・なんだ?」
来栖が張りのない声で占い師に尋ねた。
あの日アリーシアは、自分のことを騎士だと言った。自分では、心当たりがない。
だが剣を持っていたこの占い師ならば知っているはずだ。
「騎士とは、この剣を振るい魔物を倒す者のことじゃ」
「俺は、そんなことするつもりはない・・・。持って帰ってくれ」
「そうは、いかぬ。剣は、お主を選んだ」
「迷惑だ。アリーシアを殺した剣なんて・・・いらねぇよ」
「剣は、単なる道具じゃ。振るう者の意志によって善にも悪にもなる。お主、あの時何を思った。
なぜその剣を持ち娘と共に生きる道を選らなかった」
「・・・」
「望むならば剣は、お主にその力を与えただろう。
お主が死を選んだために剣は、お主を守るためにあの娘を殺さねばならなかった」
「俺が・・・悪いというのか?」
「そうじゃ」
来栖が自虐的に笑い始める。
占い師は、その痛々しい来栖の様子にも何の表情も浮かべなかった。
占い師が口を開く。
「すでに運命の輪は、回り始めている。お主は、すでにその輪の中にいるのだ」
来栖がその言葉を聞き笑いを止める。
来栖がゆっくりとゴミの山から立ち上がり落ちていた剣を取る。
「運命の輪か。輪ならアリーシアのいた所に戻ることもできるな」
来栖がしっかりとした足取りで歩き始める。天に届くように吼える。
「俺が望む力は、大切な者を守る力と運命を切り開く力、そして運命の輪が再び巡り合うまで生き抜く力だ」
剣が主の呼びかけに答えるように柄のダイアモンドが光り輝く。
「じいさん。これが俺の望む力だ。俺は、もう二度と過ちを繰り返さない。これでいいか」
「旅立つが良い。運命の輪は、東の新星を指しておる」
来栖は、その声にも振り返らずアスファルトを一歩一歩踏みしめ歩いていった。
闇の中、二つの声が響く。
一つは、氷の冷たさを持った声。
一つは、暗く重く威厳に満ちた声。
「我が主」
「わかっておる。忌々しい魔道士め。騎士を蘇らせるとは。すぐに騎士に追っ手を差し向けろ。N◎VAに行かれると厄介なことになる」
「御心のままに」
来栖は、襲いかかる魔物を倒し運命を切り開きトーキョーN◎VAにたどり着くのは、
半年後の事だった。
そしてすぐに探偵組合N・I・Kの審査に合格し新宿に探偵事務所を開いた。
「腹へった・・・」
部屋の中は、探偵事務所を兼ねているため整頓されている。
正確に言うならば部屋を整頓するしか仕事がないからだ。
最後に来た仕事は、二週間前の迷い猫探しだ。
これで依頼人が企業の重役なら大もうけなのだが依頼人は、来栖の期待を裏切り小学生だった。
普段なら断るところを小学生は、目に涙を浮かべて来栖に強引に貯金箱を渡し服のすそをつかみながら頼んできたのだ。
来栖は、断りきれず仕方なく引き受けた。
猫は、見つけ出したが収支は、見事に赤字。最後の貯金も使い果たした。
それ以来、冷蔵庫の食料を食い延ばし次の依頼を待っていたが依頼が来る前に一昨日、
ついに食料が底をついた。一昨日からは、水を飲み飢えをしのいでいる。
「だめだ・・・腹・・・へりすぎて・・・眠くなってきた」
来栖は、再び呟いた。来栖の脳裏に寝たら死ぬかもという考えがよぎったが睡魔に勝てずに現実から逃避。
そのまま夢の世界に逃げ込むこととなった。
夢に出てくるのは、決まってトーキョーN◎VAに来る前の日々。
積層要塞都市ニューフォートで暮らしていた頃だ。
運命を変えたあの日、来栖は、大学の帰り道を歩いているとおとぎ話にでてくる魔法使いそのままの格好をした占い師に呼び止められた。
占い師は、この時代では、珍しい木の杖を持ち長い白い髭が印象的な老人だった。
「お主、なかなか面白い相がでておるぞ」
「じいさん。宗教の勧誘なら他でやってくれ」
そう言うと来栖は、占い師の前を通りすぎようとしたが占い師の杖が行く手を阻んだ。
「お主は、今、運命の境目にいる。ここでわしの言葉を聞かんと後悔するぞ」
占い師の言葉は、逆らいがたい雰囲気を持っていた。
来栖は、しぶしぶ卓に座る。占い師は、慣れた手つきでタロットを切り卓に並べていく。
来栖には、置いてあるカードに何の意味があるのかさっぱりわからない。
占い師は、タロットを並べ終わると得心したように頷いた。
「両手を出すがいい」
来栖は、言うとおり両手を卓の上に出した。
占い師は、集中し呪文のようなものを唱えている。呪文が終わると同時に閃光が走った。
光が静まると来栖の手の上には、白銀の剣が載っていた。
柄には、大きなダイアモンドがはまっている。
「その剣は、お主の力になる。お主が望む力を与えてくれるだろう」
来栖が剣を握り持ち上げてみる。重さは、感じない。
しばらく剣を見つめた後、来栖は、口を開いた。
「じいさん。この剣の鞘は、ないのか? このままじゃ危なくて持ち歩けないんだけど」
その言葉を聞き占い師は、面白そうに笑った。
「待っておれ」
占い師は、また呪文のような物を唱えるとその手に鞘が現れた。飾りがついた鞘だ。
占い師の手から鞘を受け取ると来栖は、剣を鞘に収めた。
すると剣は、その存在を何処かへと消した。
「消えた・・・」
「案ずるな。あの剣と鞘は、お主の物じゃ。お主が望む時に現れお主を守るじゃろう」
来栖は、納得いかない顔で自分の手を見つめている。
「ところでお主、剣と鞘どちらが大切かの?」
占い師の問いに来栖は、手から占い師に視線を戻し答える。
「鞘なんじゃねえか」
「その理由は?」
「剣は、なくなっても困らない。だけど鞘がなくなると剣がしまえなくなって困る」
来栖の答えに占い師は、また面白そうに笑った。
「それでよい。鞘を大切にするがよい。さすれば鞘がお主を守ってくれる。
ゆめゆめ忘れることなかれ」
占い師は、そう言うとタロットを片付け卓をしまい始めた。
どうやら占いは、終わりのようだ。
狐につままれたような気分で来栖は、家路についた。
闇の中、二つの声が響く。
一つは、氷の冷たさを持った声。
一つは、暗く重く威厳に満ちた声。
「我が主。剣が騎士の手に渡りましたぞ」
「剣を渡したのは、あやつか?」
「姿は、違えど間違いございません。我が主」
「この時代にあっても我が行く手を阻もうというのか。忌々しい魔道師め」
「我が主。今ならば騎士を殺すことは、たやすいかと思います」
「ほう」
「騎士の方には、我が娘がついております。命令とあれば今すぐにでも騎士は、殺せます」
「ならばすぐに行動に移すが良い。騎士を殺し剣を我らの元へともたらすのだ」
「御心のままに」
翌日、来栖は、大学に来ていた。学部は、経済学部である。
昨日のことが気にかかり今日は、講義に集中できない。
家に帰り剣を呼び出そうとしたが剣は、現れなかった。
(夢だったのか?)
そんな気さえしてくる。教授が講義の終わりを告げる。学生達が次々と席を立ち教室から出て行く。
来栖は、それにも気づかず席に座っている。
「どうしたの? 優。講義、終わったよ」
後ろから声をかけられる。その声にようやく来栖は、我を取り戻し後ろに振り向く。
そこには、雪のように白い肌を持った女性が立っていた。
来栖のガールフレンドのアリーシア・ムトゥだ。
澄んだ青い瞳で心配そうにこちらをみつめている。
「ああ。ごめん。少し考え事をしてた」
「悩み事?」
「大したことじゃない」
来栖は、タップからディスクを抜きズボンのポケットに突っ込むと立ち上がった。
「あとでデータくれないか。講義聞いてなかった」
「仕方ないなぁ。その代わり昼ご飯おごってね」
「いいよ」
「こういう時、IAUNUSつけとけば便利なのにね」
アリーシアが言い終わってから自分の失敗に気づいた。
「ああ」
来栖は、不機嫌そうに返事する。
来栖は、ほとんどの人がつけている脳内コンピューターIANUSをつけていない。
なぜなら来栖は、体がサイバーパーツに適合できないという極めて稀な体質なのだ。
今のところ治療方法は、見つかっていない。
「ごめん。気にしてたよね」
アリーシアが不機嫌な来栖の表情に気づきあやまる。
アリーシアもIANUSをつけていない。来栖は、その理由を聞いていない。
そのことを聞くとアリーシアが傷つきそうな気がしたからだ。
「別にいいさ」
そう言うと表情を元に戻す。教室から出て食堂に向かう。アリーシアが並んで横を歩く。
食堂は、学生達で込み合っている。
「好きな物選べよ」
「うん。ありがと」
列に並んで来栖とアリーシアもトレイを手に取る。
来栖は、ハンバーガーとフライドポテトとコーラをトレイに載せる。
アリーシアは、ミートソーススパゲッティに野菜サラダとエスプレッソをトレイに載せる。
来栖はアリーシアの分の料金も支払い席を探す。
幸い窓際の席が一つ空いている。
来栖は、その席に座る。向かいには、アリーシアが座る。
アリーシアが来栖のトレイを覗き込み眉をひそめる。
「またジャンクフードばかり。体に悪いよ」
「好きなんだから仕方ないだろ。お前こそ食いすぎは、太るぞ」
「残念でした。きちんとカロリー計算してますからこのくらい食べても平気だよ」
お互いに笑いながら食事は、進んでいく。
「ねぇ。今日、何の日か知ってる?」
食後のエスプレッソを飲みながらアリーシアが来栖に尋ねてきた。
「何の日だったかなぁ」
来栖がコーラを飲みながらとぼけた口調で答える。
「本当にわからない?」
来栖の答えにアリーシアは、すねたように口を尖らす。
「わかってるよ。今日は、君と付き合い始めた日だろ」
その答えにアリーシアが満面の笑顔を浮かべた。
「そう! 覚えててくれたんだ!」
「忘れるものか」
来栖がコーラを飲み干し空になったトレイの上に置く。
アリーシアは、うつむきエスプレッソをスプーンでかき回している。
やがて決心したように顔を上げて口を開いた。
「優。今晩空いてる?」
「暇だよ」
「今晩、デートしない?」
アリーシアの頬が真っ赤に染まっている。
雪のような白い肌に赤に染まった頬が美しい。その美しさに来栖は、しばし呆然とした。
「・・・答え聞きたいんだけど」
来栖の答えを待ちきれなくなりアリーシアが口を開く。
いつもよりぶっきらぼうな口調がアリーシアの心境を表していた。
「いいよ」
いつもと違うアリーシアの様子に来栖は、慌てて答える。
「じゃあ、今晩七時に公園の噴水の前で待ち合わせ。遅れないでね」
「わかった」
アリーシアが腕時計を見る。
「もうこんな時間。私、行くね。昼ご飯おごってくれてありがと」
「別にいいさ。データ写し終わったら返すよ」
アリーシアは、トレイを持って立ち上がり食堂の出口の方へ歩いていった。
来栖は、その後ろ姿を見送るともう一杯コーラを飲むべくグラスを持って立ち上がった。
来栖は、腕時計を見た。すでに今日は、終わり明日になっていた。
七時に約束通り公園でアリーシアと待ち合わせレストランで一緒に食事し色々と楽しんでいるうちにこんな時間になってしまった。
いつもならすでに別れてお互い家路についている筈なのだが今日は、アリーシアがあともうちょっとと言うのでこんな時間になってしまった。
アリーシアは、公園のブランコに座り月を眺めている。
月は、きれいな円を描いている。
アリーシアが疲れた様子の来栖を見て公園についたらデートは、終わりという約束でここまで戻ってきたのだ。
来栖は、ブランコの前の柵に腰掛けた。
「ねぇ。優。最初に出合った時のこと覚えてる?」
「なんだよ。唐突に。覚えているよ」
最初は、来栖がアリーシアに声をかけたのがきっかけだった。
名前の響きから同じ日系人だと思って声をかけたのだ。
アリーシアは、日系人では、なくルーマニア系ヴィル・ヌーブ人だった。
アリーシアは、声をかけてきた来栖がIANUSをつけてないことに気がつき自分もIANUSをつけてないことを来栖に告げた。
お互い話してみると気が合いそれ以来なんとなく一緒にいることが多くなっていった。
正式につきあおうと言ったのは、来栖からだった。
アリーシアは、微笑みながらいいよと言ってくれた。
一年前の事だが来栖には、昨日の事のように正確に思い出せた。
「もう一年か。早いもんだ」
「色々あって楽しかったね」
「ああ」
「ねぇ、優」
今までに聞いたことがないようなアリーシアの甘い声が来栖の耳に届いた。
「昨日、剣を貰ったでしょ」
「ああ。変な占い師のじいさんに貰った」
甘い声に来栖の脳は、しびれたようになっている。まるで熱病にかかったみたいだ。
「私、その剣が欲しいの」
「ああ。いいけどどうやったら出てくるかわからないんだ」
「大丈夫。優が望めばでてくるわ」
来栖は、アリーシアに促され剣が出てくるように願った。
剣は、何もない空間よりゆっくりと現れる。
来栖は、現れた剣の真ん中を掴んだ。やはり何も重さを感じない。
「それをこっちに渡して」
来栖は、立ち上がりふらふらと頼りない足取りでアリーシアの元へ向かう。
そのまま剣をアリーシアに差し出す。アリーシアが剣に触れる。
その時、柄にはまっているダイアモンドが輝いた。光が辺りを昼間のように照らす。
それと同時に来栖の脳内に圧倒的な記憶が流れ込んでくる。
(何だ・・・。これは・・・)
今ではない場所。
ここではない時代。
迷宮。
戦う魔物と人間。
繰り広げられる別れと出会い。
生と死。
役目を終え眠る剣。その剣が今、来栖の手にある。
光が消え去る。熱病にかかかっていたような脳の感覚も消え去っている。
アリーシアは、光を避けるように手で顔を覆っている。
「アリーシア」
来栖がアリーシアを気遣うように呼びかける。
アリーシアが顔を覆っていた手をどけ顔を上げる。
そこには、見慣れたアリーシアの顔は、なかった。
澄んだ青い瞳は、血に濡れたような赤い瞳に、雪のように白い肌は、月の光に濡れたように青白い肌に変わり妖艶な雰囲気を放っていた。
「アリーシア・・・いったい何が起こった」
アリーシアの変化に来栖は、戸惑う。再び剣より記憶が流れ込んでくる。
「魔物だと・・・。アリーシアが・・・」
「そう。私、人間じゃないの」
来栖の言葉にアリーシアが悲しげに答えた。
「本当の私は、太陽の光を浴びる世界の住人ではなく月の光を浴びる世界の住人。
この姿が本当の姿」
アリーシアが悲しげに微笑み言葉を続ける。
「私、父に言われてあなたを見張っていたの」
「俺を見張っていた? なぜ?」
「あなたが騎士だから」
「俺が騎士?俺は、ただの人間だ」
「私もそうならいいと思っていた。でもあなたは、剣を手に入れてしまった。
その剣が騎士の証なのよ」
「この剣が・・・?」
「私、あなたを殺してその剣を手に入れなければならないの」
(アリーシアになら殺されてもいいかな)
アリーシアの今にも泣き出しそうな表情を見つめながら来栖は、思った。
それに彼女が魔物だというなら抵抗しても勝てないだろう。
来栖は、自分が狂ってしまったかと思ったがあいにくとそうではないらしい。
心に恐怖はなくむしろ冷静そのものだった。
「いいよ」
来栖がアリーシアに優しく微笑んだ。手に持っていた剣を地面に投げ捨てる。
「え・・・?」
「俺を殺して剣を持っていったらいいさ。それしか方法がないんだろ?」
「あなた、自分の言っていることがわかってるの?」
アリーシアの赤い瞳から大粒の涙がこぼれる。
「わかってるよ」
「わかってない。あなた死ぬのよ」
「君に殺されるのなら別にいいさ。さっきそう思った。
それに抵抗しても君に勝てそうにもない。他にいい方法もなさそうだしな。その代わり」
アリーシアは、来栖の言葉を待った。
来栖の顔は、相変わらず優しくアリーシアに微笑んでいる。
「痛くしないで一思いにやってくれ」
「バカッ」
アリーシアが来栖の胸に飛び込んでくる。子供のように来栖の胸を叩く。
「痛いよ」
「あなた大バカよ。どうして逃げたり恐がったりしてくれないの? どうしてそんなに冷静なの?
そしたら私だって単なる魔物としてあなたを殺せるのに」
「ごめんな」
来栖は、泣きじゃくるアリーシアを抱きしめ頭を撫でる。
アリーシアは、大きな声をあげて泣いた。二人は長い間そうしていた。
アリーシアが来栖を見上げた。赤い瞳が赤く腫れている。
「泣き止んだか?」
「うん」
来栖がアリーシアの瞳を見つめる。この血のように赤い瞳も月の光を浴びて濡れたようになっている青白い肌もきれいだと思う。
最後にきれいな本当のアリーシアを抱けて満足だった。
アリーシアが来栖に微笑む。
「優のこと忘れないよ。永遠に」
「ああ、ありがと」
アリーシアの顔がゆっくりと来栖の首筋に近づいていく。来栖が目を閉じる。
アリーシアの顔が首筋に覆
いさった。痛みは、襲ってこない。
背後に落ちていた剣のダイアモンドが輝いた。
アリーシアの顔が首筋から力なく肩にもたれかかる。
「アリーシア?」
来栖は、目を開きアリーシアの様子を窺う。アリーシアを抱く手に濡れたような感触がある。ゆっくりと手を目の前に持ってくる。
手は、赤く染まっている。慌ててアリーシアの背中を見る。背中に真一文字の赤い線ができている。
赤い線は、鋭利な刃物で切りつけたようだった。
赤い血がとめどなく流れ出してくる。
「アリーシア」
来栖の呼びかけにアリーシアが顔を上げる。アリーシアが弱々しく微笑む。
「優」
「しっかりしろ」
「もう・・・だめ・・・みたい。ねぇ・・・優。最後の・・・お願い・・・聞いてくれる?」
「ああ」
「キス・・・してくれる?」
来栖は、無言でアリーシアと唇を重ねた。 最後のキスは、血の味がした。唇が離れる。
「私・・・優のこと・・・本当に・・・好きだったよ・・・」
耳にようやく届くくらいの小さな声で途切れ途切れにアリーシアが呟いた。言い終えると眠るように瞳を閉じた。
アリーシアの体がゆっくりと消えていく。
体が全て消えるまでそれほど時間は、かからなかった。
来栖が嗚咽をもらす。次第にそれは、大きくなっていった。
翌日、来栖は、大学に中退届を提出し姿を消した。
闇の中、二つの声が響く。
一つは、氷の冷たさを持った声。
一つは、暗く重く威厳に満ちた声。
「我が主」
「騎士は、仕留めたか?」
「残念ながら生きております。しかし奴は、もう騎士としては、戦えないでしょう」
「ほう?」
「体は、殺せませんでしたが心を殺しました」
「そうか。ならばよい」
積層都市ニューフォートの外は、年々増加する人口のため臨時の居住区が建設されている。
無計画に建築される居住区は、次第にスラム街となっていった。
そのスラム街の一角。不法投棄されたゴミに埋もれた場所に来栖はいた。
瞳は、にごり生気が感じられない。力なく四肢を投げ出しゴミの山に埋もれている。
「探したぞ。お若いの」
杖を携えた白髪の占い師は、ゴミに埋もれる来栖に声をかけた。
来栖は、ゴミに埋もれたまま動こうとしない。
「忘れ物じゃ」
占い師は、来栖の足元に剣を置く。
アリーシアが死んだあの日来栖は、剣を公園に置いたままだった。
アリーシアが死んだ原因になった剣を再び触ることに嫌悪したからだ。
「「じいさん・・・。騎士って・・・なんだ?」
来栖が張りのない声で占い師に尋ねた。
あの日アリーシアは、自分のことを騎士だと言った。自分では、心当たりがない。
だが剣を持っていたこの占い師ならば知っているはずだ。
「騎士とは、この剣を振るい魔物を倒す者のことじゃ」
「俺は、そんなことするつもりはない・・・。持って帰ってくれ」
「そうは、いかぬ。剣は、お主を選んだ」
「迷惑だ。アリーシアを殺した剣なんて・・・いらねぇよ」
「剣は、単なる道具じゃ。振るう者の意志によって善にも悪にもなる。お主、あの時何を思った。
なぜその剣を持ち娘と共に生きる道を選らなかった」
「・・・」
「望むならば剣は、お主にその力を与えただろう。
お主が死を選んだために剣は、お主を守るためにあの娘を殺さねばならなかった」
「俺が・・・悪いというのか?」
「そうじゃ」
来栖が自虐的に笑い始める。
占い師は、その痛々しい来栖の様子にも何の表情も浮かべなかった。
占い師が口を開く。
「すでに運命の輪は、回り始めている。お主は、すでにその輪の中にいるのだ」
来栖がその言葉を聞き笑いを止める。
来栖がゆっくりとゴミの山から立ち上がり落ちていた剣を取る。
「運命の輪か。輪ならアリーシアのいた所に戻ることもできるな」
来栖がしっかりとした足取りで歩き始める。天に届くように吼える。
「俺が望む力は、大切な者を守る力と運命を切り開く力、そして運命の輪が再び巡り合うまで生き抜く力だ」
剣が主の呼びかけに答えるように柄のダイアモンドが光り輝く。
「じいさん。これが俺の望む力だ。俺は、もう二度と過ちを繰り返さない。これでいいか」
「旅立つが良い。運命の輪は、東の新星を指しておる」
来栖は、その声にも振り返らずアスファルトを一歩一歩踏みしめ歩いていった。
闇の中、二つの声が響く。
一つは、氷の冷たさを持った声。
一つは、暗く重く威厳に満ちた声。
「我が主」
「わかっておる。忌々しい魔道士め。騎士を蘇らせるとは。すぐに騎士に追っ手を差し向けろ。N◎VAに行かれると厄介なことになる」
「御心のままに」
来栖は、襲いかかる魔物を倒し運命を切り開きトーキョーN◎VAにたどり着くのは、
半年後の事だった。
そしてすぐに探偵組合N・I・Kの審査に合格し新宿に探偵事務所を開いた。