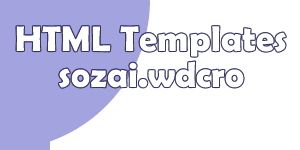Hi’z 5 Errand〜はいず 5 えらんど〜
トーキョーN◎VA-The-Detonation
小説
シーン11 カタナは、飛燕の如く紫電の如く舞う
マキシマム・揚と白耀姫の姿が中華街の人気のない裏通りに現れる。
転移が終了すると白耀姫は、握っていた手を離しすぐに表通りを目指す。
マキシマム・揚も後に続き表通りを目指す。
表通りに出た白耀姫は、顔を上げ立ち止まり厳しい表情になる。
そして隣に立ったマキシマム・揚に重々しく告げる。
「かなり不味い状況じゃ」
「そうなのか? 俺には、まったくわからん」
「人間ならばいたしかたないな。あの方向に禍々しい妖気がたちのぼっておる、」
白耀姫が南の方を指し示す。
「その方向は、虎九街の方角だな」
虎九街は、数区画に渡って放置された建築物が立ち並び迷路のようになっている地域だ。
不法入国者も多数住み着き殺人が起きても誰も気にしない違法地帯と化している。
「ふむ。では乗り込もう」
そう言うと白耀姫が虎九街に向かって歩き出す。
「少し待ってくれ」
マキシマム・揚が歩き出そうとした白耀姫の肩を掴む。
「いったいなんじゃ?」
白耀姫が肩を掴んだ手を振り払いマキシマム・揚に向き合う。
「相棒が待機している。呼ぶから少し待ってくれ」
「わかった。少し待とう。だがお主。いきなり断りもなく女性の肌に触れるでない。
無礼であろう」
「すまなかった。次から気をつける」
マキシマム・揚がまじめな顔で白耀姫に軽く頭を下げ謝る。
その様子を白耀姫が不思議そうにまじまじとマキシマム・揚の顔を見つめる。
「お主、もしかして女に甘いとよく言われぬか?」
「なぜそう思う?」
「男と話している時と態度がまったく違うからじゃ」
「そうかもな」
マキシマム・揚がポケットロンを取り出しセレス・劉の番号を押す。
二秒で会話を終えポケットロンをしまう。
「相棒は、すぐ来る。近くの屋台で待とう」
「わかった。ところで何屋じゃ」
「肉蕎麦屋。食うか? 奢るが」
「うむ。では、遠慮なくご馳走になろう」
白耀姫が遠慮なく言った。
セレス・劉が来るまでの間、白耀姫は、三杯の肉蕎麦を平らげた。
「お待たせしました。マキシ様」
暖簾をくぐりセレス・劉が現れた。
「マキシ様。この方が?」
「ああ。白虎らしい。人間にしか見えんが」
白耀姫が四杯目の肉蕎麦を平らげどんぶりを重ねた。
「うむ。美味かった」
白耀姫が満足そうにお腹をなでる。威厳がまったく感じられないその姿をセレス・劉が
不審と不安が入り混じった目で見つめる
「さて、腹ごしらえもすんだし行くか」
白耀姫は、腹ごしらえしていた時とはうって変わって厳しい表情になり立ち上がる。
「行くとはどこに?」
セレス・劉が白耀姫に尋ねる。
「虎九街じゃ。敵は、そこにおる」
白耀姫が南の方角を見据え言った。
「虎九街? 確かにこの前より怪異の存在が噂になっていますが本当に敵は、そこにいるのですか?」
「わからぬか? 道士。あの方角に禍々しい妖気がたちのぼっておる」
セレス・劉が視線を南に向ける。そして眉を寄せ険しい表情になる。
「確かに今ならばわかります。あのような禍々しい妖気を放つアヤカシがいるとは」
「古きアヤカシじゃ。かつてあの者の手によっていくつもの国が滅んだという」
「その者の名は?」
「名を蘇妲己。狡猾な狐じゃ」
「あの伝説のアヤカシですか。確かに私達では手に負えないかもしれませんね」
白耀姫の言葉にセレス・劉が厳しい表情になり考え込む。
「その蘇妲己ってのは、どんな奴だ?」
「マキシ様。本当に知らないのですか?」
マキシマム・揚の言葉にセレス・劉が驚いたようだ。
「ああ。俺は、アヤカシ関係の知識をまったく持ってない」
「わかりました。マキシ様。簡単に説明いたします。蘇妲己は、ある皇帝の妃でした。
そして皇帝をたぶらかしついには、その国を滅ぼしたそうです。その正体は、千年狐狸精。
わかりやすく言うと九尾の狐です」
「そういうことじゃ。精神を強く集中させぬとたやすく操られてしまうぞ。
何せ皇帝をたぶらかし国をいくつも滅ぼした女狐じゃ。
美貌と誘惑によって男を篭絡する術にかけてはこの世に並ぶ者はおらぬ」
白耀姫の言葉にマキシマム・揚が眉をひそめる。
顔には、不快の表情がありありと浮かんでいる。
「マキシ様? どうなさいましたか?」
マキシマム・揚の表情に気がついたセレス・劉が不安そうに尋ねた。
「大したことじゃない」
表情を戻しマキシマム・揚が立ち上がる。
「虎九街に行こう。そこに敵がいるなら倒すだけだ」
マキシマム・揚が虎九街に向う。セレス・劉と白耀姫が後に続いた。
虎九街は、重々しい空気に包まれている。
廃ビルに囲まれ昼であるのに日も差し込まず辺りは、暗い。
さながら人間を阻む魔界の入り口のようだった。
「白耀姫。敵の妖気は、何処から感じる」
「あそこじゃ」
白耀姫が遠くに見えるもっとも高いビルを指差す。
「セレス。防御は、任せる。俺は、敵を斬る事に集中する」
「わかりました。お任せください」
マキシマム・揚が先頭に立ち迷路のような虎九街を進む。
三人共無言で道を進んでいく。
ビルに近づくにつれて肌を刺すような冷気が強くなっていく。
マキシマム・揚が足を止めた。視線の先に敵の存在を見つけたからだ。
「下がっていろ」
後ろの二人に声をかけるとマキシマム・揚が立ちはだかるように一歩前に出る。
敵は、犬面と豚面の怪物がそれぞれ十匹ずつ。
どうやら不法入国者を食べているらしく不快な音を響かせしゃがみ込んでいる。
手には、錆びた剣や鉄パイプの棍棒を持っている。
こちらに気がついたのか奇声を上げ突進してくる。
マキシマム・揚が腰の後ろから二本の単分子ナイフ・スティングを抜き放つ。
豚面の怪物が鉄パイプをマキシマム・揚の頭部に向かって振り下ろす。
マキシマム・揚は、身をわずかに後方にそらし鉄パイプをかわす。
鉄パイプがアスファルトにめり込む。
マキシマム・揚が腕を飛燕の速さで振られる。
スティングが正確に豚面の怪物の頚動脈を刎ねる。
血飛沫を上げ豚面の怪物が地に倒れる。
マキシマム・揚が舞うように怪物達の攻撃をかわし次々と首を貫き頚動脈を刎ねていく。
全員倒し終わるとスティングを振りこびりついた血を払い腰の後ろの鞘に戻した。
「雑魚だな」
マキシマム・揚が怪物達の死体の中に歩を進める。
その後ろを白耀姫とセレス・劉が進む。
白耀姫が興味深そうに怪物達の顔を覗き込む。
「何かお気づきのことがおありですか?」
隣を歩いていたセレス・劉が白耀姫の様子に気がつき声をかける。
「こやつら私には、まったく見覚えがない連中だ」
「つまり中国のアヤカシではない」
「その通りじゃ。もし中国のアヤカシならば私にはわかるはずじゃ」
「では蘇妲己に力を貸している別のアヤカシがいるというわけですか」
「そうかもしれぬが何とも言えぬな」
顎を撫でながら白耀姫が答える。
「気にしても仕方が無い。蘇妲己に力を貸しているならば倒せばこやつ等も逃げ去るじゃろう」
マキシマム・揚が先頭を歩きながら口を挟む。
「その意見に賛成だ。頭を潰せば俺達の勝ちだ」
セレス・劉がマキシマム・揚の意見に頷き白耀姫が顎を撫でる。
「ところで時間にどのくらい余裕がある?」
白耀姫が聳える高いビルを見る。そして眉をしかめる。
「ふむ。あの禍々しい妖気から見るとさほど余裕はない。完全復活しておるようじゃ。
中華街に影響が出るまでまもなくといったところじゃ」
セレス・劉が落ち着いた声で尋ねる。
「影響というと?」
「奴の色香に惑わされる。中華街の全ての人間は、奴の思い通りに操られるじゃろうな」
マキシマム・揚が嫌悪感を露にし舌打ちする。そして気がついたように白耀姫を見る。
「お前は、どうやって蘇妲己に勝つつもりだ? 見たところ素手のようだが」
「簡単じゃ。殴り倒すだけじゃ。さすれば天に張られた結界が奴の魂をとらえ封神するのじゃ」
「功夫でも学んでいるのか?」
「内功の方じゃ。知ってのとおり私は、西海の守護者にして白虎一族の戦姫じゃ。
気の力は、人間を遥かに凌ぐ。そうじゃな。神気を操るといえばわかりやすいか」
白耀姫が自慢するように胸を張った。
功夫の流派は、大まかに分けると内功と外功の二つに分かれる。
内功は、呼吸や経絡を鍛え上げ体に流れる気を操り拳や蹴り等に気を宿し人体を内部より破壊する。
外功は、己の身体能力を鍛え上げこれを基に技を組み上げ人体を外部より破壊する。
「それにしてもアヤカシの世界も人間の世界と変わらんな。最後は、武力か」
マキシマム・揚があきれたように首を振った。
「まったくその通りじゃ」
白耀姫が腕を組み納得したように何度も頷く。セレス・劉がその様子を見て小さく笑う。
「おしゃべりは、ここまでのようだ」
マキシマム・揚が足を止める。目の前には、高く聳えるビルがある。
そして入り口の前には、立ちふさがるように布陣する鎧武者の一団がいた。
およそ五十名。前列、中列、後列の三列に並び槍を構え戦闘態勢を取っている。
「セレス。白耀姫。俺が突破口を開く。突破口が開いたら俺に構わず入り口に突っ込め。いいな」
マキシマム・揚が二本のスティングを抜き放ち両手をぶらりと垂れ下げる。
(高速振動ブレード・スラッシャー展開)
両手の前腕よりスラッシャーが飛び出る。
マキシム・揚が駆ける。そしてIANUSに命じて戦闘用サイバーウェアを起動する。
(スリーアクション起動。思考トリガーON:タイプD・コンバットリンク起動)
(神経加速タイプD起動準備:二秒後に起動)
タイプDの起動によりマキシマム・揚の反応速度が爆発的に上昇する。
(コンバットリンク起動。ウェブアクセス。ブックマークよりデータダウンロード。
フルメタル・カンフー・種別・外功をアップデート)
「No time for losers」
マキシマム・揚が呟く。
(キーワード確認。ガルーダ起動)
無意識に刷り込まれた暗示によりマキシマム・揚の潜在能力が解放される。
突進してくるマキシマム・揚に向かって四人の鎧武者が立ちはだかり槍を突き出す。
マキシマム・揚は、槍が体に届く寸前に空中に飛ぶ。
そして一気に鎧武者の懐へ入り込む。
スティングを鳥が羽ばたくように振り同時に真ん中二人の首を斬る。
左右の腕を一旦引き前腕のスラッシャーを外側二人の首に突き刺す。
そのままマキシマム・揚が前列に切り込む。
鎧武者がマキシマム揚を包囲し次々と槍が突き出す。
槍を払い身をかわしマキシマム・揚は、鎧武者の懐に飛び込んでいく。
マキシマム・揚の剣が振るわれるたび赤い血飛沫が舞い鎧武者がアスファルトに倒れる。
マキシマム・揚が前列を壊滅させ中列が姿を現す。
むやみに突進せずに槍衾を並べマキシマム・揚が斬りこんでくるを待ち受けている。
マキシマム・揚も足を止め鎧武者達と対峙する。
前列の二十名の鎧武者を斬り殺したにも関わらずマキシマム・揚の息は、いささかも乱れていない。
「突っ込んでこないか。賢明だな」
槍は、その長さによって先手をとれるが懐に入られた場合は、その長さが仇となり成す術を失う。
そのため中列は、槍衾を並べマキシマム・揚の突進を阻み懐に入られないようにしたのだ。
マキシマム・揚が天を仰ぐ。
空は、厚い雲に覆い隠されている。
マキシマム・揚が右腕を天に掲げ振り下ろす。
「雷公鞭」
マキシマム・揚の声に答えるように天が轟く。そして地に向かい光の鞭を振り下ろした。
青い雷が鎧武者達を打ち据える。数十万ボルトの雷撃が鎧武者達を蒸発させていく。
鎧武者達を全て消滅させマキシマム・揚が悠然とビルの入り口まで歩を進める。
そこには、陣椅子に座る侍がいた。今までの鎧武者とは、雰囲気がまるで違う。
飛竜の飾りがついた兜。顔を覆う黒漆塗りの面貌。
赤糸通しの鎧に腰に大太刀を刷いたその姿は、正に威風堂々たるものだった。
侍が腰を上げ静かに大太刀を抜く。波模様のような美しい刃紋を持った刀身が現れる。
同時に凄まじい殺気がマキシマム・揚に向かって放射される。
このような殺気を放つ相手は、マキシマム・揚の今まで戦った相手の中でもそうはいない。
カタナの本能が告げる。強敵だと。命を賭け全力で戦わねば殺される相手だと。
「セレス、白耀姫。俺は、こいつの相手をする。先に行け」
言うが早いかマキシマム・揚が侍に向かって駆ける。
右手に握られたスティングが首を、左手に握られたスティングが心臓を狙い振るわれる。
侍は、心臓を狙うスティングを大太刀で払い首を狙うスティングを受け止めるとそのまま全身の力で押し返そうとする。
マキシマム・揚も力をこめ鍔迫り合いに持ち込む。
「行け!」
一瞬だけ振り返り後ろの二人を急かす。
侍が二人を阻むためマキシマム・揚を押しのけようと力を込める。
マキシマム・揚が左手のスティングも大太刀に合わせ侍の力を受け止める。
「わかりました。マキシ様。先に行きます」
「先に行っておる。後から必ず来るのじゃぞ」
セレス・劉と白耀姫がマキシマム・揚の背後を通り過ぎていく。
マキシマム・揚は、二人がすれ違う瞬間に言った。。
「一角獣は、乙女との約束を破らない。安心しろ」
二人の足音がどんどん遠ざかっていく。
足音が聞こえなくなるまでマキシマム・揚と侍の鍔迫り合いは続いた。
侍の力にマキシマム・揚が押され始める。
このままでは、力負けすると判断したマキシマム・揚は、侍の膝を砕くため蹴りを放つ。
侍が刀に力を込め蹴りを放って不安定な体勢になったマキシマム・揚を跳ね除ける。
マキシマム・揚が跳ね飛ばされたがすぐさま体勢を立て直し間合いを取る。
「名を聞こう」
侍が張りのある低い声で言った。大太刀は、油断無く青眼に構えている。
「夏王朝禁軍武術師範、マキシマム・揚だ」
マキシマム・揚が両手を下げた構えに戻る。
「名乗り見事。わしの名は、将軍家指南役、ミフネ」
マキシマム・揚が眉をひそめる。
「将軍家指南役? まさか日本人か?」
災厄後日本は、鎖国し日本本土の情報は、一切伝わることはない。
噂では、天皇を上位とした階級性の社会になっているという。
将軍もいるという噂もまことしやかに流れている。
「わしは、ここで無い世界の住人。主命により参上した」
「お前もアヤカシってわけか」
「左様。思う存分かかってこられよ。我も武技の粋を尽くしお相手いたそう」
「望むところだ」
マキシマム・揚とミフネの間に緊張感に満ちた空気が張り詰める。
「本気で行く」
声に合わせマキシマム・揚の握るスティングと左右前腕のスラッシャーが紫電を纏う。
マキシマム・揚が一気に間合いを詰める。
ミフネは、山の如く微動だにせずマキシマム・揚の剣を待ち受ける。
マキシマム・揚の握る長短合わせて四本の剣が飛燕の如き速さでミフネに向かって駆ける。
四本の剣が空に舞う燕のごとく奔放に軌道を変え縦横無尽にミフネに襲いかかる。
マキシマム・揚の剣が空を自由に舞う飛燕ならばミフネの大太刀は、獲物を正確に捉える鷹のようだった。
マキシマム・揚の剣をミフネの大太刀は、正確に捕え全て打ち払う。
四本の剣と大太刀が触れ合うたびに火花が散る。
「くっ」
マキシマム・揚の表情に焦りが見え始める。
今までミフネに打ち込んだ剣の回数は、すでに数え切れない。
更に完璧に自分の意を消して振るわれている剣の全てがミフネの体に触れることなく
大太刀に打ち払われる。それがマキシマム・揚の焦らせる原因だ。
マキシマム・揚の剣が今までにない強さで払われる。
マキシマム・揚の右腕が外に伸び体勢が崩れる。
ミフネが隙を見逃さずに裂帛の気合とともに袈裟掛けに斬りつける。
「ちぃっ」
マキシマム・揚が左腕前腕のスラッシャーで刀を受け止める。
火花が散りと鈴のような澄んだ音が響く。
スラッシャーの刀身がアスファルトに落ちる。
マキシマム・揚が後方に飛び間合いを取る。
そして左腕の斬られたスラッシャーの断面を見る。
断面は、鏡のように滑らかだった。
それは、恐ろしいほどの大太刀の切れ味とミフネの腕の確かさを示していた。
「化け物め。スラッシャーを斬るなんてな」
高速振動ブレードであるスラッシャーは、通常ならば触れ合った物を振動で速やかに切断する。
それを逆に斬るなどいうのは、もはや神技に等しい。
「まずお主の剣の一本をいただいた。わしの刀、雪月花に斬れぬ物はない」
ミフネが大太刀を肩に担ぐように構える。
「次は、お主の命をいただく!」
ミフネが疾風の如く駆ける。
「なめるなっ!」
マキシマム・揚も駆け出す。ミフネの大太刀が美しい弧を描き振り下ろされる。
マキシマム・揚が右腕前腕のスラッシャーをかざしミフネの大太刀を受け止める。
再びスラッシャーがミフネの大太刀によって刀身を斬られる。
「二本目、いただいた!」
「これ以上させるかよっ!」
マキシマム・揚が残った左右二本のスティングを振るう。
速度は、変わらないが先ほどと違い二本の剣を失ったことにより軌道の変化が単純に
なっている。ミフネが即座に軌道の変化を読み大太刀で打ち払う。
マキシマム・揚も読まれぬように戻した腕を次に振るわずかな間に手品のように
スティングを順手から逆手に持ち替え振るタイミング、軌道を変化させる。
それでもミフネは、山のように微動だにせずスティングを打ち払い続ける。
マキシマム・揚の体が独楽のように回転する。
ミフネの足を払い体勢を崩すため右下段回し蹴りを放つ。
ミフネが宙に飛び下段回し蹴りをかわし大太刀を上段に振り上げる。
雪崩のような勢いでマキシマム・揚に太刀が振り下ろされる。
マキシマム・揚がミフネの太大刀を二本のスティングを十字に重ね合わせ受け止める。
マキシマム・揚の目の前で火花が散る。
ミフネの全体重が乗った衝撃を支えきれずマキシマム・揚が右膝をつく。
マキシマム・揚がついた右膝を軸に左足を伸ばし水面蹴りでミフネの足を刈る。
山のように微動しなかったミフネが体勢を崩す。
ミフネの体勢が崩れたのに合わせマキシマム・揚がアスファルトを転がり間合いを取る。
マキシマム・揚が立ち上がる。汗が雫となってアスファルトに落ちる。
「四本、いただいた」
ミフネが低い声で言った。
マキシマム・揚が握っているスティングに目をやり舌打ちする。
スティングの刀身は、折られておらずまだ存在する。
しかし刃が所々砕かれ鮫の歯のような姿になっている。
マキシマム・揚がスティングをアスファルトの投げ捨てる。
「わかったぜ。あんたの大太刀の正体が」
「ほう?」
「高速振動剣を断ち切り単分子ナイフの刃を砕く化け物じみた切れ味に刃毀れしない
その硬度。思い当たるのはただ一つ。ダマスカス鋼を使った大太刀だろう」
ダマスカス鋼とは、古の時代に作り出された鋼であり現在でもその製法は、解明されていない伝説の鋼だ。
この鋼を使った剣は、鉄鎧を紙のように両断し刃毀れすることはないという。
そして刀身には、美しい波模様が表れるという。マキシマム・揚の言葉にミフネが頷く。
「いかにも。わしの刀、雪月花の刀身は、ダマスカス鋼でできておる」
ミフネが雪月花の刀身を指でなぞる。
「だがそれがわかったとてどうする? 禁軍武術師範!」
「武器が何で作られているかわかれば対処のしようもある」
マキシマム・揚が両腕を振る。
ジャケットの袖に隠してあった単分子ワイヤー・スネイクの柄が手に滑り落ちてくる。
「刀身は、叩き斬られ刃は、砕かれる」
言葉と共に二本のスネイクが風を切って飛ぶ。
「ならばこのしなやかなワイヤーならばどうする? ミフネ!」
「むう」
ミフネが唸り大太刀を振るいスネイクを弾き返す。
その隙にもう一方のスネイクが別方向より迫る。
ミフネが後退しスネイクをかわす。
鞭であるスネイクは、ミフネの大太刀が振るう速度を上回り鞭特有のしなやかさのおかげで大太刀の切れ味によって切断されることも無い。
ミフネの身を捕えることは無いが攻防の主導権は、マキシマム・揚が握った。
マキシマム・揚が決着をつけるべく勝負に出た。
二本のスネイクと大太刀が激突する瞬間にマキシマム・揚が手首を返す。
スネイクが大太刀の刀身に蛇のように巻きつき大太刀の動きを封じる。
「もらった! 奔れ、雷!」
声とともにマキシマム・揚の周囲の空気が帯電し耳障りな音を発する。
マキシマム・揚の赤い髪が怒りを表すように逆立つ。
マキシマム・揚の腕から紫電が放たれる。紫電がスネイクを通してミフネに向かう。
青い閃光がミフネを包む。ミフネが苦痛のうめきを上げる。
マキシマム・揚が勝利を確信したように薄く笑う。
ミフネが大太刀の切っ先をアスファルトに突き刺す。
紫電が大太刀を伝わりアスファルトに流れる。
マキシマム・揚が舌打ちすると紫電を放つのを止める。
その瞬間を待ちかねていたようにミフネが太刀の切っ先をひねりそのままアスファルトに
向かって大太刀を倒す。
アスファルトと大太刀に挟まれ刀身に巻きついていたスネイクが切断される。
「これで全ていただいた。まだ戦うか?」
ミフネが大太刀を鞘に収め低い声で告げる。
マキシマム・揚が握っていたスネイクの柄を離す。
渇いた音と共にスネイクがアスファルトに落ちる。
そしてマキシマム・揚がくぐもった声で笑いを漏らす。
「何がおかしい?」
ミフネの声にマキシマム・揚が笑いを止め顔を上げる
「まだ戦うかだと? 当然だ」
「武器を全て破壊されてもまだ戦うと?」
ミフネが戸惑った声で言った。
「侍のあんたに教えてやろう。刀は、侍の魂らしいが俺は違う。武器は全て手の延長だ。故に俺の武器は、ここにある」
マキシマム・揚が拳を胸の前に掲げる。
「指が一本でも動くかぎり俺は、戦い続ける。俺の武器を全て砕きたければ」
マキシマム・揚が自分の心臓を指差す。
「俺の魂を砕いてみせろ」
ミフネが天を仰ぎ愉快そうに声を上げ大笑する。
「その覚悟、見事。我が奥義を持ってその魂を砕こう」
ミフネが腰を落とし大太刀の柄に手を添える。
マキシマム・揚に向かって叩きつけていた殺気が林の如く静かになっていく。
マキシマム・揚が拳を握りその手に紫電を宿す。
二人の間の空気が凍りついていく。ミフネがじりじりとすり足で間合いを詰めていく。
マキシマム・揚は、自分がミフネの一足一刀の間合いにを入るのを待っている。
一足一刀の間合いとは、一歩踏み込めば相手に致死の斬撃を叩き込める間合いのことだ。
当然、大太刀を持っているミフネの方が間合いは広い。
マキシマム・揚は、ミフネが大太刀を振るより早く一撃を叩き込むつもりで待ち構えている。
ミフネの一刀一足の間合いにマキシマム・揚が入る。
同時にマキシマム・揚が電光石火の速さで駆ける。
ミフネは、まだ大太刀の柄に手を添えたままだ。
マキシマム・揚がミフネに向かって拳を放つ。
次の瞬間、マキシマム・揚の体に衝撃が突き抜け後ろに吹っ飛ばされる。
マキシマム・揚が最後に見たミフネの姿は、大太刀に手を添えた姿だった。
大太刀を抜く瞬間を目撃していない。その姿だけがぽっかりと抜け落ちている。
マキシマム・揚がアスファルトを転がりそのまま倒れ伏したまま動かない。
マキシマム・揚の様子を見てミフネがようやく構えを解く。
ミフネがマキシマム・揚に背を向け先にビルに入っていった二人を追いかけるべく入り口に向かって歩み始める。
「痛ぇ」
小さな声だった。ミフネが足を止め振り返る。
そこには、ゆっくりと立ち上がるマキシマム・揚の姿があった。
何度か咳き込み不味そうに血をアスファルトに吐き捨てる。
胸から腹にかけて斬ったことを示すように斜めに服が切れている。
大太刀の切れ味を示すかのように着込んでいた鎖帷子が裂けその下のマキシマム・揚の皮膚に下から上に向かって
斜めに赤い線が刻まれ血が流れ出している。
マキシマム・揚がわき腹に手をやり苦痛に顔を歪める。
衝撃で肋骨も何本か折られているようだ。
「俺が踏み込んだ分だけ浅かったな。ミフネ、もう一度だ」
マキシマム・揚が挑発するようにくいくいと指を曲げて手招きする。
「切り結ぶ刃の下ぞ地獄なれ、身を捨てて浮かぶ瀬もあれ、か」
ミフネが面白そうに呟き低く笑う。ミフネが腰を落とし大太刀の柄に手を添える。
マキシマム・揚は、構えず手を下げる。いつもの剣を振る時の構えだ。
ミフネがすり足でじりじりと間合いを詰め始める。
「最後にもう一度だけ聞いておこう。まだ戦うか?」
マキシマム・揚が精神を集中するように瞑目する。
「俺は、カタナだ。戦い始めた以上どちらかが死ぬまで戦う」
マキシマム・揚が閉じていた瞳を開ける。
開いた瞳にも表情にも何の感情も無かった。
その顔は、悟りを開いた高僧のように落ちつき静かだった。
ミフネがマキシマム・揚を一刀一足の間合いに捕える。
ミフネの右手が大太刀の柄を握り鯉口を切る。
マキシマム・揚は、電光石火の動きで踏み込む。
ミフネの大太刀が鞘走り加速し抜き放たれる。
マキシマム・揚の耳に大太刀の風切り音が入ってくる。
ミフネの大太刀がマキシマム・揚の命を砕くべく迫る。
マキシマム・揚の右足が力強くアスファルトを蹴る。
ミフネの大太刀がマキシマム・揚の皮膚に触れる。
マキシマム・揚の右足が紫電を纏い駆け上がる。
大太刀の鋭い刃がマキシマム・揚の皮膚に食い込み始める。
ミフネの首元から落雷のような打撃音が響きわたる。
ゆっくりとミフネが膝からアスファルトに崩れ落ちる。
マキシマム・揚が右足をアスファルトに下ろす。
全ては、二秒にも満たない刹那の瞬間の出来事。
「見事」
ミフネが呟き大太刀を鞘に戻しアスファルトに正座する。
マキシマム・揚もアスファルトに倒れるようにどっかと腰を下ろす。
そして行儀悪く胡座を組む。
「何故、奥義を破ることができた?」
「最初に食らった時、あんたが大太刀を抜く姿だけが見えなかった。それで気がついた。
全ての動作を無駄なく高速無比に行う居合い抜きだと。俺の兄弟子にも神業のような
居合いの使い手がいるからな」
マキシマム・揚が勝ち誇るでもなく淡々と告げる。
「勝ったのは・・・運がよかっただけだ」
「ほう」
「何も考えずにただ無我夢中で蹴りを出しただけだ。
それが一瞬速くあんたに当たっただけだ」
ミフネが面白そうに笑う。しばらく笑うと大太刀を腰から外しマキシマム・揚に差し出す。
怪訝な顔でマキシマム・揚が差し出された大太刀を見つめる。
「この刀でわしの首を取り後世の誉れにするがいい。お主の勝ちだ」
ミフネが一点の曇りも無い晴れ晴れとした声で言った。
マキシマム・揚が大太刀を受け取り立ち上がりミフネの後ろに回る。
大太刀を抜き放ち上段に構え振り下ろす。
大太刀は、ミフネの首の寸前で止まる。
「たまたま運良く一回勝っただけだ。首まで貰うほど価値があるもんじゃない」
マキシマム・揚が大太刀を鞘に戻す。
「どちらかが死ぬまで戦うと言ったのはお主だ。よもや二言があるとは言うまい」
ミフネが振り返り厳しい声で追求する。
「魂なら貰った。この大太刀だ」
マキシマム・揚が重そうに大太刀を肩に担ぐ。。
「刀は、武士の魂。それを差し出したってことは、命を貰ったってことだ。
それに一回の勝ちで二つの物を貰うのは俺の主義じゃない」
マキシマム・揚がにやりと笑う。
「武士としてのあんたは死んだ。文句は無い筈だ」
ミフネが小さな声で笑う。それは次第に大きな笑いになった。
「見事。なればその刀、お主に預けておこう。いずれまた貰い受けにくる」
ミフネの姿が風景に溶け込むように消えていく。
「次は、実力で勝ってあんたの首を貰うさ」
マキシマム・揚が力強く言い放つ。
ミフネの姿が消え去るとその場に力尽きたようにがっくりと片膝をつく。
「ちっ。無理しすぎたか」
IANUSが体の異常を感じ取り全て戦闘用サイバーウェアを強制終了させる。
そしてIANUSが体の異常を告げるワーニングをがなりたてる。
痛みが焼かれるように熱さで自己主張し鉛のような疲労感が体を押し潰そうとする。
「一角獣は、乙女との約束を破らないか・・・」
マキシマム・揚が自分に言い聞かせるように呟くと大太刀を杖のように突き立ち上がった。
シーン10 LORD OF GARD〜あなたこそ守るべき我が君主なり〜に戻る
シーン12 Order Of Kight〜騎士の使命〜に進む
転移が終了すると白耀姫は、握っていた手を離しすぐに表通りを目指す。
マキシマム・揚も後に続き表通りを目指す。
表通りに出た白耀姫は、顔を上げ立ち止まり厳しい表情になる。
そして隣に立ったマキシマム・揚に重々しく告げる。
「かなり不味い状況じゃ」
「そうなのか? 俺には、まったくわからん」
「人間ならばいたしかたないな。あの方向に禍々しい妖気がたちのぼっておる、」
白耀姫が南の方を指し示す。
「その方向は、虎九街の方角だな」
虎九街は、数区画に渡って放置された建築物が立ち並び迷路のようになっている地域だ。
不法入国者も多数住み着き殺人が起きても誰も気にしない違法地帯と化している。
「ふむ。では乗り込もう」
そう言うと白耀姫が虎九街に向かって歩き出す。
「少し待ってくれ」
マキシマム・揚が歩き出そうとした白耀姫の肩を掴む。
「いったいなんじゃ?」
白耀姫が肩を掴んだ手を振り払いマキシマム・揚に向き合う。
「相棒が待機している。呼ぶから少し待ってくれ」
「わかった。少し待とう。だがお主。いきなり断りもなく女性の肌に触れるでない。
無礼であろう」
「すまなかった。次から気をつける」
マキシマム・揚がまじめな顔で白耀姫に軽く頭を下げ謝る。
その様子を白耀姫が不思議そうにまじまじとマキシマム・揚の顔を見つめる。
「お主、もしかして女に甘いとよく言われぬか?」
「なぜそう思う?」
「男と話している時と態度がまったく違うからじゃ」
「そうかもな」
マキシマム・揚がポケットロンを取り出しセレス・劉の番号を押す。
二秒で会話を終えポケットロンをしまう。
「相棒は、すぐ来る。近くの屋台で待とう」
「わかった。ところで何屋じゃ」
「肉蕎麦屋。食うか? 奢るが」
「うむ。では、遠慮なくご馳走になろう」
白耀姫が遠慮なく言った。
セレス・劉が来るまでの間、白耀姫は、三杯の肉蕎麦を平らげた。
「お待たせしました。マキシ様」
暖簾をくぐりセレス・劉が現れた。
「マキシ様。この方が?」
「ああ。白虎らしい。人間にしか見えんが」
白耀姫が四杯目の肉蕎麦を平らげどんぶりを重ねた。
「うむ。美味かった」
白耀姫が満足そうにお腹をなでる。威厳がまったく感じられないその姿をセレス・劉が
不審と不安が入り混じった目で見つめる
「さて、腹ごしらえもすんだし行くか」
白耀姫は、腹ごしらえしていた時とはうって変わって厳しい表情になり立ち上がる。
「行くとはどこに?」
セレス・劉が白耀姫に尋ねる。
「虎九街じゃ。敵は、そこにおる」
白耀姫が南の方角を見据え言った。
「虎九街? 確かにこの前より怪異の存在が噂になっていますが本当に敵は、そこにいるのですか?」
「わからぬか? 道士。あの方角に禍々しい妖気がたちのぼっておる」
セレス・劉が視線を南に向ける。そして眉を寄せ険しい表情になる。
「確かに今ならばわかります。あのような禍々しい妖気を放つアヤカシがいるとは」
「古きアヤカシじゃ。かつてあの者の手によっていくつもの国が滅んだという」
「その者の名は?」
「名を蘇妲己。狡猾な狐じゃ」
「あの伝説のアヤカシですか。確かに私達では手に負えないかもしれませんね」
白耀姫の言葉にセレス・劉が厳しい表情になり考え込む。
「その蘇妲己ってのは、どんな奴だ?」
「マキシ様。本当に知らないのですか?」
マキシマム・揚の言葉にセレス・劉が驚いたようだ。
「ああ。俺は、アヤカシ関係の知識をまったく持ってない」
「わかりました。マキシ様。簡単に説明いたします。蘇妲己は、ある皇帝の妃でした。
そして皇帝をたぶらかしついには、その国を滅ぼしたそうです。その正体は、千年狐狸精。
わかりやすく言うと九尾の狐です」
「そういうことじゃ。精神を強く集中させぬとたやすく操られてしまうぞ。
何せ皇帝をたぶらかし国をいくつも滅ぼした女狐じゃ。
美貌と誘惑によって男を篭絡する術にかけてはこの世に並ぶ者はおらぬ」
白耀姫の言葉にマキシマム・揚が眉をひそめる。
顔には、不快の表情がありありと浮かんでいる。
「マキシ様? どうなさいましたか?」
マキシマム・揚の表情に気がついたセレス・劉が不安そうに尋ねた。
「大したことじゃない」
表情を戻しマキシマム・揚が立ち上がる。
「虎九街に行こう。そこに敵がいるなら倒すだけだ」
マキシマム・揚が虎九街に向う。セレス・劉と白耀姫が後に続いた。
虎九街は、重々しい空気に包まれている。
廃ビルに囲まれ昼であるのに日も差し込まず辺りは、暗い。
さながら人間を阻む魔界の入り口のようだった。
「白耀姫。敵の妖気は、何処から感じる」
「あそこじゃ」
白耀姫が遠くに見えるもっとも高いビルを指差す。
「セレス。防御は、任せる。俺は、敵を斬る事に集中する」
「わかりました。お任せください」
マキシマム・揚が先頭に立ち迷路のような虎九街を進む。
三人共無言で道を進んでいく。
ビルに近づくにつれて肌を刺すような冷気が強くなっていく。
マキシマム・揚が足を止めた。視線の先に敵の存在を見つけたからだ。
「下がっていろ」
後ろの二人に声をかけるとマキシマム・揚が立ちはだかるように一歩前に出る。
敵は、犬面と豚面の怪物がそれぞれ十匹ずつ。
どうやら不法入国者を食べているらしく不快な音を響かせしゃがみ込んでいる。
手には、錆びた剣や鉄パイプの棍棒を持っている。
こちらに気がついたのか奇声を上げ突進してくる。
マキシマム・揚が腰の後ろから二本の単分子ナイフ・スティングを抜き放つ。
豚面の怪物が鉄パイプをマキシマム・揚の頭部に向かって振り下ろす。
マキシマム・揚は、身をわずかに後方にそらし鉄パイプをかわす。
鉄パイプがアスファルトにめり込む。
マキシマム・揚が腕を飛燕の速さで振られる。
スティングが正確に豚面の怪物の頚動脈を刎ねる。
血飛沫を上げ豚面の怪物が地に倒れる。
マキシマム・揚が舞うように怪物達の攻撃をかわし次々と首を貫き頚動脈を刎ねていく。
全員倒し終わるとスティングを振りこびりついた血を払い腰の後ろの鞘に戻した。
「雑魚だな」
マキシマム・揚が怪物達の死体の中に歩を進める。
その後ろを白耀姫とセレス・劉が進む。
白耀姫が興味深そうに怪物達の顔を覗き込む。
「何かお気づきのことがおありですか?」
隣を歩いていたセレス・劉が白耀姫の様子に気がつき声をかける。
「こやつら私には、まったく見覚えがない連中だ」
「つまり中国のアヤカシではない」
「その通りじゃ。もし中国のアヤカシならば私にはわかるはずじゃ」
「では蘇妲己に力を貸している別のアヤカシがいるというわけですか」
「そうかもしれぬが何とも言えぬな」
顎を撫でながら白耀姫が答える。
「気にしても仕方が無い。蘇妲己に力を貸しているならば倒せばこやつ等も逃げ去るじゃろう」
マキシマム・揚が先頭を歩きながら口を挟む。
「その意見に賛成だ。頭を潰せば俺達の勝ちだ」
セレス・劉がマキシマム・揚の意見に頷き白耀姫が顎を撫でる。
「ところで時間にどのくらい余裕がある?」
白耀姫が聳える高いビルを見る。そして眉をしかめる。
「ふむ。あの禍々しい妖気から見るとさほど余裕はない。完全復活しておるようじゃ。
中華街に影響が出るまでまもなくといったところじゃ」
セレス・劉が落ち着いた声で尋ねる。
「影響というと?」
「奴の色香に惑わされる。中華街の全ての人間は、奴の思い通りに操られるじゃろうな」
マキシマム・揚が嫌悪感を露にし舌打ちする。そして気がついたように白耀姫を見る。
「お前は、どうやって蘇妲己に勝つつもりだ? 見たところ素手のようだが」
「簡単じゃ。殴り倒すだけじゃ。さすれば天に張られた結界が奴の魂をとらえ封神するのじゃ」
「功夫でも学んでいるのか?」
「内功の方じゃ。知ってのとおり私は、西海の守護者にして白虎一族の戦姫じゃ。
気の力は、人間を遥かに凌ぐ。そうじゃな。神気を操るといえばわかりやすいか」
白耀姫が自慢するように胸を張った。
功夫の流派は、大まかに分けると内功と外功の二つに分かれる。
内功は、呼吸や経絡を鍛え上げ体に流れる気を操り拳や蹴り等に気を宿し人体を内部より破壊する。
外功は、己の身体能力を鍛え上げこれを基に技を組み上げ人体を外部より破壊する。
「それにしてもアヤカシの世界も人間の世界と変わらんな。最後は、武力か」
マキシマム・揚があきれたように首を振った。
「まったくその通りじゃ」
白耀姫が腕を組み納得したように何度も頷く。セレス・劉がその様子を見て小さく笑う。
「おしゃべりは、ここまでのようだ」
マキシマム・揚が足を止める。目の前には、高く聳えるビルがある。
そして入り口の前には、立ちふさがるように布陣する鎧武者の一団がいた。
およそ五十名。前列、中列、後列の三列に並び槍を構え戦闘態勢を取っている。
「セレス。白耀姫。俺が突破口を開く。突破口が開いたら俺に構わず入り口に突っ込め。いいな」
マキシマム・揚が二本のスティングを抜き放ち両手をぶらりと垂れ下げる。
(高速振動ブレード・スラッシャー展開)
両手の前腕よりスラッシャーが飛び出る。
マキシム・揚が駆ける。そしてIANUSに命じて戦闘用サイバーウェアを起動する。
(スリーアクション起動。思考トリガーON:タイプD・コンバットリンク起動)
(神経加速タイプD起動準備:二秒後に起動)
タイプDの起動によりマキシマム・揚の反応速度が爆発的に上昇する。
(コンバットリンク起動。ウェブアクセス。ブックマークよりデータダウンロード。
フルメタル・カンフー・種別・外功をアップデート)
「No time for losers」
マキシマム・揚が呟く。
(キーワード確認。ガルーダ起動)
無意識に刷り込まれた暗示によりマキシマム・揚の潜在能力が解放される。
突進してくるマキシマム・揚に向かって四人の鎧武者が立ちはだかり槍を突き出す。
マキシマム・揚は、槍が体に届く寸前に空中に飛ぶ。
そして一気に鎧武者の懐へ入り込む。
スティングを鳥が羽ばたくように振り同時に真ん中二人の首を斬る。
左右の腕を一旦引き前腕のスラッシャーを外側二人の首に突き刺す。
そのままマキシマム・揚が前列に切り込む。
鎧武者がマキシマム揚を包囲し次々と槍が突き出す。
槍を払い身をかわしマキシマム・揚は、鎧武者の懐に飛び込んでいく。
マキシマム・揚の剣が振るわれるたび赤い血飛沫が舞い鎧武者がアスファルトに倒れる。
マキシマム・揚が前列を壊滅させ中列が姿を現す。
むやみに突進せずに槍衾を並べマキシマム・揚が斬りこんでくるを待ち受けている。
マキシマム・揚も足を止め鎧武者達と対峙する。
前列の二十名の鎧武者を斬り殺したにも関わらずマキシマム・揚の息は、いささかも乱れていない。
「突っ込んでこないか。賢明だな」
槍は、その長さによって先手をとれるが懐に入られた場合は、その長さが仇となり成す術を失う。
そのため中列は、槍衾を並べマキシマム・揚の突進を阻み懐に入られないようにしたのだ。
マキシマム・揚が天を仰ぐ。
空は、厚い雲に覆い隠されている。
マキシマム・揚が右腕を天に掲げ振り下ろす。
「雷公鞭」
マキシマム・揚の声に答えるように天が轟く。そして地に向かい光の鞭を振り下ろした。
青い雷が鎧武者達を打ち据える。数十万ボルトの雷撃が鎧武者達を蒸発させていく。
鎧武者達を全て消滅させマキシマム・揚が悠然とビルの入り口まで歩を進める。
そこには、陣椅子に座る侍がいた。今までの鎧武者とは、雰囲気がまるで違う。
飛竜の飾りがついた兜。顔を覆う黒漆塗りの面貌。
赤糸通しの鎧に腰に大太刀を刷いたその姿は、正に威風堂々たるものだった。
侍が腰を上げ静かに大太刀を抜く。波模様のような美しい刃紋を持った刀身が現れる。
同時に凄まじい殺気がマキシマム・揚に向かって放射される。
このような殺気を放つ相手は、マキシマム・揚の今まで戦った相手の中でもそうはいない。
カタナの本能が告げる。強敵だと。命を賭け全力で戦わねば殺される相手だと。
「セレス、白耀姫。俺は、こいつの相手をする。先に行け」
言うが早いかマキシマム・揚が侍に向かって駆ける。
右手に握られたスティングが首を、左手に握られたスティングが心臓を狙い振るわれる。
侍は、心臓を狙うスティングを大太刀で払い首を狙うスティングを受け止めるとそのまま全身の力で押し返そうとする。
マキシマム・揚も力をこめ鍔迫り合いに持ち込む。
「行け!」
一瞬だけ振り返り後ろの二人を急かす。
侍が二人を阻むためマキシマム・揚を押しのけようと力を込める。
マキシマム・揚が左手のスティングも大太刀に合わせ侍の力を受け止める。
「わかりました。マキシ様。先に行きます」
「先に行っておる。後から必ず来るのじゃぞ」
セレス・劉と白耀姫がマキシマム・揚の背後を通り過ぎていく。
マキシマム・揚は、二人がすれ違う瞬間に言った。。
「一角獣は、乙女との約束を破らない。安心しろ」
二人の足音がどんどん遠ざかっていく。
足音が聞こえなくなるまでマキシマム・揚と侍の鍔迫り合いは続いた。
侍の力にマキシマム・揚が押され始める。
このままでは、力負けすると判断したマキシマム・揚は、侍の膝を砕くため蹴りを放つ。
侍が刀に力を込め蹴りを放って不安定な体勢になったマキシマム・揚を跳ね除ける。
マキシマム・揚が跳ね飛ばされたがすぐさま体勢を立て直し間合いを取る。
「名を聞こう」
侍が張りのある低い声で言った。大太刀は、油断無く青眼に構えている。
「夏王朝禁軍武術師範、マキシマム・揚だ」
マキシマム・揚が両手を下げた構えに戻る。
「名乗り見事。わしの名は、将軍家指南役、ミフネ」
マキシマム・揚が眉をひそめる。
「将軍家指南役? まさか日本人か?」
災厄後日本は、鎖国し日本本土の情報は、一切伝わることはない。
噂では、天皇を上位とした階級性の社会になっているという。
将軍もいるという噂もまことしやかに流れている。
「わしは、ここで無い世界の住人。主命により参上した」
「お前もアヤカシってわけか」
「左様。思う存分かかってこられよ。我も武技の粋を尽くしお相手いたそう」
「望むところだ」
マキシマム・揚とミフネの間に緊張感に満ちた空気が張り詰める。
「本気で行く」
声に合わせマキシマム・揚の握るスティングと左右前腕のスラッシャーが紫電を纏う。
マキシマム・揚が一気に間合いを詰める。
ミフネは、山の如く微動だにせずマキシマム・揚の剣を待ち受ける。
マキシマム・揚の握る長短合わせて四本の剣が飛燕の如き速さでミフネに向かって駆ける。
四本の剣が空に舞う燕のごとく奔放に軌道を変え縦横無尽にミフネに襲いかかる。
マキシマム・揚の剣が空を自由に舞う飛燕ならばミフネの大太刀は、獲物を正確に捉える鷹のようだった。
マキシマム・揚の剣をミフネの大太刀は、正確に捕え全て打ち払う。
四本の剣と大太刀が触れ合うたびに火花が散る。
「くっ」
マキシマム・揚の表情に焦りが見え始める。
今までミフネに打ち込んだ剣の回数は、すでに数え切れない。
更に完璧に自分の意を消して振るわれている剣の全てがミフネの体に触れることなく
大太刀に打ち払われる。それがマキシマム・揚の焦らせる原因だ。
マキシマム・揚の剣が今までにない強さで払われる。
マキシマム・揚の右腕が外に伸び体勢が崩れる。
ミフネが隙を見逃さずに裂帛の気合とともに袈裟掛けに斬りつける。
「ちぃっ」
マキシマム・揚が左腕前腕のスラッシャーで刀を受け止める。
火花が散りと鈴のような澄んだ音が響く。
スラッシャーの刀身がアスファルトに落ちる。
マキシマム・揚が後方に飛び間合いを取る。
そして左腕の斬られたスラッシャーの断面を見る。
断面は、鏡のように滑らかだった。
それは、恐ろしいほどの大太刀の切れ味とミフネの腕の確かさを示していた。
「化け物め。スラッシャーを斬るなんてな」
高速振動ブレードであるスラッシャーは、通常ならば触れ合った物を振動で速やかに切断する。
それを逆に斬るなどいうのは、もはや神技に等しい。
「まずお主の剣の一本をいただいた。わしの刀、雪月花に斬れぬ物はない」
ミフネが大太刀を肩に担ぐように構える。
「次は、お主の命をいただく!」
ミフネが疾風の如く駆ける。
「なめるなっ!」
マキシマム・揚も駆け出す。ミフネの大太刀が美しい弧を描き振り下ろされる。
マキシマム・揚が右腕前腕のスラッシャーをかざしミフネの大太刀を受け止める。
再びスラッシャーがミフネの大太刀によって刀身を斬られる。
「二本目、いただいた!」
「これ以上させるかよっ!」
マキシマム・揚が残った左右二本のスティングを振るう。
速度は、変わらないが先ほどと違い二本の剣を失ったことにより軌道の変化が単純に
なっている。ミフネが即座に軌道の変化を読み大太刀で打ち払う。
マキシマム・揚も読まれぬように戻した腕を次に振るわずかな間に手品のように
スティングを順手から逆手に持ち替え振るタイミング、軌道を変化させる。
それでもミフネは、山のように微動だにせずスティングを打ち払い続ける。
マキシマム・揚の体が独楽のように回転する。
ミフネの足を払い体勢を崩すため右下段回し蹴りを放つ。
ミフネが宙に飛び下段回し蹴りをかわし大太刀を上段に振り上げる。
雪崩のような勢いでマキシマム・揚に太刀が振り下ろされる。
マキシマム・揚がミフネの太大刀を二本のスティングを十字に重ね合わせ受け止める。
マキシマム・揚の目の前で火花が散る。
ミフネの全体重が乗った衝撃を支えきれずマキシマム・揚が右膝をつく。
マキシマム・揚がついた右膝を軸に左足を伸ばし水面蹴りでミフネの足を刈る。
山のように微動しなかったミフネが体勢を崩す。
ミフネの体勢が崩れたのに合わせマキシマム・揚がアスファルトを転がり間合いを取る。
マキシマム・揚が立ち上がる。汗が雫となってアスファルトに落ちる。
「四本、いただいた」
ミフネが低い声で言った。
マキシマム・揚が握っているスティングに目をやり舌打ちする。
スティングの刀身は、折られておらずまだ存在する。
しかし刃が所々砕かれ鮫の歯のような姿になっている。
マキシマム・揚がスティングをアスファルトの投げ捨てる。
「わかったぜ。あんたの大太刀の正体が」
「ほう?」
「高速振動剣を断ち切り単分子ナイフの刃を砕く化け物じみた切れ味に刃毀れしない
その硬度。思い当たるのはただ一つ。ダマスカス鋼を使った大太刀だろう」
ダマスカス鋼とは、古の時代に作り出された鋼であり現在でもその製法は、解明されていない伝説の鋼だ。
この鋼を使った剣は、鉄鎧を紙のように両断し刃毀れすることはないという。
そして刀身には、美しい波模様が表れるという。マキシマム・揚の言葉にミフネが頷く。
「いかにも。わしの刀、雪月花の刀身は、ダマスカス鋼でできておる」
ミフネが雪月花の刀身を指でなぞる。
「だがそれがわかったとてどうする? 禁軍武術師範!」
「武器が何で作られているかわかれば対処のしようもある」
マキシマム・揚が両腕を振る。
ジャケットの袖に隠してあった単分子ワイヤー・スネイクの柄が手に滑り落ちてくる。
「刀身は、叩き斬られ刃は、砕かれる」
言葉と共に二本のスネイクが風を切って飛ぶ。
「ならばこのしなやかなワイヤーならばどうする? ミフネ!」
「むう」
ミフネが唸り大太刀を振るいスネイクを弾き返す。
その隙にもう一方のスネイクが別方向より迫る。
ミフネが後退しスネイクをかわす。
鞭であるスネイクは、ミフネの大太刀が振るう速度を上回り鞭特有のしなやかさのおかげで大太刀の切れ味によって切断されることも無い。
ミフネの身を捕えることは無いが攻防の主導権は、マキシマム・揚が握った。
マキシマム・揚が決着をつけるべく勝負に出た。
二本のスネイクと大太刀が激突する瞬間にマキシマム・揚が手首を返す。
スネイクが大太刀の刀身に蛇のように巻きつき大太刀の動きを封じる。
「もらった! 奔れ、雷!」
声とともにマキシマム・揚の周囲の空気が帯電し耳障りな音を発する。
マキシマム・揚の赤い髪が怒りを表すように逆立つ。
マキシマム・揚の腕から紫電が放たれる。紫電がスネイクを通してミフネに向かう。
青い閃光がミフネを包む。ミフネが苦痛のうめきを上げる。
マキシマム・揚が勝利を確信したように薄く笑う。
ミフネが大太刀の切っ先をアスファルトに突き刺す。
紫電が大太刀を伝わりアスファルトに流れる。
マキシマム・揚が舌打ちすると紫電を放つのを止める。
その瞬間を待ちかねていたようにミフネが太刀の切っ先をひねりそのままアスファルトに
向かって大太刀を倒す。
アスファルトと大太刀に挟まれ刀身に巻きついていたスネイクが切断される。
「これで全ていただいた。まだ戦うか?」
ミフネが大太刀を鞘に収め低い声で告げる。
マキシマム・揚が握っていたスネイクの柄を離す。
渇いた音と共にスネイクがアスファルトに落ちる。
そしてマキシマム・揚がくぐもった声で笑いを漏らす。
「何がおかしい?」
ミフネの声にマキシマム・揚が笑いを止め顔を上げる
「まだ戦うかだと? 当然だ」
「武器を全て破壊されてもまだ戦うと?」
ミフネが戸惑った声で言った。
「侍のあんたに教えてやろう。刀は、侍の魂らしいが俺は違う。武器は全て手の延長だ。故に俺の武器は、ここにある」
マキシマム・揚が拳を胸の前に掲げる。
「指が一本でも動くかぎり俺は、戦い続ける。俺の武器を全て砕きたければ」
マキシマム・揚が自分の心臓を指差す。
「俺の魂を砕いてみせろ」
ミフネが天を仰ぎ愉快そうに声を上げ大笑する。
「その覚悟、見事。我が奥義を持ってその魂を砕こう」
ミフネが腰を落とし大太刀の柄に手を添える。
マキシマム・揚に向かって叩きつけていた殺気が林の如く静かになっていく。
マキシマム・揚が拳を握りその手に紫電を宿す。
二人の間の空気が凍りついていく。ミフネがじりじりとすり足で間合いを詰めていく。
マキシマム・揚は、自分がミフネの一足一刀の間合いにを入るのを待っている。
一足一刀の間合いとは、一歩踏み込めば相手に致死の斬撃を叩き込める間合いのことだ。
当然、大太刀を持っているミフネの方が間合いは広い。
マキシマム・揚は、ミフネが大太刀を振るより早く一撃を叩き込むつもりで待ち構えている。
ミフネの一刀一足の間合いにマキシマム・揚が入る。
同時にマキシマム・揚が電光石火の速さで駆ける。
ミフネは、まだ大太刀の柄に手を添えたままだ。
マキシマム・揚がミフネに向かって拳を放つ。
次の瞬間、マキシマム・揚の体に衝撃が突き抜け後ろに吹っ飛ばされる。
マキシマム・揚が最後に見たミフネの姿は、大太刀に手を添えた姿だった。
大太刀を抜く瞬間を目撃していない。その姿だけがぽっかりと抜け落ちている。
マキシマム・揚がアスファルトを転がりそのまま倒れ伏したまま動かない。
マキシマム・揚の様子を見てミフネがようやく構えを解く。
ミフネがマキシマム・揚に背を向け先にビルに入っていった二人を追いかけるべく入り口に向かって歩み始める。
「痛ぇ」
小さな声だった。ミフネが足を止め振り返る。
そこには、ゆっくりと立ち上がるマキシマム・揚の姿があった。
何度か咳き込み不味そうに血をアスファルトに吐き捨てる。
胸から腹にかけて斬ったことを示すように斜めに服が切れている。
大太刀の切れ味を示すかのように着込んでいた鎖帷子が裂けその下のマキシマム・揚の皮膚に下から上に向かって
斜めに赤い線が刻まれ血が流れ出している。
マキシマム・揚がわき腹に手をやり苦痛に顔を歪める。
衝撃で肋骨も何本か折られているようだ。
「俺が踏み込んだ分だけ浅かったな。ミフネ、もう一度だ」
マキシマム・揚が挑発するようにくいくいと指を曲げて手招きする。
「切り結ぶ刃の下ぞ地獄なれ、身を捨てて浮かぶ瀬もあれ、か」
ミフネが面白そうに呟き低く笑う。ミフネが腰を落とし大太刀の柄に手を添える。
マキシマム・揚は、構えず手を下げる。いつもの剣を振る時の構えだ。
ミフネがすり足でじりじりと間合いを詰め始める。
「最後にもう一度だけ聞いておこう。まだ戦うか?」
マキシマム・揚が精神を集中するように瞑目する。
「俺は、カタナだ。戦い始めた以上どちらかが死ぬまで戦う」
マキシマム・揚が閉じていた瞳を開ける。
開いた瞳にも表情にも何の感情も無かった。
その顔は、悟りを開いた高僧のように落ちつき静かだった。
ミフネがマキシマム・揚を一刀一足の間合いに捕える。
ミフネの右手が大太刀の柄を握り鯉口を切る。
マキシマム・揚は、電光石火の動きで踏み込む。
ミフネの大太刀が鞘走り加速し抜き放たれる。
マキシマム・揚の耳に大太刀の風切り音が入ってくる。
ミフネの大太刀がマキシマム・揚の命を砕くべく迫る。
マキシマム・揚の右足が力強くアスファルトを蹴る。
ミフネの大太刀がマキシマム・揚の皮膚に触れる。
マキシマム・揚の右足が紫電を纏い駆け上がる。
大太刀の鋭い刃がマキシマム・揚の皮膚に食い込み始める。
ミフネの首元から落雷のような打撃音が響きわたる。
ゆっくりとミフネが膝からアスファルトに崩れ落ちる。
マキシマム・揚が右足をアスファルトに下ろす。
全ては、二秒にも満たない刹那の瞬間の出来事。
「見事」
ミフネが呟き大太刀を鞘に戻しアスファルトに正座する。
マキシマム・揚もアスファルトに倒れるようにどっかと腰を下ろす。
そして行儀悪く胡座を組む。
「何故、奥義を破ることができた?」
「最初に食らった時、あんたが大太刀を抜く姿だけが見えなかった。それで気がついた。
全ての動作を無駄なく高速無比に行う居合い抜きだと。俺の兄弟子にも神業のような
居合いの使い手がいるからな」
マキシマム・揚が勝ち誇るでもなく淡々と告げる。
「勝ったのは・・・運がよかっただけだ」
「ほう」
「何も考えずにただ無我夢中で蹴りを出しただけだ。
それが一瞬速くあんたに当たっただけだ」
ミフネが面白そうに笑う。しばらく笑うと大太刀を腰から外しマキシマム・揚に差し出す。
怪訝な顔でマキシマム・揚が差し出された大太刀を見つめる。
「この刀でわしの首を取り後世の誉れにするがいい。お主の勝ちだ」
ミフネが一点の曇りも無い晴れ晴れとした声で言った。
マキシマム・揚が大太刀を受け取り立ち上がりミフネの後ろに回る。
大太刀を抜き放ち上段に構え振り下ろす。
大太刀は、ミフネの首の寸前で止まる。
「たまたま運良く一回勝っただけだ。首まで貰うほど価値があるもんじゃない」
マキシマム・揚が大太刀を鞘に戻す。
「どちらかが死ぬまで戦うと言ったのはお主だ。よもや二言があるとは言うまい」
ミフネが振り返り厳しい声で追求する。
「魂なら貰った。この大太刀だ」
マキシマム・揚が重そうに大太刀を肩に担ぐ。。
「刀は、武士の魂。それを差し出したってことは、命を貰ったってことだ。
それに一回の勝ちで二つの物を貰うのは俺の主義じゃない」
マキシマム・揚がにやりと笑う。
「武士としてのあんたは死んだ。文句は無い筈だ」
ミフネが小さな声で笑う。それは次第に大きな笑いになった。
「見事。なればその刀、お主に預けておこう。いずれまた貰い受けにくる」
ミフネの姿が風景に溶け込むように消えていく。
「次は、実力で勝ってあんたの首を貰うさ」
マキシマム・揚が力強く言い放つ。
ミフネの姿が消え去るとその場に力尽きたようにがっくりと片膝をつく。
「ちっ。無理しすぎたか」
IANUSが体の異常を感じ取り全て戦闘用サイバーウェアを強制終了させる。
そしてIANUSが体の異常を告げるワーニングをがなりたてる。
痛みが焼かれるように熱さで自己主張し鉛のような疲労感が体を押し潰そうとする。
「一角獣は、乙女との約束を破らないか・・・」
マキシマム・揚が自分に言い聞かせるように呟くと大太刀を杖のように突き立ち上がった。
シーン10 LORD OF GARD〜あなたこそ守るべき我が君主なり〜に戻る
シーン12 Order Of Kight〜騎士の使命〜に進む